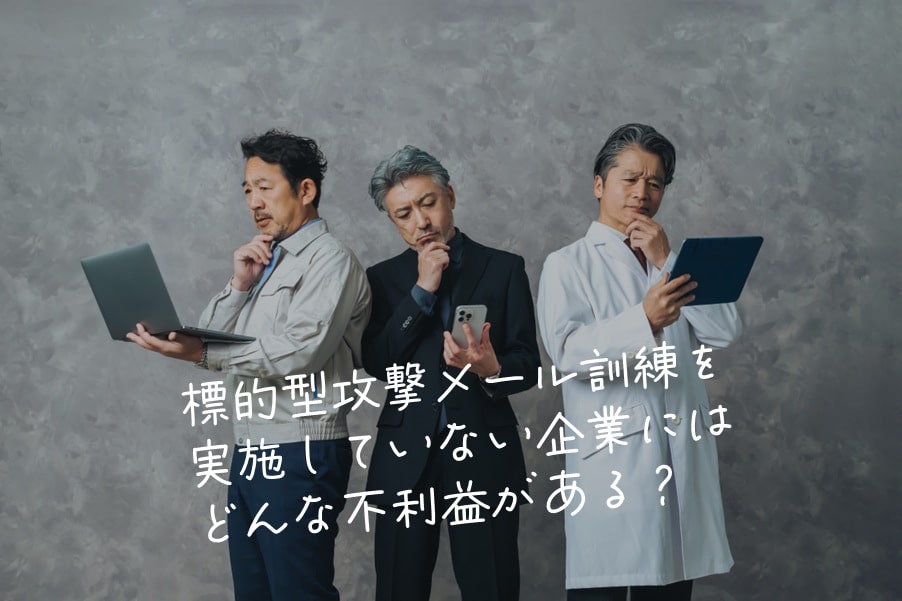
“格付け制度”やサイバー保険との関係から考える、これからの企業リスク
🧐 いま、なぜ訓練が注目されているのか?
近年、企業を狙った標的型攻撃メールがますます巧妙化しており、
その**“入口”となるのは、いつも社員が受け取る一通のメール**です。
こうした攻撃に備えるため、社員に対して“模擬攻撃メール”を送信して訓練を行う
**「標的型攻撃メール訓練」**を実施する企業が増えています。
しかしその一方で、まだ訓練を実施していない企業も多く存在します。
今回は、訓練をしないことで**将来的にどんな不利益が生じる可能性があるのか?**を、
公的制度や保険の最新動向をふまえて解説します。
🚫 訓練未実施の企業が直面するかもしれない“3つの不利益”
✅ ① 取引先・顧客からの【信用リスク】
最近では、企業のセキュリティ体制が
**“取引判断の基準”**として見られることが増えています。
- 取引先から「セキュリティ対策チェックシート」の提出を求められた…
- サプライヤー調査票に「訓練の実施有無」が記載されていた…
こうした経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
訓練をしていない=社員教育が不十分なリスクのある企業と見なされ、
新規取引の機会を失ったり、既存取引が見直される可能性もありえるかもしれません。
✅ ② 経済産業省が進める「セキュリティ対策格付け制度」への影響
ご存じでしたか?
📣 経産省は今、企業のサイバーセキュリティ対策を「見える化」する制度の検討を始めています。
この制度では、以下のような項目が“格付け”の対象に含まれると想定されています。
- セキュリティポリシーの整備状況
- 対応体制(CSIRT等)の有無
- 社員へのセキュリティ教育・訓練の実施状況
つまり──
💬 「標的型攻撃メール訓練をしていない」というだけで、格付けが低く評価される可能性もあるということです。
将来的にはこの格付けが、以下のような場面で使われる可能性があります。
- 融資や補助金の審査
- 取引先選定・調達判断
- 上場企業としての評価
✅ ③ サイバーセキュリティ保険の【加入条件】や【保険料】への影響
近年、サイバー攻撃による被害が急増し、
サイバー保険に加入する企業が増えています。
ところが…
🛡️ 一部の保険会社では、加入条件に「訓練の実施有無」を問う項目が!
たとえば以下のようなことが実際に起きています:
- 訓練を実施していれば、保険料が割引に
- 訓練未実施の企業は、補償対象から一部除外
- 契約更新時に、リスク評価としてマイナスポイントに
これは、保険会社の立場になって考えれば当然とも言える話ですよね。安易に補償費用を払っていたら保険会社は潰れてしまいますから、事故が起きそうな企業とは契約したくない、契約するのであればそれなりの保険料を払ってもらうか、補償対象外の条項を設けないと割に合わないというわけです。
実際、ある保険会社では訓練を実施したことのエビデンスとして、訓練実施結果のデータの提出を求めるということが行われており、そうしたデータの提出に協力したこともあります。
逆に企業の立場から見れば、訓練をしているということは、保険を契約する際においては経済面などで有利に働く要素と言えます。
📉 被害が起きてからでは遅い─“備えないこと”がリスクになる時代
実際のサイバー攻撃事件の多くは、
- 社員がメールのリンクをうっかりクリック
- 添付ファイルを何気なく開いてしまった
という、人の行動によって引き起こされています。
訓練を実施しておらず、クリック率が可視化されていない企業は、外部から見ればサイバー攻撃を受けた場合にどれくらいの確率で被害に遭ってしまいそうなのか?が皆目わからないということになります。
そうした不安要素が取引においてはマイナスに働いてしまいかねないというのは、誰にでも容易に想像が付くかと思います。
🧠 訓練を通じて、社員が「引っかからない力」を身につけることが、会社全体の守りにつながるのです。
📊 訓練未実施のままだと…経営面のリスクがじわじわと
| リスクの種類 | 想定される不利益 |
|---|---|
| 信用評価 | サプライヤー登録・調達対象から外れる |
| 規制・制度対応 | 格付け制度で低評価、補助金審査に不利 |
| 金融・保険 | サイバー保険の保険料が高くなる/補償範囲が狭くなる |
| 社内体制 | インシデント時に社員が正しく対応できず被害が拡大 |
💡 まとめ:「訓練」は“やるべきこと”ではなく、“やっておかないと損すること”に
これまでの情報をまとめると──
- ✅ 取引先や金融機関の評価に影響
- ✅ 経済産業省の格付け制度で不利に
- ✅ サイバー保険の保険料や補償にも影響
つまり、訓練をしないことで“選ばれにくい企業”になってしまうリスクがあるのです。
今や「サイバー攻撃を受けるのは当たり前」、
だからこそ、“どう備えているか”が問われる時代です。
オンライン研修教材を提供し、社員個人の自助努力に任せる、また、集合研修などを開催して座学で学ぶといったやり方で社員の情報セキュリティリテラシーを高めるということを積極的に進めていただくことはもちろんですが、標的型攻撃メール訓練など、身についているであろう知識を実戦で試す場を提供し、業務に活かせるレベルとして本当に身についているかどうかを、目に見える形で確かめることも、会社としては必要なことであろうと思います。





