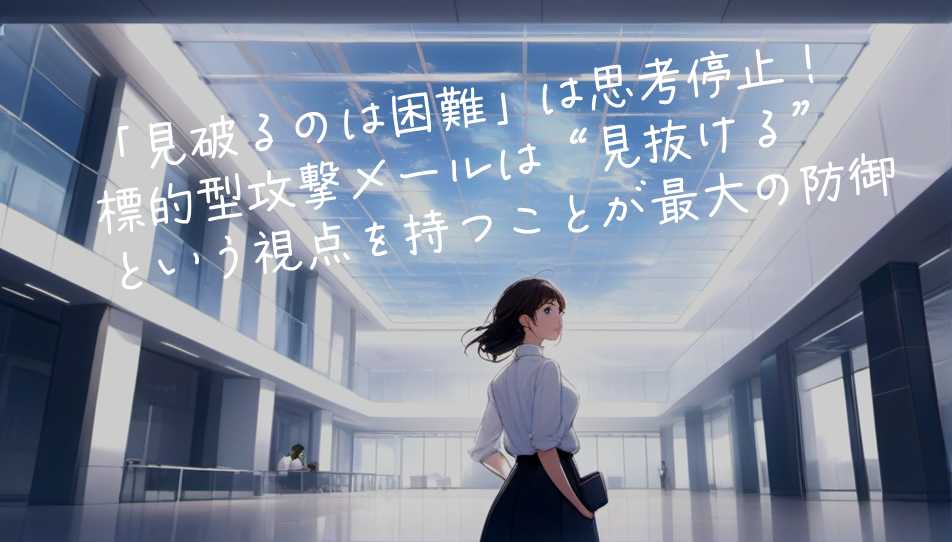
様々なメディアで耳にすることの多い
「標的型攻撃メールは見破るのが困難です」というフレーズ。
たしかに、攻撃者はメールの文面や送信元アドレスを本物そっくりに偽装してくるため、
一見して不審と気づけないケースもあります。
しかし、ここで危険なのは──
この言葉を**「だから仕方ない」「訓練しても無意味」**と受け取ってしまうこと。
それはまさに、**“思考停止”**の状態です。
「見破るのは困難」「見抜くのは不可能」こうした言葉をメディアなどで目にすることは多いですが、それは、ドメイン名とは何か?を知らないなど、インターネットを使う上で知っているべき知識を持っていない人に当てはまる言葉であって、全ての人に当てはまる言葉ではないと考えます。
専門家がこうした言葉を安易に使ってしまうことは、多くの人を思考停止状態にしてしまうという点で百害あって一利無しであり、専門家であるなら、こうした言葉の使い方を考えるべきではないか。ということを思わずにはいられません。
🟥 「見破れない」を信じると起こる3つの弊害
❌ ① 訓練が無意味に思える
→ 「どうせ見抜けないのだから訓練なんてしても…」と考えるようになり、組織全体の防御力が低下します。
❌ ② 判断を放棄してしまう
→ 「自分では気づけない」と思い込むと、不審なメールを受け取ってもスルーしてしまうリスクがあります。
❌ ③ 防御行動が鈍る
→ メールの内容を吟味する、添付ファイルを開く前に考える、報告する──こうした初歩的な行動すら行われなくなってしまいます。
🟩 では本当に見破れないのか?──答えは「No」
たしかに、一部の攻撃メールは非常に巧妙です。
しかし多くの標的型攻撃メールには、注意深く観察すれば気づける“違和感”が含まれています。
🔍 例えばこんなポイントに要注意
| ☑ 観察ポイント | 🔎 違和感の例 |
|---|---|
| 送信者のメールアドレス | 表示名は正しいのに、ドメインが似て非なるもの(例:@abc.co.jp → @abcc.co.jp) |
| 本文の言い回し | どこかぎこちない日本語や、不自然な敬語 |
| リンク先のURL | 表示URLと実際のリンク先が一致しない |
| 添付ファイルの種類 | .exe や .js など、業務上不要な実行形式ファイル |
| 強い誘導や催促 | 「至急対応してください」「いますぐ確認を」など、不安をあおる表現が多用されている |
🟨 実際に“気づけた”人もいます
標的型攻撃メール訓練を実施すると、
- 「普段の社内連絡と文体が違う」
- 「送信元が取引先と微妙に違う」
- 「URLをマウスオーバーしたらリンク先が変だった」
といった理由で、開封もせずに報告してくる社員が複数名は現れるものです。
→ 「常に疑う目線」を持っていれば、人は見抜くことができるのです。
本当に見破ることができないのなら、メールを読んでいない人や、対応を後回しにしている人を除けば、誰もが騙されてしまう結果となるはずです。
🟦 「このメール、もし不審なメールだったら?」という視点を
私たちに求められているのは、「100%の精度で見破る」ことではありません。
すべてのメールに“違和感センサー”を働かせることです。
📌 「このメール、もし不審なメールだったら?」
📌 「本当に自分が操作すべき内容なのか?」
そうした**“もしも”の目線**を持ってメールを見るだけで、
不自然な点に気づける確率はぐんと上がります。
✅ “不審さに気づくアンテナ”は訓練で高められる
「見破るのは困難」と言って諦めてしまうのではなく、
「見破ることはできるかもしれない」という可能性を持ち続けることが、
組織全体のセキュリティレベルを引き上げるカギになります。
標的型攻撃メールは確かに巧妙化していますが、
それに気づく力は「才能」ではなく、**“訓練や教育で身につけるスキル”**です。
繰り返し訓練や研修を行うことで、
社員一人ひとりの中に「違和感に気づくセンサー」が育っていきます。
そして、そのセンサーは「このメール、もし不審だったら?」という視点から始まります。
社員一人一人の“疑う目”が、組織の未来を守ります。





