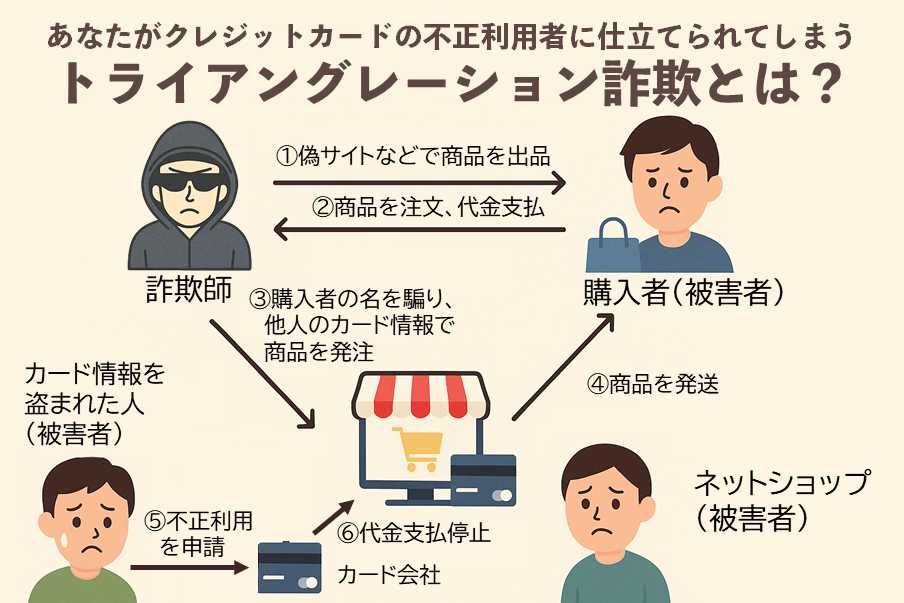✅「怪しいサービス」を使うとは限らない時代
「GoogleカレンダーがマルウェアのC&Cサーバに利用された」
そんな衝撃的なニュースが報告されました。
【参考リンク】
Googleカレンダーを悪用するマルウェアが登場 カレンダーが「悪のサーバ」に変化(キーマンズネット)
🧨 **C&Cサーバ(コマンド&コントロールサーバ)**とは…
感染した端末に命令を送るための“司令塔”のような存在。
これまでは、不審な外部サーバに接続する通信が検出されればマルウェアと疑うことができましたが、
Googleカレンダーのような正規のサービスを介した通信であれば、
セキュリティシステムですら“通常の業務利用”と見なしてしまう可能性があります。
つまり、攻撃者は…
🔐 「信頼されているサービス」を“悪用する”ことで、監視をすり抜けてくるのです。
💡攻撃者は“あらゆるもの”を悪用する
Googleカレンダーの事例は、氷山の一角にすぎません。
以下のような私たちが普段使っているサービスも、実は悪用の対象になることがあります。
🧰 攻撃者に悪用される“正規サービス”の例
| サービス | 悪用方法 |
|---|---|
| Googleカレンダー | C&C命令を記載し、感染端末が取得 |
| Google Docs / OneDrive | マルウェアをホスティングして配布 |
| Slack / Discord | 情報漏えい先、通信経路に利用 |
| GitHub | 攻撃コードを正規ファイルのように公開 |
| Dropbox / WeTransfer | 社外からの不正ファイル共有 |
💬 どれも「使ったことがある」サービスではないでしょうか?
この手の悪用は昔からありましたが、様々なクラウドサービスが登場し、多くの企業の業務で使用されるようになってきたことで、攻撃者にとってはこれらのサービスが「攻撃のインフラとしてうってつけ」として悪用される時代になっているのです。
🧠 従業員が“今”知っておくべき3つのこと
セキュリティ対策はIT部門の仕事――
そんな時代は終わりました。攻撃は“人”を狙ってくるようになっています。
だからこそ、社員一人ひとりの「気づき」が企業を守る鍵になります。
① 「信頼できるサービス」だからといって安心しない
GoogleやMicrosoftのドメインが使われているリンクだからといって、無条件に開いてはいけません。
📩 例:Googleカレンダーの招待が届いた
→ でも、招待者が知らない人で、イベント内容が不自然…
そんなときは、「業務っぽいから開く」ではなく、「おかしいから相談する」判断が大切です。
② ちょっとした“違和感”を見逃さない
「ファイル名が文書なのに中身が画像」
「メールが社内っぽいのに、文体がどこか不自然」
「急ぎの連絡なのに、理由が説明されていない」
こうした**“違和感”に反応できるかどうか**が、防御の第一歩になります。
🔎 「いつもと違う」を見抜ける力を持つことが重要です。
③ わからない時は、自分で判断しない
セキュリティ教育で一番大切なのは、「不明なものに触れない」という自制力です。
そしてもう一つ重要なのが…
💬 「これは開いても大丈夫かな?」と思ったら、すぐに周りに相談すること。
- 上司に一言聞く
- 情報システム部門に報告する
- セキュリティ窓口に問い合わせる
このちょっとした確認が、大きな被害を未然に防ぐことにつながります。
🛡「気づける人」を育てることが最大の防御
いまや、セキュリティソフトやファイアウォールだけでは防ぎきれない攻撃が増えています。
とくに今回のような「GoogleカレンダーをC&Cに使う攻撃」は、見た目上は業務利用と変わりません。
だからこそ――
💡 “社員の目”による気づきが、最大の防御になるのです。
✅ 社員が意識すべき3つのこと
| 🔍 警戒ポイント | 📝 内容 |
|---|---|
| ✔️ 信頼できるサービスでも油断しない | 見慣れていても危険が潜む場合あり |
| ✔️ 「いつもと違う」に敏感になる | 違和感を見逃さない“勘”を鍛える |
| ✔️ 困ったら即報告 | セルフ判断せず、誰かに相談するクセを |
🎯 攻撃に備える“最初の一歩”は、擬似体験から
いくら注意喚起しても、「自分が被害に遭うわけがない」と思ってしまいがちです。
ですが、実際に「巧妙なメール」を受け取り、
「クリックしてしまった…」という体験をすると、
人は一気に警戒心を持つようになります。
教科書を読んだだけでテストで100点が取れる人は天才です。
しかし、そんな天才は滅多にいません。だから学生は問題集に取り組み、問題を解くという実践を通じて、学んだことを真の知識として身につけていくのです。
反面、社員教育の現場ではどうでしょうか?
教科書を読んだだけで100点が取れる人などいないのに、Eラーニングなどの座学で学ばせただけで、100点を取るようなことを期待していないでしょうか?
学生は進学したいという動機があるから自ら実践しようとしますが、
会社においては、自助努力を期待できるだけの動機を社員全員に求めるのは無理があるでしょう。
だからこそ、企業は学ぶ機会だけでなく、標的型攻撃メール訓練などの実践の場も合わせて提供することが必要だと考えます。
本当に“気づく力”を育てたいと考えるのなら、
疑似体験などを通じて学んだことを実践する場も提供する。
プロスポーツの世界で練習をしない選手などいません。そして、練習をすることも業務の一環です。
社員教育もそれと同様です。学びと実践(練習)の場は業務としてセットで提供すべきです。