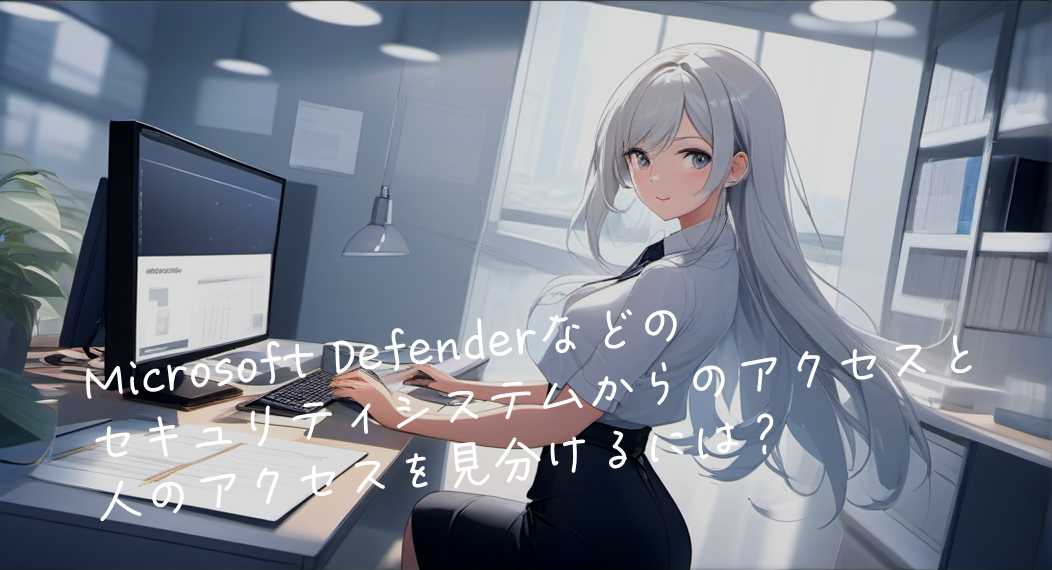🧠 セキュリティ意識の高まりは歓迎。でも、それが“暴走”に変わると?
セキュリティ意識の高まりは大歓迎──
…しかし、それが暴走した正義感となると話は別です。
実は、標的型攻撃メール訓練において、
「自分は会社を守っている」と信じて行動した社員が、訓練そのものを破綻させてしまうというケースがあります。
本記事では、
- 実際に起きた“暴走トラブル”の例
- なぜそのような行動が起きるのか?
- そして、訓練担当者が事前にできる予防策
について、具体的に考察します。
🚨 Case1|通報されたことでドメインが使用不能に…
ある企業では、標的型攻撃メール訓練の一環として、社内ユーザーに「不審なメール」を送信。
リンク先は安全な訓練サイトにリダイレクトされる仕組みでした。
ところが…
💥 1人の社員が訓練メールを本物のフィッシングと誤認し、
「これは危険なメールです」と、第三者機関に通報。
その結果、訓練で使用していた専用ドメインがブラックリスト入りし、以降の訓練で利用できなくなるという事態に発展しました。
訓練実施担当者からすれば、”リンクをクリックすれば「これは訓練です!」って表示されるのだから、フィッシング詐欺サイトじゃないってわかるでしょ!”と思うかもしれませんが、第三者機関はそこまで確認した上でブラックリスト入りさせるかどうかは判断していないようで、”疑わしきは罰する”で、とにかく止めてしまうことを優先させるようです。
XやYouTubeで、嘘の通報によるアカウント凍結の被害が発生している事例がありますが、これと同じようなことが標的型攻撃メール訓練においても起こりうるということです。
特に.xyzドメインはフィッシング詐欺で使われるケースも多いことから、一度ブラックリスト入りしてしまうと解除するのは容易ではなく、弊社でも使うのを断念せざるを得なかったケースもあるため、筆者の経験上、.xyzドメインを訓練で使用することは避けることをお勧めします。
📢 Case2|チャットで“ネタバレ”、訓練が全崩壊
別の企業では、ある社員が受信した訓練メールについて、社員が善意でこう発言。
「このメール、訓練じゃない?クリックしないように!」
その投稿が社内チャットで瞬く間に拡散し、
本来“気づかずに開くかどうか”を見るはずだった訓練が、社内全体にバレてしまい効果ゼロに。
その他にも、訓練メールが自分に届かないようシステムでブロックするように設定してしまった事例や、自組織の成績を良くしようと、内緒で事前に情報を共有していたといった事例などもあります。
🌐 Case3|SNSで訓練情報が流出、企業イメージに傷
さらに別の例では、社員が「また変なメール来た」とX(旧Twitter)に投稿。
添付されたスクリーンショットには、企業ロゴと訓練ドメインがしっかり映り込んでいました。
結果、訓練の意図も説明されぬまま情報が拡散され、
「こんな訓練してるの?」という声が外部に広がり、企業イメージの毀損へ…。
🧩 なぜ“暴走”が起きるのか?
「通報=悪いこと」とは限りません。
むしろ、通報しようという姿勢自体はセキュリティ意識の高さを示す証拠です。
しかし、それが組織のルールから外れて行動に移されてしまうと、“正義感の暴走”になります。
その原因は以下のような点にあります。
| 🔍原因 | 🔎説明 |
|---|---|
| 訓練の存在が知らされていない | 本物と思い込み、外部へ通報してしまう |
| 通報のルートが不明確 | 「どこに報告すべきか」が分からず、自己判断で外部機関へ |
| 訓練を“ゲーム”と勘違い | 「気づいた自分が勝ちだ」と種明かしを拡散する行動へ |
| 周囲を守りたい善意 | 仲間に注意を促すつもりが、訓練の妨げに |
🛡 社員の暴走を防ぐために、訓練担当者が事前にできる5つのこと
✅ 1.ネタバレしない範囲で、訓練実施を事前周知する
「当社では情報セキュリティ向上のため、今月中に標的型攻撃メール訓練を実施します」
というように、実施時期や存在のみを伝えることで、
社員に過剰な反応をさせずに、通報リスクを抑えることができます。
✅ 2.通報フローを明確に示す
「不審なメールを見かけたら、必ず社内のCSIRTチームもしくは情報システム部門に連絡を」
というように、社内通報のルートを明文化しておきましょう。
第三者機関への直接通報は原則NGであることも明示します。
これは標的型攻撃メール訓練に限らず、インシデント発生時の基本として徹底されるべき事柄です。
例えば、サイバー攻撃によって情報漏洩が起きてしまったことを、「被害に遭った」として社員が勝手に外部に通報してしまったらどのようなことになるでしょうか?
SNSが発達し、情報があっという間に拡散してしまう現代において、会社側の対応ができていない状況で情報だけが一人歩きしてしまうことは、会社に取り返しがつかない損害を与えてしまう結果にもなりかねません。
✅ 3.通報を責めず、導く研修を実施する
「通報した社員が悪い」のではなく、“通報の仕方”に誤りがあっただけ。
それを伝えるための研修も重要です。
例:
- なぜ社内報告が必要か?
- 外部に出すことで何が起きるか?
- 通報は“正しいルールの中で”行うことの意味
これは、訓練の中で伝えるだけでなく、入社時の研修から伝えるなど、社内の文化として定着するよう、日ごろから何度も繰り返して伝えていくことが大切です。
✅ 4.社内チャットでの情報共有に注意喚起を
訓練前のタイミングで、こんな一文を入れておくと効果的です。
「訓練期間中は、メールの内容を社内チャット等で共有することはお控えください。気づいたとしても、周囲の学びの機会を奪わないようご協力をお願いします。」
✅ 5.フィードバックは“一斉タイミング”で実施
訓練後に「種明かし」を行う際は、個別ではなく全員に同時通知を行いましょう。
一部の社員だけが先に知ることで、未受信者に拡散されることを防ぎます。
💡「正義感」は、組織のルールの中で活かしてこそ力になる
社員が通報してくれるのは、セキュリティに対する意識を高く持ってくれているという点で、ある意味訓練の成功です。でも、それがルール外の行動になったとき、訓練そのものが壊れてしまいます。
だからこそ、訓練実施者には、
- 社員の行動を責めるのではなく
- “正義感を正しい方向に導く環境”をつくること
が求められます。
🎯訓練設計の最終ゴールは「学びの最大化」と「信頼の維持」
訓練は「社員を試す」ものではなく、
「社員の力を信じて育てる」ものです。
暴走しない正義感を、会社の力に変えていく。
そのための工夫は、訓練の設計段階から始まっています。