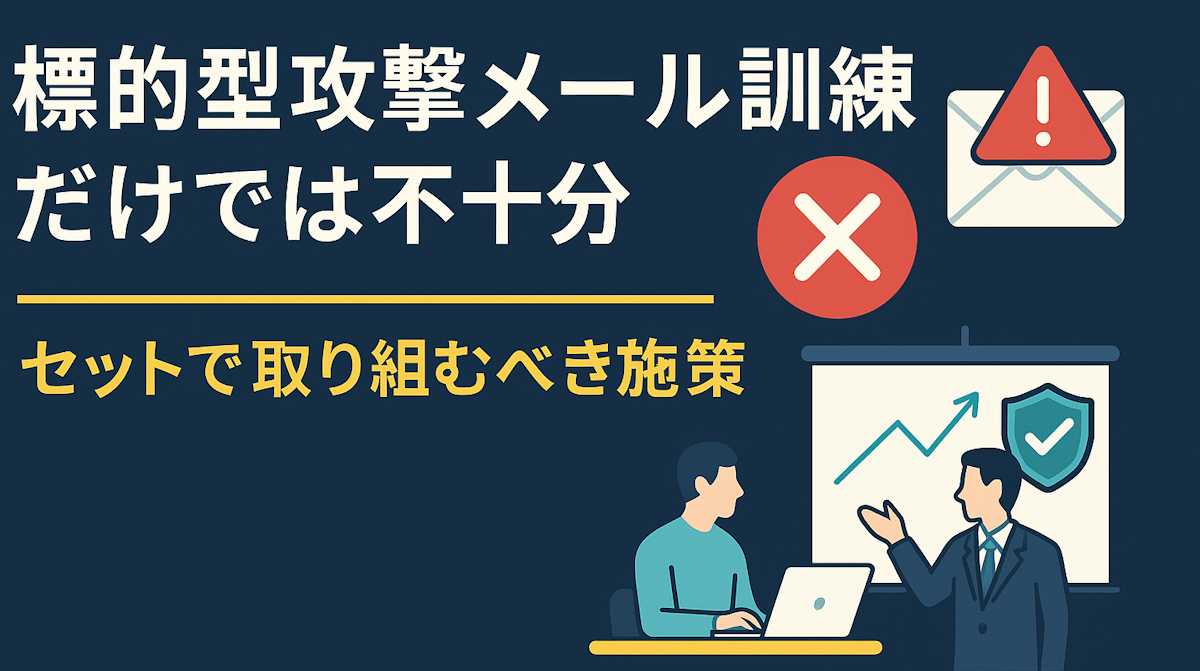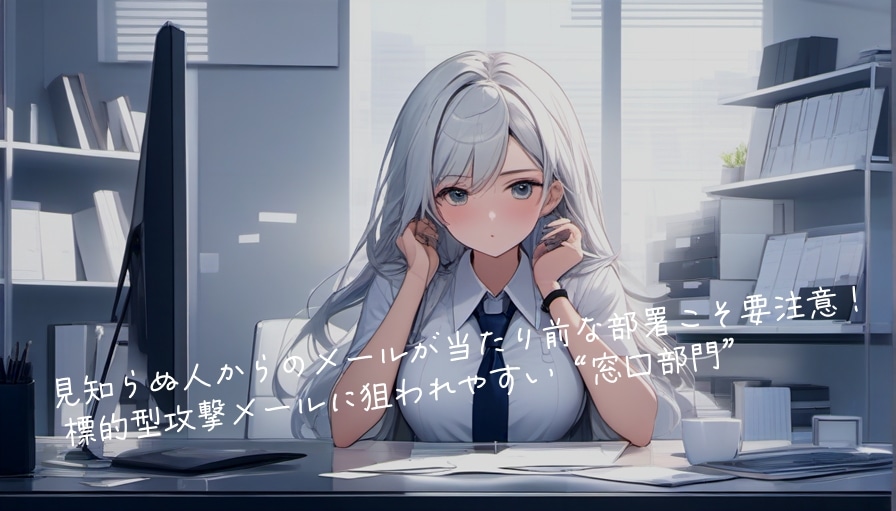
💬突然ですが、
あなたの会社で「見知らぬ人からのメールを日常的に受け取る部署」はどこでしょうか?
多くの企業では、
- ✅ メディア対応を行う広報・PR部門
- ✅ 応募者対応を行う人事・採用担当窓口
- ✅ 製品やサービスに関する問い合わせを受けるカスタマーサポート
- ✅ 新規取引や提案を受ける営業部門
- ✅ 採用エージェントやパートナー企業と接点を持つ経営企画部門や総務部門
などが、見知らぬ個人や外部組織から日常的にメールを受け取っています。
このような「外部との接点を持つ部署」は、標的型攻撃メールの入り口となる危険性が特に高いことをご存じでしょうか?
🎯実際にあった標的型攻撃の事例
■ 事例①:広報部門が狙われた取材依頼メール
とある上場企業の広報部門に、テレビ局を名乗る人物から「〇〇番組で貴社の取り組みを紹介したい」との取材依頼メールが届きました。添付されたPDFに企画書があるとのことで、広報担当者がファイルを開いたところ、実はそれがマルウェアの仕込まれた実行ファイルでした。幸い、EDRの検知により感染は防がれましたが、標的型攻撃の巧妙さを物語る事例です。
■ 事例②:人事担当に送られた“応募者を装った”攻撃
人材募集の応募者を装い、「履歴書をご確認ください」としてWordファイルを添付したメールが、大手企業の人事担当に届きました。ファイルを開くと、「マクロを有効にしてください」という表示。マクロを有効化すると、バックドア型マルウェアが実行され、外部からの侵入を許してしまったという事例です。
■ 事例③:営業部門宛の「見積もり依頼」に潜む罠
「新規取引を検討しています」という文言とともに、見積依頼書のダウンロードリンクが貼られたメールが営業部門に届きました。営業担当者はリンクをクリックし、ダウンロードしたファイルを開いたところ、ランサムウェアに感染し、社内の共有サーバーが暗号化されてしまいました。
いずれも、送信者が見知らぬ人でも違和感がない例です。
こうしたメールが日常的に送られてきている状況であれば、受け取り側は普段から受け取っているメールの一つとしか思わないので、いつもの流れで開いてしまうことは十分にあり得ることです。
⚠️「怪しくないメール」が一番危ない
これらの事例の共通点は、“一見して怪しくない”という点です。
攻撃者はターゲットの業務内容や担当者の役割を事前に調査し、違和感のないシナリオで近づいてきます。
だからこそ、日ごろから「怪しくないメールの中にこそ罠がある」ことを、社員に意識させておく必要があります。
🧠特に重点的に教育すべき部署
| 部署名 | 主な攻撃手法 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 広報・PR | 取材依頼、協業提案 | 添付ファイルやURLに注意 |
| 人事・採用 | 応募者を装った履歴書送付 | マクロ付きWordファイルの扱い |
| カスタマーサポート | 問い合わせを装ったウイルス添付 | 添付ファイルの拡張子に注意 |
| 営業・企画 | 新規商談・見積もり依頼 | 外部サイトへの誘導リンクに注意 |
コールセンターなど、見知らぬ人からのメールを日ごろから多く受け取っていて、且つ、人員の入れ替わりが頻繁に発生しているような部署は攻撃者から見れば狙い目の部署です。
従業員のセキュリティリテラシーレベルがバラバラで、管理する側もその状況を把握できておらず、教育も十分に行き届いていないとなれば、まさに穴だらけの状況と言えるからです。
✅教育のポイント
重点部門には、以下のような教育を行いましょう。
- 🔍 「業務内容に沿った偽メール」の例を交えた訓練
- 🎓 「業務に即した不審メールの見抜き方」の研修
- 🧪 定期的な標的型攻撃メール訓練
- 🛑 「ファイル開封前チェックリスト」の整備
標的型攻撃メール訓練というと、全社員を対象に実施するケースが多いですが、空き巣に狙われやすい家と狙われにくい家があるように、攻撃者も攻撃が成功しやすい相手を狙う方が効率的ですから、狙われやすい部署ほど優先的、且つ、重点的に対策を行うべきであるのは言うまでもないことです。
そして、そういった部署ほど重点的に対策を行っていると対外的に示すことで、攻撃者から狙われにくくなります。空き巣対策として窓用センサーライトを設置したり、防犯ガラスに変更するなど、犯罪者から見て侵入しにくそうな家だと思わせるのと同じ理屈です。
📝狙われるのは“窓口”から
サイバー攻撃者は、企業の「玄関」ではなく「裏口」や「応接口」から侵入しようとします。
つまり、外部からのメールを日常的に受け取る部署が最初の突破口になりえます。
だからこそ、広報、人事、営業、サポートなど、見知らぬ人からのメールが来ても不自然でない部署にこそ、日ごろからの意識づけと訓練が不可欠です。
自社の“情報の門番”である彼らを、まず守ること。
御社の窓口部門の担当者は、自分が最も狙われやすいことを日ごろから意識しているでしょうか?
既に訓練を継続的に実施している企業様で、まだ、全社員を対象とした一律の内容の訓練しか実施していないということであれば、全社員対象の訓練とは別に、重点部門を対象に個別に訓練を実施したり、訓練メールの内容を部門ごとにカスタマイズするなど、より踏み込んだ内容に進めてみてはどうかと思います。