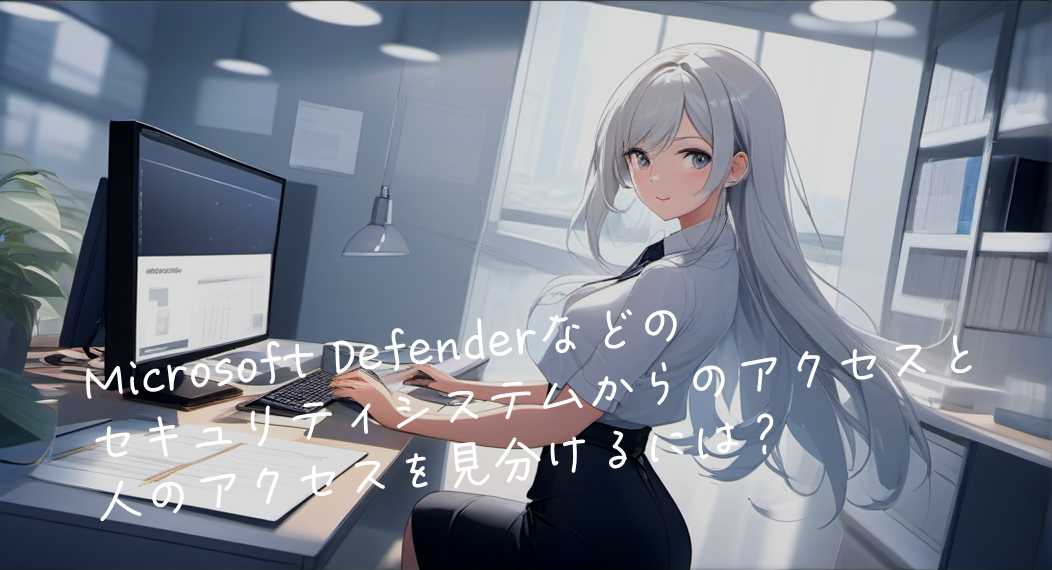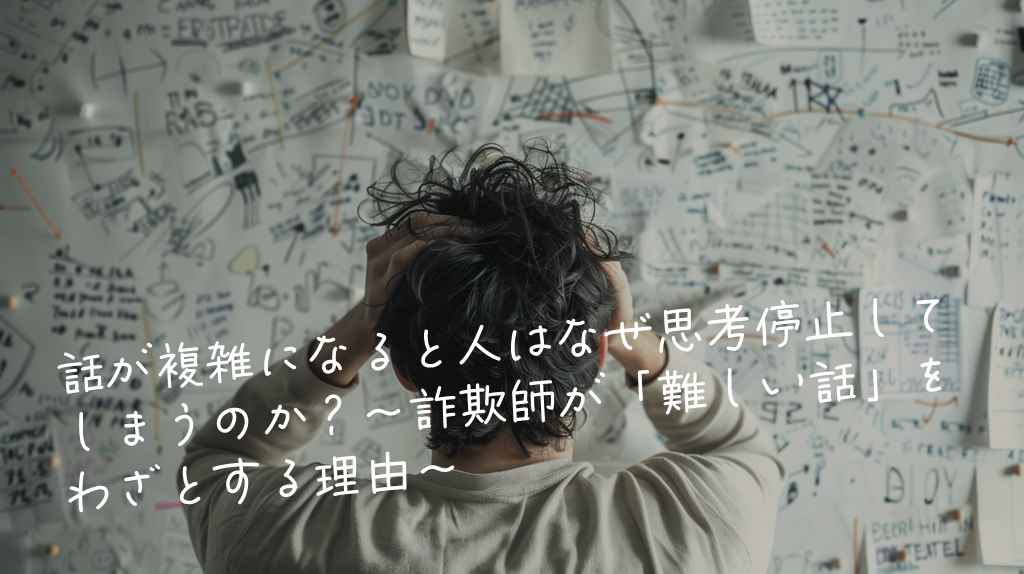
💬 「もう、よくわからないから…」それが一番危ない
あなたはこんな経験、ありませんか?
- 銀行や保険の説明がやたら長くて途中から話を聞くのをやめてしまった
- サポートセンターとのやりとりで、専門用語ばかりでついていけなくなった
- 契約書を読んでいて「よくわからないけどまあいいか」でサインした
このように、話が複雑になると私たちは“思考すること”をやめてしまいがちです。
そしてこれは、実は心理学的に見てもごく自然な反応であり、
それを巧妙に突いてくるのが詐欺師たちなのです。
🧩 認知的負荷:脳の処理能力には“限界”がある
私たちの脳には、処理できる情報量に限界があります。
この「処理の限界」を**認知的負荷(Cognitive Load)**と呼びます。
情報が多すぎたり、複雑すぎたりすると、脳は「もうムリ!」と悲鳴をあげ、
思考をストップさせてしまうのです。
この状態になると、人は判断力を失い、
「言われるまま」「指示された通り」に行動してしまいます。
🎭 詐欺師がわざと話を難しくする理由
詐欺師は、「相手に理解させるため」に話をしているのではありません。
彼らの目的は、あなたを混乱させ、判断力を奪うことです。
👇 よくある詐欺のテクニック:
- 「専門的な話」を長々とする
- 契約や制度の説明をやたら複雑にする
- 難解な言葉やカタカナ語を多用する
- 焦らせて考える時間を与えない
「今すぐ対応しないと危険です」「本日中に手続きが必要です」「早い者勝ちです」
そんな言葉を聞いたとき、冷静に考える余裕がなくなっていませんか?
💥 思考停止に追い込む“3つの心理作用”
詐欺被害が発生する背景には、次のような心理的バイアスが関係しています:
🌀 1. 正常性バイアス
「まさか自分が詐欺に遭うなんて」という思い込みから、
異常事態を“普通のこと”として受け入れてしまう心理。
❌ 2. 意思決定回避
複雑な状況では、人は「どちらを選んでも間違いそう」と感じ、
判断を他人に委ねたくなる傾向があります。
→ 「よくわからないから言われた通りにした」などが典型。
🙈 3. 認知的回避
考えるのが面倒、不安、難しすぎる…
そんなストレスを避けるために、“そもそも考えること”を無意識に拒絶してしまうのです。
📖 実際の事例:ある中小企業社員の体験
50代のある社員が、パソコンに現れた「ウイルス感染警告」に驚き、
表示されたサポートセンターに電話してしまいました。
- 「遠隔操作でウイルスを除去します」
- 「必要なのはセキュリティソフトの登録料だけです」
- 「今処理しないとデータがすべて失われます」
頭では「こんな電話は詐欺だ」と知っていたはずなのに――
焦りと複雑な説明の連続により、思考が停止し、
気づけばクレジットカード番号を伝えていたのです。
🧘♂️ 複雑な話に出くわしたときの対処法
✅ 1. 「わからない」は“危険信号”だと捉える
理解できない話に対して「大丈夫だろう」とスルーせず、
「わからない=立ち止まるべき合図」と考える習慣を持ちましょう。
✅ 2. その場で判断しない
「今すぐ」が詐欺の常套句。
その場では絶対に決めない・送らない・話を進めない。
✅ 3. 他人の目を入れる
信頼できる第三者に相談すると、思考停止から脱するヒントが得られることがあります。
🔐 わからないことを“放置”しない勇気を
「なんとなくわからないけど…まぁいいか」
という気の緩みが、詐欺師にとって最高の隙。
- 話が難しいと感じたときは、一旦立ち止まることが最も賢明な選択です。
- 思考停止は、知識や経験とは無関係に誰にでも起きる現象です。
- そして、詐欺の手口はそれを利用するように設計されているのです。
これは何も詐欺に限った話ではありません。法律には触れていないが悪徳商法と呼ばれるもの、グレーに近いセールス話法、相手を煙に巻く話し方など、私たちの身の回りに日常的に存在しています。
「話が難しいときほど、立ち止まる」
これは、現代を生き抜くための大切な“防御の習慣”です。
社員研修や啓発活動では、詐欺の知識だけでなく、思考停止への対処法も教えることが、
本当の意味でのセキュリティ対策につながります。