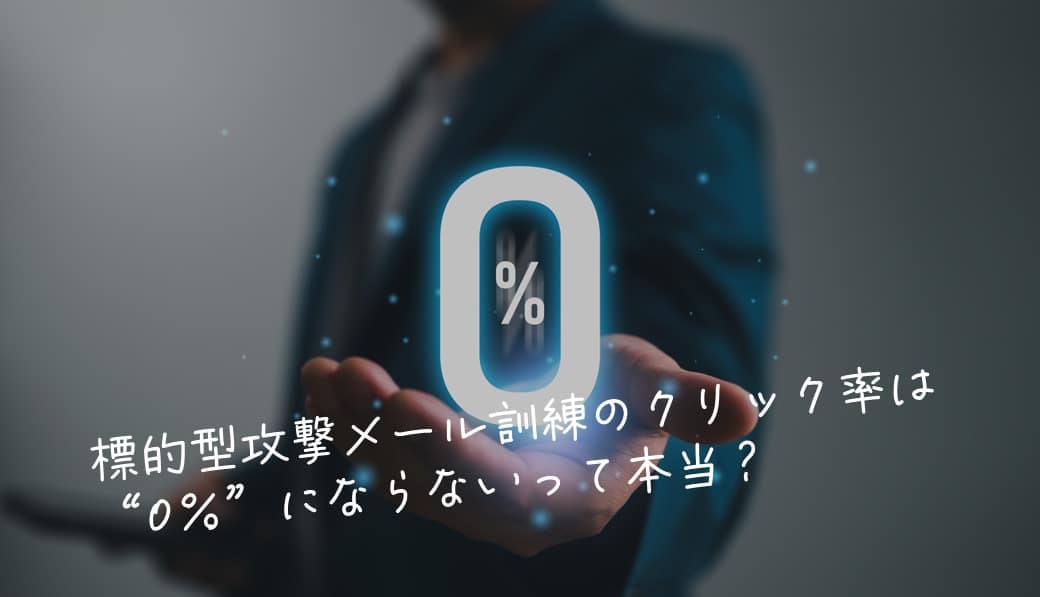
🔍標的型攻撃メール訓練における現実的な限界と考察
標的型攻撃メール訓練を実施する際、最も注目されがちな数値のひとつが**「クリック率」**です。
訓練の成果を測るために、「今回はクリック率10%」「前回より5%下がった」といった数値が報告されます。
そして多くの担当者が、一度はこう考えたことがあるはずです。
「最終的には、クリック率を0%にできたら理想だ」
しかしながら、現実にはクリック率が完全に0%になることは極めて稀です。
それはなぜなのか?本記事では、その理由を人間行動・攻撃手法の多様化・組織構造の観点から総合的に考察していきます。
📊 まず、実際の訓練結果データでは…
さまざまな業種・規模の企業で実施された訓練データをみると、一般的なクリック率の傾向は以下の通りです。
但し、以下の数値は正しい統計手法に基づいて算出されたものではなく、世間で流通している様々な話を総合すると大体以下のような感じでは無いか。というものに過ぎないので、この数値だけを見て良い・悪いを判断するべきではないということは申し上げておきます。
実際、筆者が訓練に関わっている企業では、クリック率が例年1%前後という企業もありますし、5~15%の間で推移しているという企業もあります。
| 実施タイミング | 想定される平均クリック率 |
|---|---|
| 初回訓練 | 約20〜40%前後 |
| 継続訓練(年2〜4回) | 約10〜20%程度に減少 |
| 安定運用企業(2年以上継続) | 5〜10%前後が多い |
訓練の難易度次第でクリック率も大きく変わったりしますが、いずれの段階でも、「0%」という数字はほとんど観測されない。というのは、筆者のこれまでの経験からも、確かにその通りだと言ってよいと思います。
🔍 クリック率が0%にならない3つの理由
✅ ① ヒューマンエラーの発生確率はゼロにはならない
人間は、どれだけ注意していてもミスを完全に防ぐことはできない存在です。
- 多忙なタイミングで判断が甘くなる
- 「急ぎ対応が必要」と書かれた件名に反射的に反応してしまう
- スマートフォンでの閲覧で、詳細を確認せずにタップしてしまう
こうした一瞬の判断ミスや思い込みは、どれだけ訓練しても完全には排除できません。
どれだけ世の中が進歩しても交通事故がなくならないのと同じです。
✅ ② 攻撃手法の高度化・多様化
標的型攻撃メールは、年々手口が巧妙になっています。
- 実在の取引先名を騙る
- 社内で実際にやりとりされるメールの内容を模倣
- 添付ファイルではなく、クラウド上のファイルへのリンクや認証画面を装う
このように、新たな“疑似正当性”を持つメールが次々と登場するため、訓練の経験だけでは対応しきれず、知っている手口には騙されないが、知らない手口には簡単に騙されてしまうといった場面が出てくるのです。
✅ ③ 社員のリテラシー・業務環境にばらつきがある
同じ会社であっても、社員のセキュリティ知識や業務習慣には大きな差があります。
- 営業部門はメールのやり取りが多く、スピード重視の傾向
- 内勤や管理部門は慎重な反面、メール開封率が高い
- 新入社員や契約社員はセキュリティ教育の浸透度が低いことも
こうした部門や個人の特性の違いがある以上、常に全社員が完璧な判断を下すことは現実的に困難です。
例えば、顧客対応をしているパート社員が、管理者から「送られてきたメールには漏れなく目を通すように」と指示されていたら、たとえそれが不審なメールだったとしても、”上からそのように指示されているから”という理由で開いてしまうことはあり得ます。
何故なら、ファイルを開くことが業務として指示されていることだからです。
管理者は「何でそんなファイル開くんだ!」と思うかもしれませんが、パート社員からすれば「漏れなく目を通せと指示されていたから開いただけ」ということだったりします。
🧭 クリック率“0%”より大切なこと
標的型攻撃メール訓練の目的は、「社員全員が1回も間違えない」ことではありません。
本来の目的は、
「なぜ引っかかったのか」を把握し、再発を防ぐしくみを整えること
です。
クリック率という“結果”だけでなく、以下のような行動や反応の質に注目すべきです。
その点では、クリック率0%は一見、嬉しい数値のように見えますが、引っかかった後の行動について測定・検証ができなかったという点では、残念な結果に終わってしまったとも言えます。
| 視点 | 評価ポイント |
|---|---|
| 報告行動 | 不審メールを報告した人の割合は? |
| 判断理由 | クリック・非クリックの根拠を社員自身が説明できるか? |
| 組織反応 | 情報共有や周知のアクションはあったか? |
🛡️ 組織として取るべき次の一手
クリックを完全にゼロにするのではなく、**「クリックされても事故に発展させない体制づくり」**が重要です。
- ✅ メール通報ルールの明確化
- ✅ 内部通報・報告のしやすい仕組み
- ✅ クリック後の早期検知・対応フローの整備
- ✅ 継続的な訓練とフィードバックを通じた文化づくり
ヒューマンエラーを前提としながらも、システム・組織・教育の3方向からリスクを抑えることが、現実的かつ持続可能な対策であると考えます。
📘 まとめ
クリック率0%は本当にあり得ないのか?というと、全く無いということはなく、実際、筆者が関わった訓練でもクリック率が0%の結果となったケースはあります。
とはいえ、その数は非常に少なく、大抵は誰かしらクリックしてしまうというのがほとんどです。
そもそも、こういったメールが送られてきたら自社の社員は騙されてしまうこともあり得るはずだ。という想定の元でシナリオを設計するわけですから、クリックしてしまう人が出るのはむしろ当然と言えます。
| 観点 | 要点 |
|---|---|
| ❌「クリック率0%」の誤解 | 人間の特性上、現実的には困難 |
| ✅ 真に見るべき指標 | 行動の質・報告率・再発防止の視点 |
| 🛡 今後の方針 | ゼロエラーを目指すのではなく、誤クリックを想定した体制づくり |
クリック率が0%になることを目指して教育や訓練を実施すること自体は良しとしつつも、クリック率を0%にすること自体は達成すべき目標ではありません。
組織としては被害を出さないこと、万一、被害に遭ってしまったとしても最小限の被害で留められることこそが本来あるべき姿なのだと考えれば、クリック率0%にこだわる必要など無いのです。





