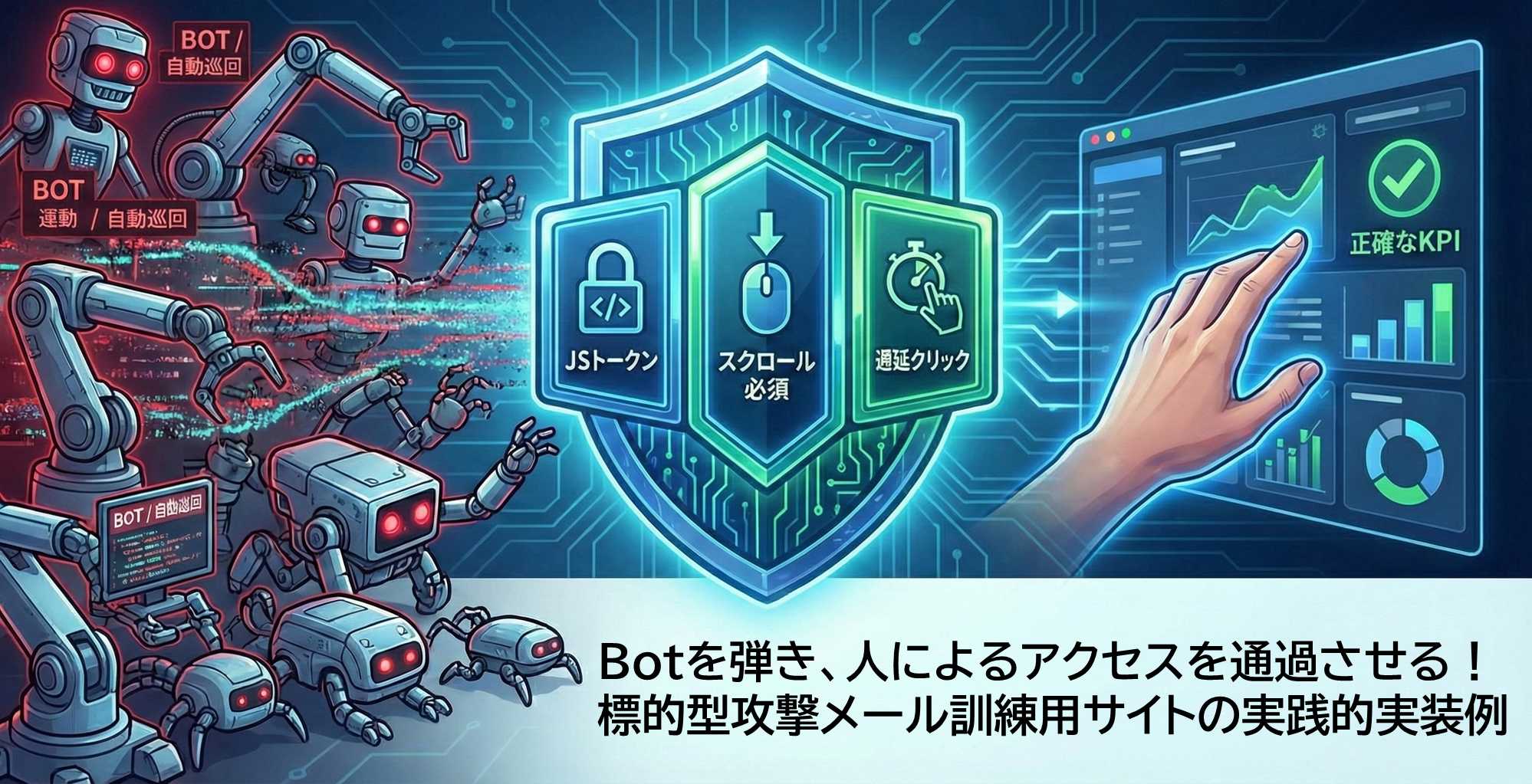〜訓練自動化のメリットと注意点をやさしく整理します〜
標的型攻撃メール訓練を担当していると、意外と手間のかかる作業が多いと感じることはありませんか?
訓練メールの作成、配信、社員の反応チェック、報告書の作成…。それに加えて「また次回も準備しないと」と考えると、なかなかの負担です。
そんなときに目にするのが、「訓練の自動化」という言葉。ツールを使って自動で訓練を実施できれば、ずいぶん楽になるのでは?と思う方も多いと思います。
実際、訓練を自動化できることを売りにしたシステムを採用した、もしくは、採用候補として考えているという企業もあるでしょう。
確かに、自動化にはたくさんのメリットがあります。でも一方で、気をつけておきたいポイントもあるのです。
今回は、訓練自動化のメリットとデメリットをわかりやすく整理しながら、「自動化すべきか?」を一緒に考えてみましょう。
✅自動化すると、こんなにラクになります(メリット)
● 作業時間が大幅に減る!
あらかじめテンプレートや送信スケジュールを設定しておけば、あとは自動でメールが送られ、結果もレポートとしてまとめてくれます。忙しい担当者にとって、これはとてもありがたい機能です。
最近はAIと連動して、条件に応じて送信する訓練メールを動的に設定することを売りにしているシステムもあるようなので、運用はシステムに任せられるというのはとても便利だと言えます。
● 定期的な実施がしやすくなる
自動で月1回、四半期ごと、年に数回とスケジュール設定できるので、「忙しくて今年は訓練をやれなかった…」という事態を防げます。
● 結果の分析・報告がカンタンに
クリック率や部署ごとの傾向などを自動で集計してくれるので、経営層への報告もしやすくなります。
🤔でもちょっと待って!自動化にも落とし穴があります(デメリット)
● 内容がマンネリ化しやすい
いつも同じテンプレートメール、同じタイミングだと、社員に“訓練メールだ”と見抜かれてしまい、警戒心も薄れてしまうことがあります。
● 一人ひとりの反応を深く見るのが難しい
自動で結果は出ますが、「なぜその人が引っかかったのか」「どうフォローすべきか」までは分かりません。フォローの質が下がることも。
また、結果についてはいつでも見ることができるという安心感から、担当者も「後で結果を見ればいいや」と後回しにしてしまい、忙しさに追われて結局、ほったらかしとなってしまうということもあります。
● 想定外のトラブルに気づきにくい
メールが届かない、リンクが正しく動作しないなどのトラブルが起きても、自動で進んでしまうと気づくのが遅れることがあります。
💡自動化がうまく機能するケースとは?
以下のような状況であれば、自動化のメリットを活かしやすいです。
- 訓練を定期的に続けたいけれど、人手が足りない
- 全社的な傾向を把握して、次の施策に活かしたい
- ある程度、訓練の運用が社内に定着している
こうした場合には、自動化が「楽になるだけでなく、効果も安定する」ことが期待できます。
📌逆に、“手動で実施”したほうがいい場面もあります
- 新入社員や特定部署に向けた個別の訓練
- 実際にトラブルが発生した直後の緊急対応訓練
- 「なぜこの社員が引っかかったのか」を深く分析して対策を考えるとき
こうした場合は、手間がかかっても人の目と判断が大切になります。
一人一人の社員に向き合うように、手動で調整しながら訓練を実施することで、個々の部署のセキュリティリテラシーのレベルや、どのようなメールに騙されてしまいやすいか?といった特徴など、クリック率などの結果からだけでは見えてこなかったものも見えることがあります。
また、情報セキュリティに無関心な社員が多い場合、訓練を自動化することはできても、訓練自体をスルーされてしまいやすいため、自動で算出される訓練実施結果は良好だが、実際には社員のセキュリティリテラシーは低いまま。ということも起こりかねません。
高い費用を出して訓練を自動化しても、結果にコミットされなれば、折角の投資も無駄になってしまいます。
🛡️まとめ:自動か、手動か?ではなく、“使い分け”が大事
訓練の自動化はとても便利な仕組みです。でも、「便利だから全部自動で回す」ではなく、訓練の目的や状況に合わせて自動と手動を上手に使い分けることが大切です。
たとえば、
- 年間を通じた定期訓練は自動化して、
- 特別な場面では手動で設計・実施する、
といったハイブリッド運用が、現実的で効果的な方法かもしれません。