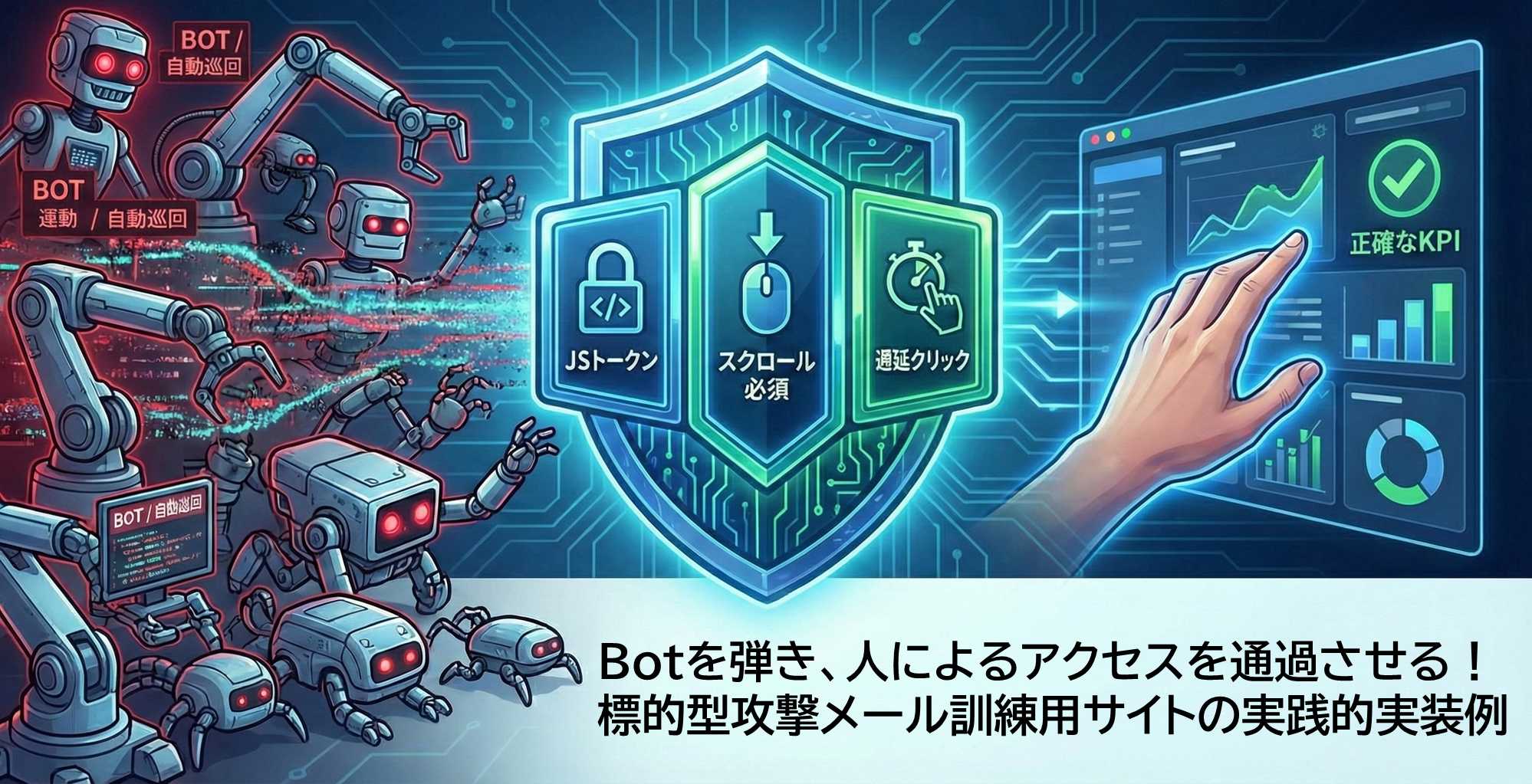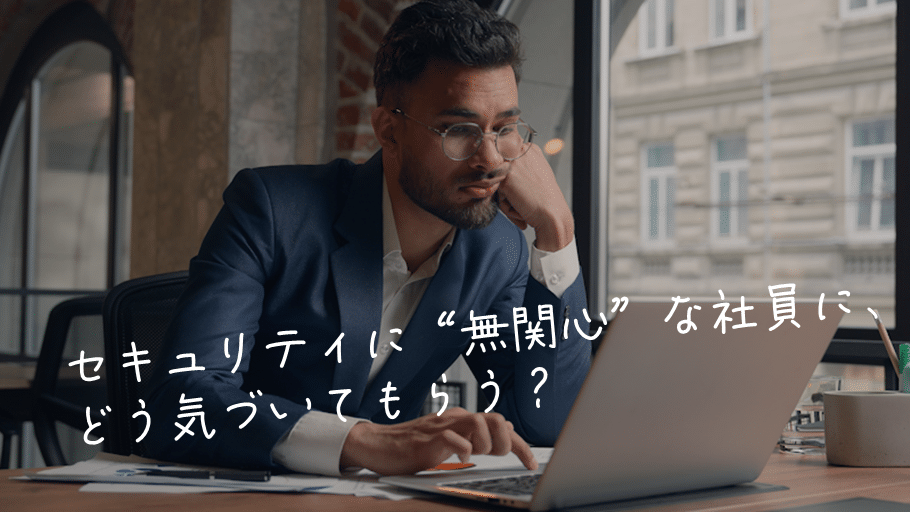
〜訓練実施担当者ができる、伝え方の工夫〜
標的型攻撃メール訓練を実施していると、「ちゃんと見てくれた人」と「全く無関心な人」がいることに気づくことがありますよね。特に、セキュリティ研修や注意喚起のメールを“流し見”してしまう社員へのアプローチに悩む方も多いのではないでしょうか。
「セキュリティなんて自分には関係ない」
「何かあったらIT部門が対応してくれる」
「何で社員に不審なメールを見分けさせるんだ!」
そんな“他人事”の意識を、“自分ごと”に変えてもらうには、ちょっとした工夫と視点の切り替えが必要です。今回は、情報システム担当者としてできる「伝え方の工夫」について、やさしく整理してみます。
❓なぜ聞き流されてしまうのか?
まずは、「なぜセキュリティの話が伝わりにくいのか」を整理してみましょう。
- セキュリティの話は抽象的で難しいと感じられがち
- 「自分が標的になることなんてない」と現実味がない
- 過去にトラブルを経験しておらず、危機感が持てない
- 研修がいつも同じ内容で、新鮮味がない
つまり、「頭では大切だとわかっていても、心には響いていない」状態だと言えます。
🎯ポイントは、“自分だったらどうする?”と考えてもらうこと
聞き流されないためのコツは、感情を動かすことと具体的な状況を想像してもらうことです。たとえば、次のような工夫が有効です。
● クイズ形式で考えてもらう
例:「このメール、あなたは開きますか?」
→ 社員が実際に判断する形にすると、主体的に考えるきっかけになります。
● 実話ベースの事例紹介
例:「同業他社で発生した情報漏えい事故」
→「うちにも起こり得る」とリアリティを持ってもらいやすくなります。
● ヒヤリ体験を通じて実感してもらう
→ 標的型攻撃メール訓練で「自分が引っかかった」経験は、何より強い気づきにつながります。
💡「脅す」のではなく、「共感」から始める
セキュリティ啓発というと、「開いたら危ない」「これをやると会社に損害が…」といった“脅し口調”になってしまいがちです。
でも、それではかえって「面倒くさい」「怖いから見たくない」という反応を招いてしまうこともあります。そこで大切なのが、共感ベースの伝え方です。
- 「ついクリックしてしまう気持ち、よくわかります」
- 「そのメール、私も一瞬あやうく開きそうになりました」
といった声かけは、社員の心を開く第一歩になります。
💡管理職や経営層の“巻き込み”も効果的
研修や訓練に対して、管理職が真剣に取り組んでいる姿勢を見せることで、現場の社員にも「これは大事なことなんだ」と伝わります。
- 管理職自身が訓練に参加する
- ミーティングでセキュリティの話題にふれる
- 成果報告に上層部がコメントする
こうした小さなアクションも、全体の意識向上には非常に効果的です。
逆に、管理職が自ら「あんな訓練、やったって無駄」などと発言していたら、それを耳にする部下の社員も「そうなんだ」と思ってしまいます。
トップが情報セキュリティに無関心であったら、会社全体の意識もそうなってしまいかねないことを考えれば、管理職や経営層こそ、第一に巻き込むべき対象と言えます。
🛡️最後に:小さな“気づき”が、会社を守る第一歩
すべての社員に一度で完璧に伝わることは、正直ありません。
でも、「ちょっと気をつけようかな」「これは他人事じゃないかも」と思ってもらうことが、セキュリティ文化づくりの第一歩です。
意識啓発は長期戦であり、社員の入退社による組織の新陳代謝が繰り返される限り、繰り返して実施すべきものです。
あきらめず、でも押しつけすぎず、社員の心に届く伝え方を探っていきましょう。
一人ひとりの気づきが、会社全体のリスクを確実に減らしてくれます。
たった一人でも気づきを得て変わってもらうことができたら、それだけでも大きな前進です。