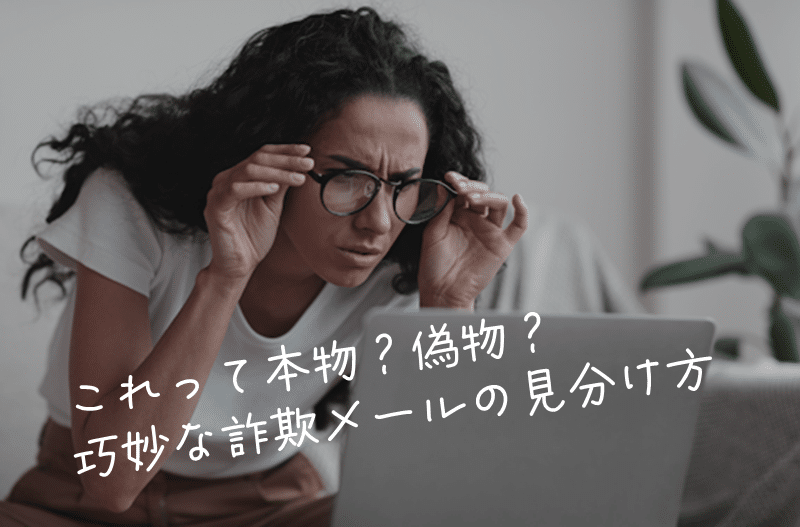
これって本物?それとも偽物?巧妙なフィッシングメールを見破る5つのポイント
最近のフィッシングメールは一昔前と違い、日本語が自然で読みやすいものが増えています。
「文面が丁寧だから本物っぽい」「日本語が変じゃないから大丈夫」
…そう思って油断していませんか?
実は、**本物そっくりに作り込まれた“なりすましメール”**が急増中。
企業名、ロゴ、署名まですべて本物のように見えるメールでも、リンクをクリックすると情報を盗まれてしまうケースがあります。
🎣日本語が自然なフィッシングメールが送られてくる理由
フィッシングメールの日本語が自然である理由の一つとして、本物のメールをそっくりそのまま流用しているということが挙げられます。
正規のサイトから発信されている本物のメールをコピーし、リンク先のURLだけを書き換えて送るという方法です。
内容自体は本物なので、メール本文を見ても当然、偽物だとはわかりません。犯罪者はメールを作り込む手間が省けるだけでなく、偽物であるとはバレにくいというメリットが得られるので、この手のフィッシングメールは増加する一方です。
では、この手の巧妙なメールに騙されないためにはどうすれば良いのでしょうか?
この記事では、日本語が自然でも見破るべきフィッシングメールの5つのチェックポイントをご紹介します。
✅ 1. 差出人のメールアドレスを細かく確認する
メールの「表示名」は本物そっくりでも、**メールアドレス(@以降)**が違うケースがあります。
メール本文はコピーできても、差出人アドレスまで真似てしまうと迷惑メール判定に引っかかってしまう場合、これを回避するためにメールアドレスを本物っぽいものにして送る手口が使われます。
このような場合は、差出人アドレスをよく見ることで、フィッシングメールであると見破ることができます。
例:
- 表示名:Amazon カスタマーサービス
- メールアドレス:
support@amazon-login-alerts.com(偽物)
📌 チェックポイント:
- 公式のドメインか?(例:
@amazon.co.jp,@rakuten.co.jpなど) - 本物と1文字違いの偽ドメインになっていないか?
✅ 2. メール内のリンク先URLを確認する
本文のリンクを**クリックする前に、マウスをかざす(PCの場合)**と、実際のURLが表示されます。
フィッシングメールは偽のサイトに誘導することが目的なので、リンク先には偽のサイトのURLを設定せざるを得ません。なので、リンク先が本物か偽物かを見分けることができれば、騙されてしまうことは回避できることになります。
例:
- 表示テキスト:
https://www.amazon.co.jp - 実際のリンク:
http://amaz0n.secure-check.jp
📌 チェックポイント:
- URLのドメイン名が本物と一致しているか?
https://で始まっているか(セキュアな通信)amazon.co.jpのような正規ドメインの直後にスラッシュ(/)があるか?
✅ 3. 緊急性や不安を煽る文面に注意
日本語が丁寧でも、「アカウント停止」「緊急対応が必要です」「24時間以内に対応を」といった焦らせる表現には要注意です。
なぜなら:
急がせることで冷静な判断をさせないのがフィッシングの常套手段だからです。
正規のサービスであれば緊急性や不安をやたらと煽るようなことはしませんし、もし、そのようなことがあるとしても、正規の手段で対応することを伝えるのが一般的です。
📌 チェックポイント:
- 「今すぐ」「期限付き」「アカウントがロックされました」「永久ロック」「緊急」などの文言
- メールの雰囲気が**“怖がらせる”ような内容**になっていないか
✅ 4. 添付ファイルの拡張子に注意
メールに添付されているファイルが、ウイルス感染の入り口になっていることもあります。
ウイルスに感染させるにはプログラムを実行させることが必要です。プログラムが実行できるファイルの種類は決まっていますので、ウイルスに感染しないためには、プログラムが実行できる種類のファイルを開かないこと。
逆に言えば、プログラムが実行できないファイルの拡張子(.txt、.docx、.xlsxなど)を覚えておき、それ以外は危険性があるファイルだと考えて、注意すればよいということになります。
特に注意すべき拡張子:
.exe(実行ファイル).zip(圧縮ファイル).xlsm(マクロ付きExcel)
📌 チェックポイント:
- 見覚えのない差出人からの添付ファイルは開かない
- 社内ルールで添付ファイルの扱いを明確に
✅ 5. “ちょっとした違和感”を見逃さない
完璧に見えるフィッシングメールでも、よく読むとほんのわずかな違和感があることが多いです。
たとえば…
- メール署名にいつもある電話番号がない
- ロゴ画像の解像度が荒い
- 自分の名前ではなく「お客様各位」となっている
といったように、自分が担当者だったら、このようなメールを送るだろうか?と考えると、違和感に気づきやすくなります。
あなたがフィッシングメールで使われている技術に詳しいなら、犯罪者の視点に立って、これがフィッシングメールだとしたら、どのようにしてこのメールを送ってきたのだろうか?と考えると、使われている手口に気づきやすいかもしれません。
📌 チェックポイント:
- 過去に届いた本物のメールと比較してみる
- 怪しいと感じたらメールを開いたままにせず、公式サイトで確認する
🔐 まとめ:文面が自然でも“本物とは限らない”
文面が自然というか、本物をそのまま真似ている場合はメール本文を見ただけではフィッシングメールであるとは気づけませんが、フィッシングメールである以上、リンク先が偽物であるなど、どこかしらに詐欺の痕跡を見つけることができるものです。
ぱっと見、本物であるように見えても、これはもしかしたらフィッシングメールかもしれないという疑いを常に持ち、以下のようなポイントに注意することが、騙されないための第一歩になります。
| チェック項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 差出人アドレス | 正規ドメインか、一文字違いがないか |
| リンク先URL | 表示と実際が一致しているか |
| 文面のトーン | 急かす・怖がらせる内容ではないか |
| 添付ファイル | 拡張子に注意(exe, zip, xlsmなど) |
| 違和感の有無 | ロゴ・署名・名前などの細かい違い |
📩 万が一、不安なときは?
- 公式の問い合わせ窓口にメールの真偽を確認
- リンクはクリックせず、公式サイトからログイン
- 社内なら情報システム部門や上司にすぐ相談
以上を徹底することで、たとえ巧妙なフィッシングメールであっても、うっかり騙されてしまうことを防ぐことができますよ!





