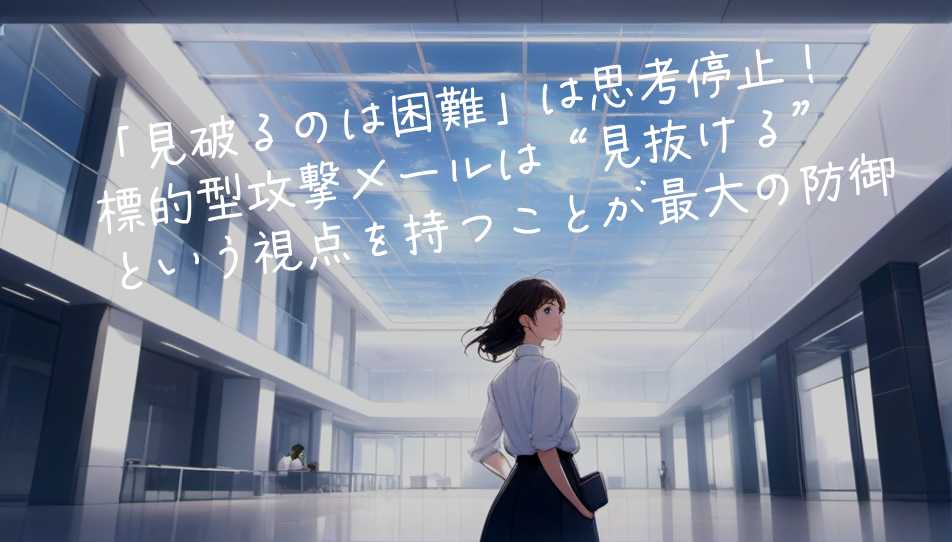🧠 人は「体験したこと」をよく覚えている
皆さんは、子どものころに訪れた場所の道順や、初めて海外旅行に行ったときの情景を、今でも鮮明に覚えていませんか?
不思議なことに、わざわざ暗記しようとしたわけではないのに、体験した出来事は長く記憶に残るものです。
これは単なる偶然ではなく、医学的にも説明がつく人間の習性です。
🩺 医学的な仕組み:体験が記憶に残る理由
医学者ではないので、専門的な話はその分野の専門家をあたっていただきたいですが、体験が記憶に残る理由として、以下のようなことが言われています。
- 海馬が体験情報を強く刻む
新しい情報は脳の「海馬」に保存されます。特に、実体験を伴う情報は視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を通して入力されるため、より強く残ります。
- エピソード記憶として残る
「どこで」「何を」「どう感じたか」といった“出来事の記憶(エピソード記憶)”は、単なる知識よりも長期保存されやすい特性があります。
- 感情が記憶を強化する
驚きや緊張といった感情が伴うと、扁桃体が活性化し、記憶がより鮮明になります。
👉 つまり、「実際に体験し、感情が動く」ことで、学んだ内容は忘れにくくなるということです。
📧 不審メール対策に体験が必要な理由
「フィッシング詐欺メールに注意しましょう」と口で伝えるだけでは、どうしても記憶に残りにくいものです。
テレビのニュース番組などでもフィッシング詐欺については繰り返し注意喚起が出されていますが、テレビで紹介された内容を見ても、数日もすれば、「テレビで紹介していた詐欺メールの内容ってどんな内容だったっけ?」と思ったことがある方も少なくないはずです。
しかし、実際に詐欺メールを受け取り、
- 「本物そっくりで気づきにくい!」
- 「リンクをクリックしたらどうなるんだろう?」
と体験を通じて“気づき”を得ると、次回から自然と注意できるようになるものです。
実際、ご自身が体験した詐欺メールについては、今でも思い出すことができるのではないでしょうか?
📌 ただ知っている → 「知識止まり」
📌 一度体験した → 「実際の行動につながる」
このように、実際に体験することの方が本人の記憶に残りやすいことは、ご自身の体験から考えてもはっきりと実感いただけるのではないかと思います。
🛡️ 標的型攻撃メール訓練の効用
「標的型攻撃メール訓練」は、まさに体験による学習効果を活かした教育手法です。
- 社員に安全に“疑似攻撃”を体験させることができる
- 一度体験した記憶が残り、実際の攻撃時に違和感に気づきやすくなる
- 訓練結果をフィードバックすることで、個人と組織の学びを可視化できる
つまり訓練は、「知識を与える」から「習慣を身につける」へと変換する仕組みと言えます。
✅ 実際に体験してもらうことが何よりも大事
- 人は「体験したこと」を長く記憶に残す。
- 医学的にも、体験+感情によって記憶が強化される。
- フィッシング詐欺対策には、講義や知識提供だけでなく「実際の体験」が不可欠。
- 標的型攻撃メール訓練は、その体験を安全に提供するための最適な手段。
💡 社員に“忘れにくい体験”を積ませることが、結果的に会社を守る力に直結すると考えてください。
標的型攻撃メール訓練というと、社員が模擬の詐欺メールに騙されてしまうかどうかを確かめるやり方をしているケースが多いですが、社員全員に実際に模擬の詐欺メールをあえて開いてもらう「体験型」の訓練を実施することも有効です。
多くの人は「不審なメールは開いてはいけない」と普段から刷り込まれているため、模擬とはいえ、実際に不審と思われるメールを開くことには抵抗を感じるはずです。
それをあえて開くのですから、この抵抗感が緊張を生み、記憶を強化させるということに繋がって、体験として記憶に残るというわけです。
このように、標的型攻撃メール訓練は医学的にも理にかなった方法と言えるのではないでしょうか。