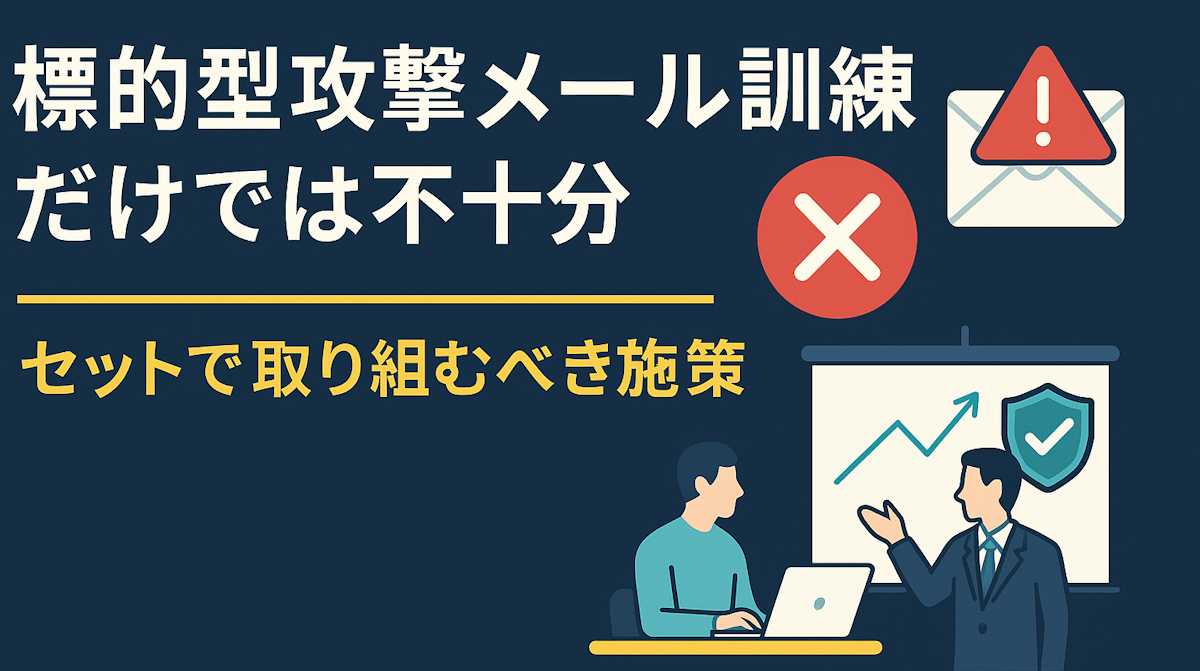🔹「社員を最後の砦に」とはよく言われますが…
サイバー攻撃が日々巧妙化する中、標的型攻撃メールやフィッシング詐欺メールから会社を守るために、社員を「最後の砦」と位置付けて教育する企業は増えています。
しかし、この「最後の砦」という言葉を
「不審なメールに絶対に騙されてはならない」
という意味で運用してしまうと、思わぬ副作用が生まれます。
⚠ 「最後の砦」の誤った解釈がもたらす弊害
- 報告の遅れ・隠蔽
「もし自分が騙されたら罰せられるかも…」という恐怖から、
被害報告をためらい、初動対応が遅れる。
- 過度な緊張による業務効率の低下
メールを開くたびに過剰な警戒心が働き、
本来の業務が滞る。
- 心理的安全性の低下
ミスが許されない雰囲気が広がり、
社員同士での情報共有や相談がしづらくなる。
最後の砦となる社員が不審なメールに騙されてしまうことで被害の発生に繋がってしまっては、「最後の砦」としての意味が無いとして、最後の砦なのだから不審なメールに騙されてはいけないなどという考えが社内に蔓延してしまうと、却って別な問題が発生してしまうことになりかねません。
✅ 本来の「最後の砦」の意味とは?
本当に目指すべきは…
「不審なメールに絶対に騙されないこと」ではなく、
『自分が会社を守る盾となる』という意識を持つこと」
つまり、社員がセキュリティを「自分事」として捉え、日常の業務で自然と安全な行動を取れるようになることが重要です。
この意識が社内文化として定着すれば、結果として社員は「最後の砦」として機能します。
社員に対して直接的に「最後の砦となれ!」と言うのでは無く、自然発生的に、結果的にそうなるようにするというのが、「社員を最後の砦にする」という言葉の本当の意味です。
💡 セキュリティ文化を根付かせるためのポイント
- ミスを責めず、共有を促す風土づくり
→ 不審メールやインシデントを報告した社員を評価する仕組みを導入。
- 訓練を“試験”ではなく“日常の練習”として実施
→ 点数付けや序列化ではなく、学びを共有する形にする。
- 経営層も参加する全社的取組み
→ 「セキュリティは全員の責任」という姿勢をトップ自らが示す。
📌 まとめ
- 「最後の砦」を**「絶対に騙されない存在」**と誤解すると、
報告遅延や業務低下などの逆効果を招く。 - 目指すべきは、社員一人ひとりが自分事として会社を守る文化。
- その文化があってこそ、社員は自然に「最後の砦」として機能する。
社員が不審なメールに絶対に騙されないよう教育することで、社員を「最後の砦」とする、
自分が会社を守るという意識を一人一人に持たせることで、社員が「最後の砦」となる、
どちらも社員を「最後の砦」に変えるという意味では同じですが、そのアプローチは全く異なりますし、得られる結果も全く異なります。
どちらが考え方として適切かは言うまでも無いでしょう。
💬 言葉の使い方ひとつで、社内の雰囲気も文化も変わります。
「最後の砦」という言葉は、社員の心を追い詰める言葉ではなく、誇りと自信を持たせる言葉として活かすべきです。