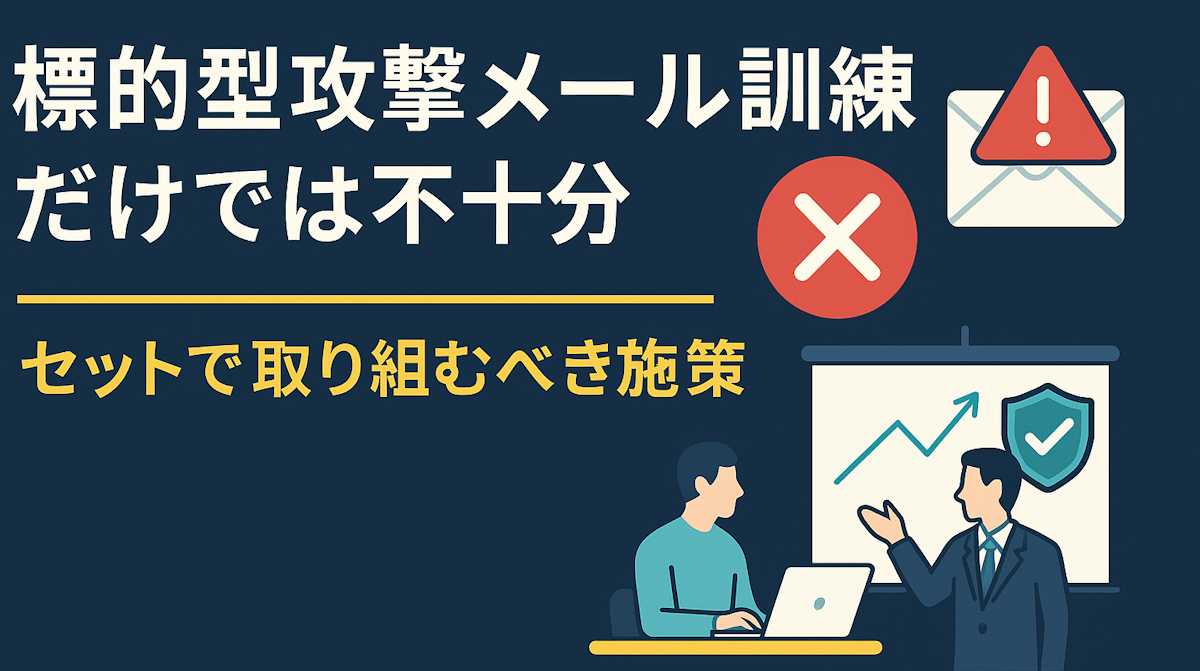📌 フィッシング詐欺が“日常”になった現代
今や、フィッシング詐欺メールは毎日大量に送られています。
X(https://x.com/cX8oKyVKoqucXfR)で報告しているフィッシング詐欺メールのタイトルだけでも毎日50~100種類以上にもなり、送付数はその何倍にも及びますから、詐欺メールは1日中、のべつ幕なしに送られてくる状況です。
そんな状況ですから、受信者は知らない相手からのメールはもちろん、取引先や利用サービスからのメールであっても、まず疑うことが当たり前になっています。
その結果、たとえ正規の企業からの案内であっても、
- 見た目が怪しい
- 文面が不自然
- 添付やURLが唐突
このような特徴があれば、即削除や未読スルーされることも珍しくありません。
以前から、詐欺メールっぽく見えてしまう正規のメールを目にする度に、
「これじゃ詐欺メールと間違われるじゃん!」
とモヤモヤすることがあるのですが、同じようなことを思っている人は私ばかりではないようです。
👉フィッシング詐欺のようなSMSを送ってくる本家ネットバンクのセキュリティと立ち位置(オルタナティブ・ブログ記事)
⚠ 正規メールが「怪しい」だけで失うもの
企業が送った本物のメールが「怪しい」と思われるだけで、以下のような損失を招きます。
- 顧客からの信頼喪失
「この会社からのメール、本当に大丈夫?」という不安は、購買や契約更新の意欲を下げます。
- 優秀な人材の離脱
セキュリティ意識が低い組織は、情報リテラシーの高い人材から見限られる可能性があります。
殿様商売ができる企業であれば、どんな内容のメールを送ったところで、それだけですぐに商売が傾いてしまうような事態にはならないでしょうが、だからといって、それを長く続けていれば優秀な人材からは避けられ、新興企業に徐々に顧客を奪われ、会社はやがて衰退していく。ということになりかねません。
🛡 社員教育の盲点
多くのセキュリティ教育は
「不審なメールを見抜く」
ことに力を入れています。
しかし、それだけでは不十分です。
「自分が不審なメールを送らない」
という意識を持たせることも、同じくらい重要です。
自分が不審なメールを送らないよう注意することは、どのようなことが不審に思われてしまうのかを普段から意識することであり、それは翻って、受信したメールが不審なメールかどうかに気づきやすくなるということにも繋がります。
🔍 「不審なメール」と誤解される典型例
- 件名や差出人が曖昧(例:「重要なお知らせ」「担当者より」など)
- 事前説明なしの添付ファイル送付
- 不自然な日本語や過剰な改行
- 長く複雑なトラッキング付きURL
- 本文中でパスワードや個人情報の入力を依頼
- メール本文に記載しているURLと実際のリンク先URLが異なる
こうした特徴は、正規メールでも受信者の警戒心を高めてしまいます。
例えば、クラウド型のマーケティングシステムを利用しているようなケースでは、メール本文に記載しているURLのリンク先が、マーケティングシステムが提供するトラッキング用のURLとなっていて、メール本文上で目に見えるURLには自社のドメイン名が使われているが、実際のリンク先にはマーケティングシステムのドメイン名が使われているといったことがあります。
マーケティングシステムのドメイン名が正規のドメイン名かどうかわかるような人は、そのシステムを使っている人くらいなので、多くの人は「リンク先が記載と異なる」→「不審なメール」と捉えてしまいます。
フィッシング詐欺メールが横行する中で、メールに記載のリンク先と実際のリンク先を違うものに設定してしまうマーケティングシステム、また、そうしたことに気づかないままシステムを利用してしまうマーケティング担当者も今どきどうかと思いますが、今のように、フィッシング詐欺メールが大量に送付されている状況にあっては、利用する側もこうしたことを意識するべきです。
📋 担当者ができる取り組み例
- 送信前チェックリストの導入
件名・本文・署名・URLを第三者目線で見直す。
- 社内ガイドライン整備
送信フォーマット、署名ルール、追跡リンク使用の可否を明文化。
- 「疑われない文章術」研修
顧客が安心して読める文面作成のポイントを教育。
「詐欺メールに注意」というトーンだけでは他人事に感じてしまい、自分事として捉えてもらいにくいですが、「自分自身が詐欺メールっぽいメールを送っていないか?」というトーンで語りかけることは、自分事として考えてもらいやすいきっかけにはなるのではと思います。
✅ まとめ
フィッシング詐欺の氾濫によって、受信者の目は常に疑いのフィルターを通しています。
この状況で怪しく見えるメールを送ることは、自ら信頼を削る行為です。
セキュリティ教育の担当者は、
- 怪しいメールを見抜く力
- 怪しいと思われないメールを書く力
この両方を社員に身につけさせる取り組みを、今すぐ始めるべきです。