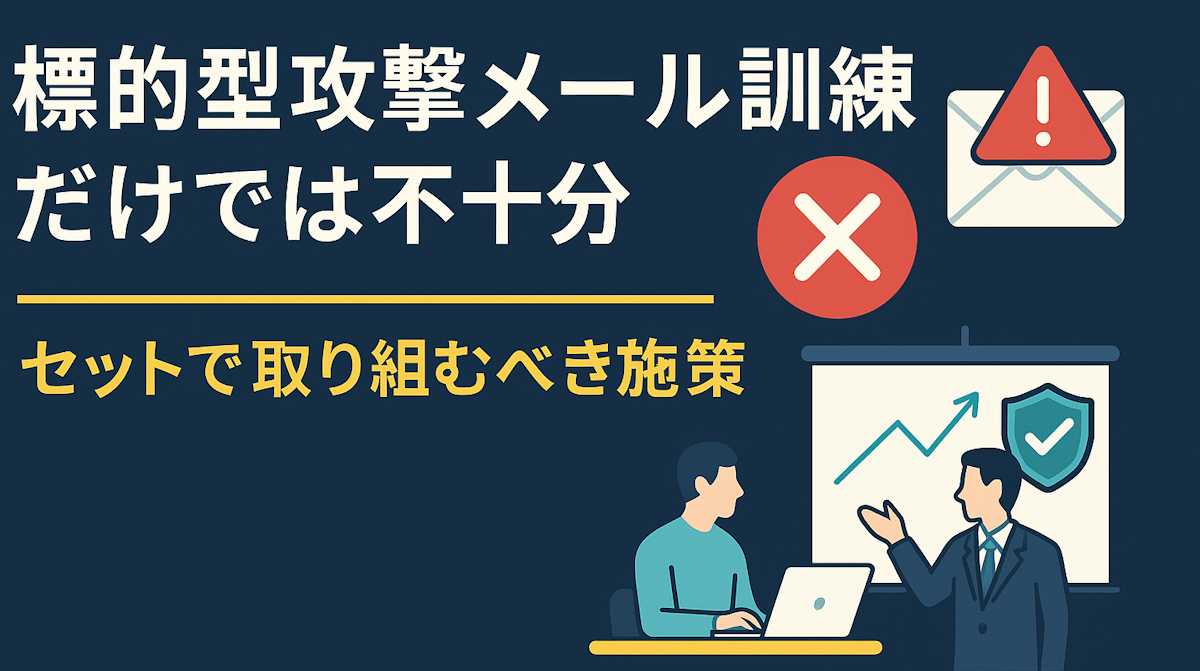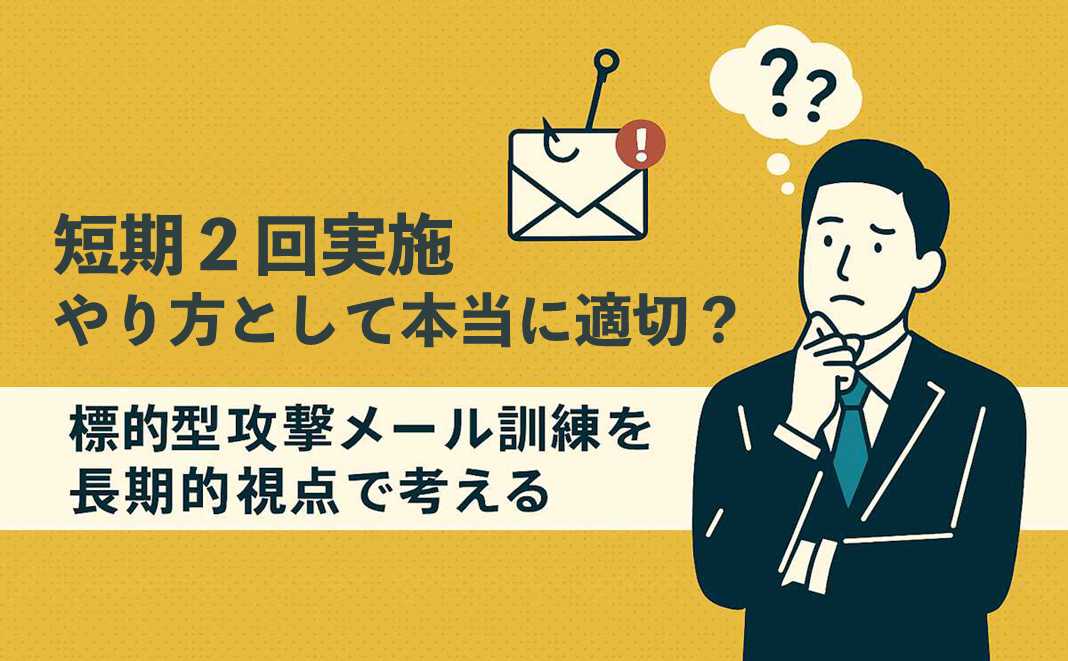
業者に標的型攻撃メール訓練実施を委託すると、
1回目の訓練 → 2週間〜2ヶ月後くらいに2回目を実施して効果検証というサイクルがよく採用されています。
確かに、短期間でクリック率の低下を確認できれば、「訓練の効果があった」と安心感を得られます。
しかし、それは本当に長期的な安全性を保証する方法なのでしょうか?
今回は、コスト面・効果面・攻撃トレンドの変化速度という3つの観点から、
訓練の実施方法としてよくある、1度の訓練で2回、訓練メールを送信するというやり方の是非を考えてみます。
1. コスト面から見た課題
💡 短期間に2回行うことの負担
- 訓練メールの作成
- 配信準備
- 結果集計・報告書作成
これらを短期間で繰り返すことで、担当者の工数や外部委託費がかさみます。
💡 費用対効果の疑問
- 一時的な数値改善が見えても、数ヶ月後には元の水準に戻ってしまうことも。
- 効果の持続性がないまま、コストだけが増える恐れがあります。
💡 長期運用の観点
- 年間計画に沿って分散実施したほうが、総コストを安定化できる可能性が高いです。
2回訓練を行うということは、それだけ委託費が増えることになります。
限られた予算を短期に2回の訓練実施にかけるか、時期を分けて1回ずつで実施するかは、長期的な視点に立って、その是非を考える必要があります。
2. 実際の効果から見た課題
📉 短期間でのクリック率低下は“本物”か?
- 1回目直後は警戒心が高くなっているため、2回目は自然とクリック率が下がります。
- これは**「記憶が鮮明だから」**であって、知識や習慣の定着とは別問題です。
🕒 時間が経つと効果は減衰する
- 注意力は数ヶ月単位で薄れていきます。
- 短期2回の結果だけで、長期的な安全性を判断するのは危険です。
1回目の訓練を実施してから2週間~2ヶ月程度では、クリック率が下がるのはむしろ当たり前の結果とも言えます。
もし、クリック率が下がって当たり前のところが、実際には下がらなかったら、それはそれで問題ですが、クリック率が下がって当然の結果を得るためだけに費用をかけるのだとしたら、それはコストのかけ方として妥当なのかどうか、考え直した方が良いかもしれません。
3. 攻撃トレンド変化の速さ
⚡ 攻撃の進化は想像以上に早い
- 生成AIの普及により、攻撃メールの品質・多様性は数ヶ月単位で進化。
- 以前は見抜けたパターンも、半年後には通用しないこともあります。
📌 短期2回では網羅できない
- 短期間に連続実施すると、同じ手口ばかりを試すことになり、
新たな手口への耐性が育たないという問題があります。
攻撃の手口は無数にある中で、1回目の訓練の効果があったかどうかを確かめるために、2回目も1回目と同じ訓練を実施するのだとしたら、訓練という機会を有効に活用するという観点から言って、非常に勿体ないと言えます。
4. 長期的視点での訓練計画例
📅 年間計画の一例
- 年3〜4回実施:季節・業務イベント(決算期、賞与支給時期など)に合わせてテーマを変える
- 最新トレンド対応:フィッシング詐欺型、業務ツール偽装型、生成AI活用型などを順次導入
- 小規模訓練+全社訓練の併用:定期的な少人数テストと年1回の大規模訓練を組み合わせる
💬 ポイント
- 訓練は「一発勝負」ではなく継続して実施する習慣をつくることが重要です。
- クリック率の上下だけでなく、「社員の行動や判断基準が変化しているか」を観察することが大切です。
訓練の本質は、不審なメールに気づく視点を養い、不審なメールに常に注意する習慣を身につけることです。その観点から言えば、年間を通じて訓練を行い、油断や気の緩みが起きないようにするのが理想と言えます。
5. まとめ
短期2回実施は、あくまで効果測定のスナップショットです。
本当に必要なのは、長期的に攻撃に耐えられる組織体質の構築です。
- 年間計画で継続的に実施する
- 攻撃トレンドの変化に合わせて内容を更新する
- 社員の行動変化を測定する指標を導入する
これらを組み合わせてこそ、標的型攻撃メール訓練は真価を発揮します。
1度訓練を実施したら、しばらくは実施しないだろうとタカをくくっている社員の裏をかいて、あまり日を置かずに2回目の訓練を実施するといったやり方もあるので、短期で2回訓練を実施すること自体は否定しませんが、これまで特に理由もなく「訓練は1度に2回実施するのが当たり前」と思っていたとしたら、これを機会に、短期に2回訓練を実施することが本当に必要かどうか、考えてみることをお奨めします。
長期的な視点に立って考えれば、訓練実施の効果が出ているかどうかを確かめる方法は、短期で2回訓練を実施する方法だけでは無いはずです。