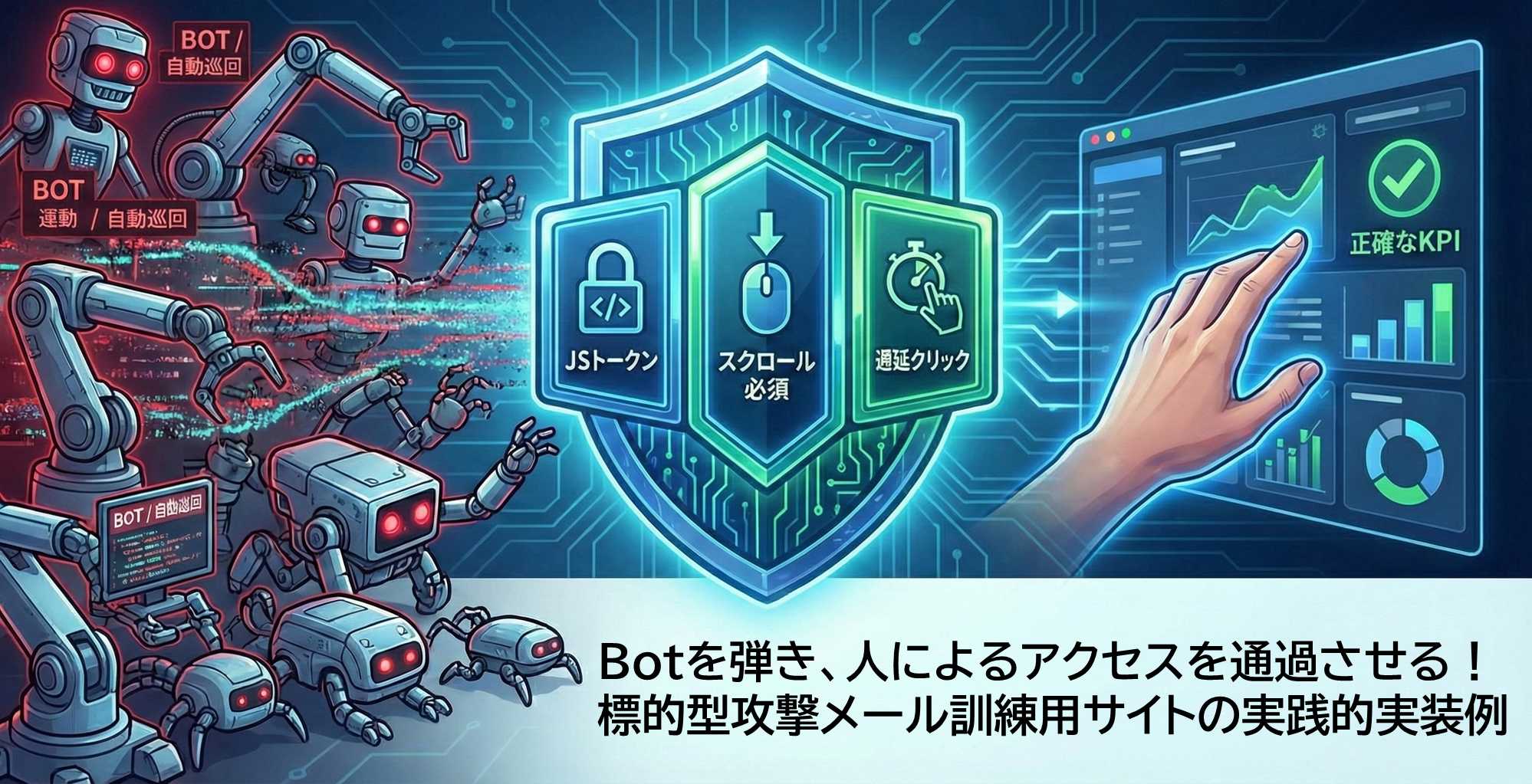標的型攻撃メール訓練における人事面での適切な対処とは
標的型攻撃メール訓練を定期的に実施している企業の中には、
「何度訓練を行っても、同じ社員が毎回リンクをクリックしてしまう」
という悩みを抱えているケースも少なくありません。
毎回とまではいかなくても、「なんでこの人はまたクリックしてるの?」と思ったことがある方は結構いらっしゃるのではと思います。
このような社員に対して、
- 懲戒処分にするべきなのか?
- 昇進・評価に影響を与えるべきなのか?
- そもそも指導で改善するのか?
といった対応の是非について、悩む担当者も多いことでしょう。
とはいえ、こうした事象に対して、
- 「この社員は危機意識が低いのでは?」
- 「やる気がないのでは?」
- 「処分すべきでは?」
といった短絡的な判断をしてしまうことは、企業として本質的なリスク管理の観点を欠いているかもしれないということを考える必要があります。
👀背景には“努力ではどうにもならない要因”が潜んでいることも
クリックを繰り返してしまう原因としては、本人の注意不足やスキル不足だけでなく、
認知特性や健康状態、精神的な負荷、発達障害・学習障害など、本人の努力では対処しづらい背景が存在する場合もあります。
📌【例1】注意制御に困難があるケース
発達障害(例:ADHD)などの影響で、注意を一定時間持続することが難しく、瞬間的な判断においてミスをしてしまうことがある。
📌【例2】文字情報の処理に特性があるケース
学習障害(例:ディスレクシア)などにより、メールの文面の意味が正確に読み取れず、結果として誤った判断をしてしまうことがある。
📌【例3】精神的な過緊張・プレッシャーによる判断力低下
「絶対に間違えてはいけない」という強いプレッシャーから、逆にパニックになってしまい、正しい判断ができない。
📌【例4】業務環境のストレスや多忙による注意力の欠如
メールを“流し読み”せざるを得ないほどの業務負荷があり、注意力を奪われやすい状況にある。
つまり、本人の能力や努力だけでは解決できないことが根本的な原因である場合もあるということです。このような場合、本人を幾ら指導しても問題の解決には至らないばかりか、お互いに疲弊してしまう結果になりかねません。
✅会社として取るべき4つの対応方針
これらの背景を踏まえると、企業がとるべき対応は**「罰すること」ではなく、「支援の仕組みを整えること」**です。
① 🧑🏫個別支援型の再教育と丁寧な振り返り
- 一律の集合研修ではなく、その社員の特性に合わせた個別の指導機会を設ける。
- ミスの背景や認知プロセスを、専門家や上司と共に整理する。
② 🧠適性への理解と社内相談体制の整備
- ミスが頻発する社員に対して、障害や認知特性を前提とした対応が必要かもしれないという視点を持つ。
- 必要に応じて産業医や社外専門家への相談機会を提供する。
③ ⚖人事評価への反映は慎重に行う
- 単に「クリックしたか否か」だけで評価を下すことは避ける。
- 背景事情を十分に確認した上で、公正なプロセスに基づく判断を行う。
④ 🧾業務内容や配置の見直しも視野に入れる
- 本人の適性に著しい乖離がある場合は、より適した職務への配置転換や業務見直しも含めて検討。
- セキュリティリスクを最小化しつつ、本人の強みを活かせる業務に導くことが理想。
🚫「本人の努力が足りない」という誤った決めつけに要注意
多くの人は「自分と同じようにできない人」に対して、
「もっと頑張ればできるはず」と思いがちです。
しかし、同じ情報が与えられても、人によって処理の仕方はまったく異なります。
企業が本当にセキュアで多様性を受け入れる職場を目指すなら、
**「頑張ることを前提にしない設計」**が必要です。
🔐セキュリティ対策=多様性への理解
社員が不審なメールに引っかかることは、会社にとって重大なリスクです。
しかし、それを個人の資質だけの問題として処理してしまうことは、さらなる組織リスクを生みかねません。
🚨 セキュリティ意識の低さではなく、
🧩「見えづらい特性」に企業が気づけるかどうかが問われています。
社員一人ひとりの背景に向き合いながら、
教育・支援・配置・評価のすべてを“個別最適化”していく姿勢こそが、
本質的なセキュリティ強化につながっていくと考えます。