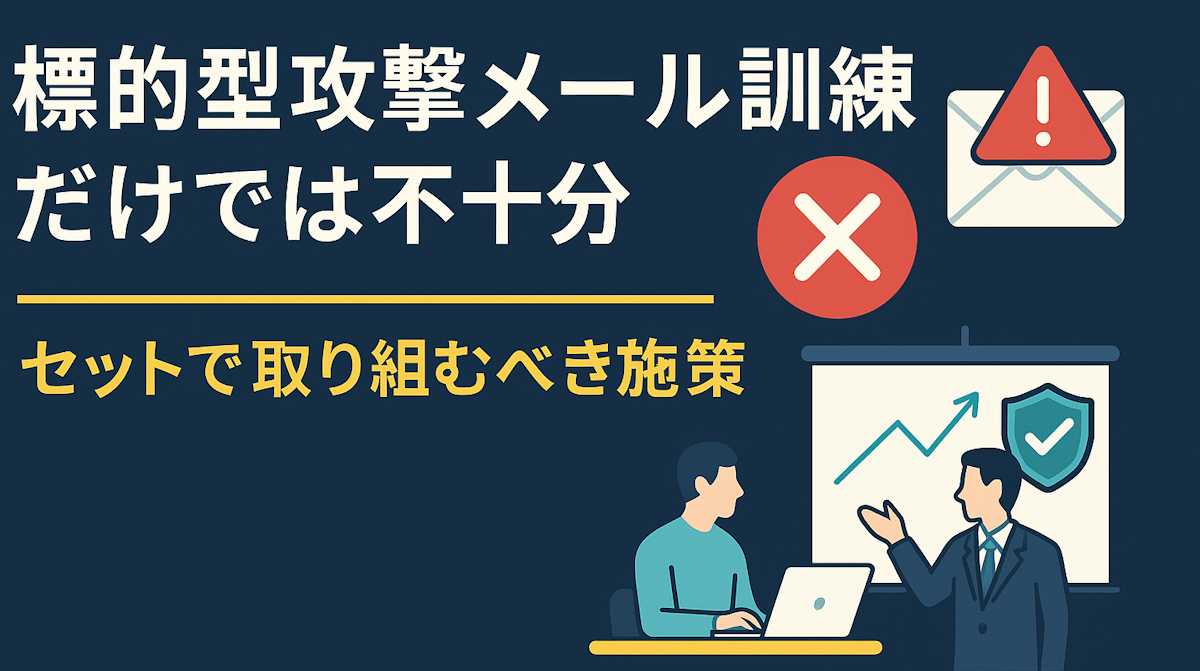◆ 攻撃を100%防ぐのは不可能、でも…
サイバーセキュリティの分野では、
「脅威の侵入を100%防ぐのはもはや不可能」という認識が広まっています。
そのため、近年では「攻撃を受けても、迅速に復旧してビジネスを継続できる体制」が重視されるようになってきました。
しかし——
**「復旧できる体制がある=すぐに元通りになる」**と考えてしまってはいないでしょうか?
サイバーレジリエンスを高め、万一のインシデントにも迅速に回復できるソリューションの宣伝文句を見ると、すぐにでも元通りに復旧できるかのような印象を受けてしまいますが、数十分で復旧できるという話と、数日で復旧できるという話では、同じ復旧できるという話でも影響は全く異なります。
「復旧できるようになっているなら大丈夫」と考えてしまいがちですが、具体的に「何が」「どれくらいの時間で」「どのような形で」復旧できるのかによっては、大丈夫だと思っていたものが、実は全く大丈夫ではなかったということになるかもしれません。
◆ 復旧までの時間は想像以上に長い
たとえばランサムウェア攻撃を受けた企業の多くが、
バックアップを用いて復旧を図っていますが、次のような現実があります。
🔻 実際の復旧事例(某製造業のケース)
- 社内ファイルサーバが全て暗号化
- バックアップからの復旧作業に9日間を要した
- 復旧中は製造ラインの一部が完全停止
- 顧客への納品が遅れ、数千万円単位の違約金が発生
いくら「復旧できる」と言っても、
その“復旧までの時間”に業務が止まってしまうことのリスクは計り知れません。
御社では万一の際、復旧までに要する時間として具体的にどれくらいの時間がかかるか、実際にテストを行って計測したことはあるでしょうか?
また、復旧までの間に発生する様々な問題について想定し切れているでしょうか?
復旧できることの価値は、業務が止まってしまうことで生じる「損失」「信用の失墜」「風評被害」「社員のモチベーション低下」などを、会社が持ちこたえられる程度に最小化できるかどうかにあります。
幾ら復旧ができても、会社が復活できないほどにダメージを負ってしまってはどうしようもありません。
◆ 復旧できる前提で油断すると痛い目を見る
「どうせバックアップがあるから」「EDRで隔離できるから」
——そんな気の緩みが、セキュリティ対策の手を緩めてしまうことがあります。
しかし、脅威の侵入を許してしまえば、復旧のための作業・調査・再設定にかかる時間・労力・コストは非常に大きいのです。
✅ たとえ復旧できても…
- 顧客や取引先からの信頼は一度失えば取り戻すのは困難
- 情報漏洩時は報告義務が生じ、企業イメージに致命傷
- 記者会見・第三者委員会・弁護士対応…本業に集中できない日々
また、復旧作業を行っている間も別の攻撃を受けないという保証はありません。
復旧作業に追われて通常の業務ですら手が付かない状況なのに、別の攻撃を受けて更に混迷を極めてしまうということだってあり得るのです。
◆ 復旧体制と“侵入防止策”は両輪
「復旧できる体制」は非常に重要ですが、
“そもそも攻撃を受けない”努力を怠ってはいけません。
👇 具体的には…
- ゼロトラストの導入
- 標的型攻撃メール訓練の定期的な実施
- エンドポイントの堅牢化
- 社員のセキュリティリテラシー向上
これらを地道に継続していくことで、
**「攻撃を受けにくくする」**環境を整えることができます。
脅威の侵入を許してしまえば復旧はしなくてはならないので、迅速・確実に復旧ができる体制を整えておくことはもちろん必要ですが、それはあくまで安心して本業に取り組めるようにするための「保険」であり、「伝家の宝刀」と考えるべきです。
◆ あなたの組織は“防御と復旧”の両方に取り組んでいますか?
「復旧できるから防御はそこそこでいい」
そんな考えは、致命的なリスクを見落としています。
攻撃の侵入は、確かに防ぎきれないかもしれません。
それでも、一件でも侵入を防げれば、復旧にかかるコストも、信頼失墜のリスクも、確実に減らせるのです。
🔐 今一度、見直しを!
✅ 復旧体制の整備はできていますか?
✅ 復旧までにかかる時間の確認はできていますか?
✅ 予防のための教育や訓練は実施していますか?
✅ セキュリティ対策に「油断」は生まれていませんか?
「復旧できるから安心」ではなく、
「復旧できるがその必要がないよう、まずは防ぐ」という視点を、会社全体で共有しましょう!