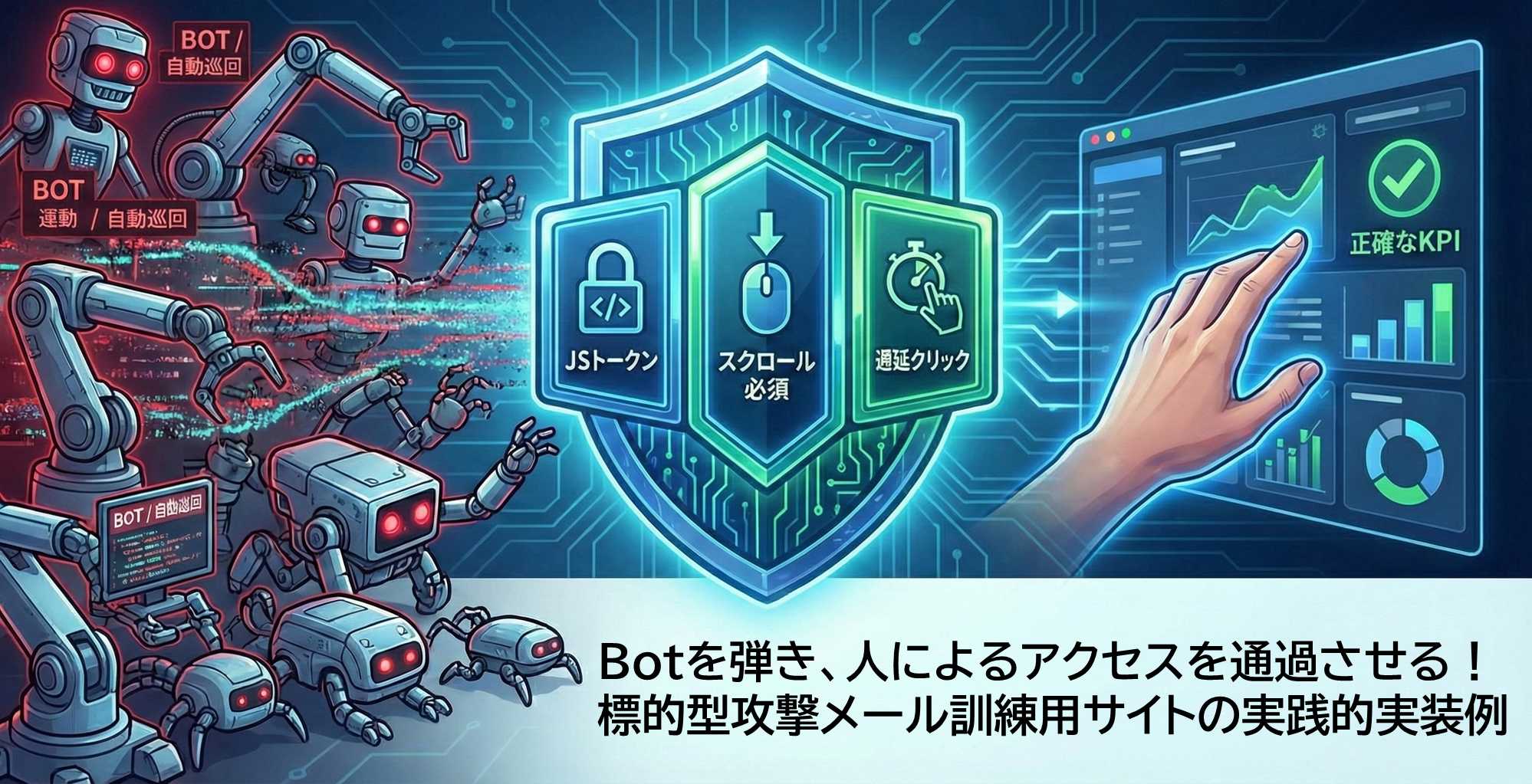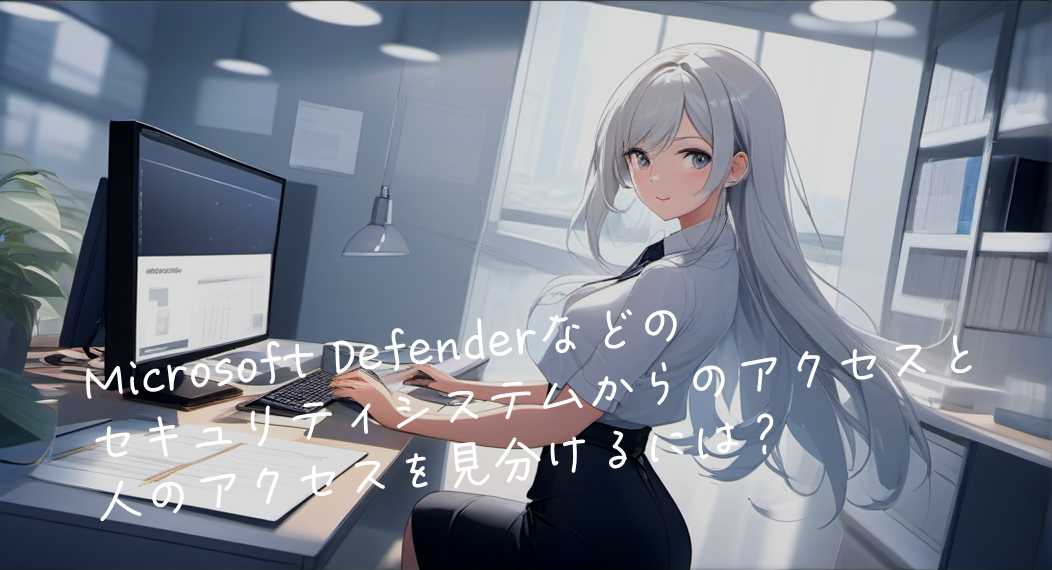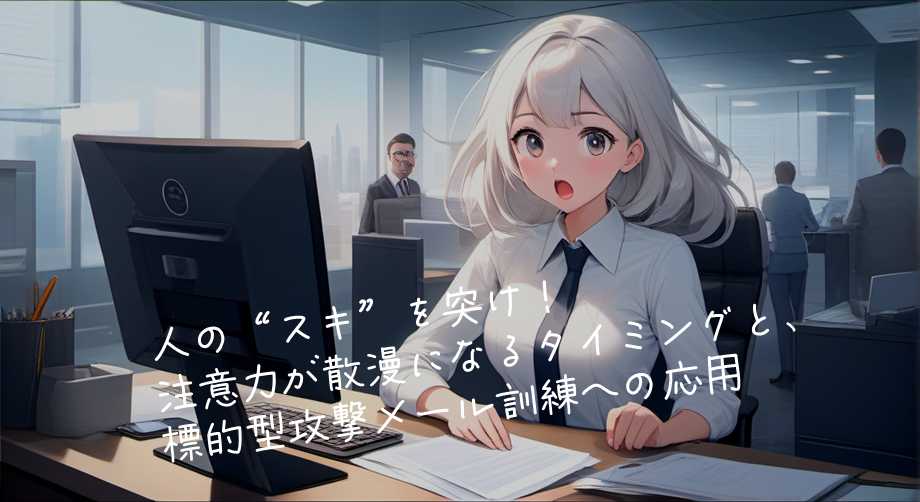
訓練メールはいつ送信するのがベストなのか?
訓練実施担当者であれば、この問題について考えたことは一度や二度ではないでしょう。
サイバー攻撃は、技術だけではなく「人間の心理的な隙」を突いてきます。
特に標的型攻撃メールでは、「どんな内容で」「誰に向けて」「どのタイミングで」送るかが極めて重要です。
では、人はどんなときに注意力を失いやすいのでしょうか?
この記事では心理学的・医学的観点から“人のスキ”が生まれる瞬間を探り、それを踏まえた実践的な訓練スケジュール設計について考えてみたいと思います。
🧩 なぜ人は注意を失うのか?
知っておきたい5つの「散漫タイミング」
| タイミング | 原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 🕘 朝イチ直後 | 睡眠惰性(Sleep Inertia) | 脳が完全に目覚めておらず判断力が鈍る |
| 🍱 昼食後 | 血糖値の急上昇とその後の急降下 | 強烈な眠気と集中力低下 |
| 🕔 終業間際 | 認知疲労・タスク終了意識 | 注意が雑になり「とりあえず対応」しがち |
| 🔄 マルチタスク中 | 認知資源の分散 | チェックが甘くなり、疑う余裕がない |
| 😤 ストレスや疲労時 | コルチゾール分泌・感情の揺れ | イライラ・焦りで判断ミスしやすい |
🔍 攻撃者はこの“スキ”を見逃しません。
実際の攻撃メールも、人の集中が切れやすいこのようなタイミングを狙って送られています。
昨今のフィッシング詐欺メールは24時間・365日、のべつ幕なしにメールを送ってきますが、これも、大量にメールを送ることでストレスを誘発したり、疲れているタイミングでメールを目にすることを狙ってのものと思われます。
長期休暇明けを狙って攻撃メールが送られてくるのも、休暇中に届いたメールが溜まっていて、処理に追われるタイミング、つまり、「朝イチ直後の判断力が鈍っている時にマルチタスクが発生することでストレスや疲労が溜まる」という、注意力が確実に落ちると思われるタイミングであるからこそです。
📅 訓練スケジュールへの応用ポイント
この心理的な“スキ”を活かし、本人に気づきを得てもらうには、「いつ訓練メールを送るか」が極めて重要です。以下のように、意図的に集中力が切れやすいタイミングを狙ってみましょう。
なお、配信時間帯に記載している時刻はあくまで一般的な企業を想定した場合の時刻です。業種や業態によっては勤務体系も異なりますので、集中力が切れやすいタイミングも当然異なるでしょう。
自社の業務と照らし合わせながら、自社ではどのような時間帯が集中力が切れやすいか?を考えるのがポイントです。
✅ 1. 時間帯別に複数の訓練を設計
| 配信時間帯 | 狙い | 例文の方向性 |
|---|---|---|
| 9:15ごろ | 睡眠惰性が残る時間帯。通勤直後でまだぼんやり。 | 「勤怠打刻エラー」「急ぎの報告依頼」系 |
| 13:30ごろ | 昼食後で眠気が強く、チェックが甘くなる | 「支払い処理ミス」「クレーム対応」系 |
| 17:20ごろ | 終業間際で急ぎ処理しがちな時間帯 | 「請求書未確認」「取引先からの連絡」系 |
💡 同じメールでも時間帯をずらして送れば、反応の違いから「心理的な弱点」が可視化できます。
集中力が切れやすいタイミングがいつか?がはっきりしない場合は、様々な時間帯で訓練メールを送ってみて、その結果から分析を行うのも一つの方法です。
✅ 2. 忙しい業務の“スキマ”を狙う
Zoom会議中や、日報作成時間などマルチタスク状態が想定される時間帯をあえて狙ってみましょう。
※例えば「10:55」や「15:55」など、次の予定直前を狙うと効果的かもしれません。
✅ 3. 月末・週明けなど“テンションが変動する日”を選ぶ
| 日付例 | 狙い |
|---|---|
| 月曜日 | 週の初めでエンジンがかかっていない |
| 金曜日 | 早く帰りたい心理が強くなりがち |
| 月末 | 経理・総務が多忙で疲労もピークに |
💡多忙なタイミングで訓練メールを送ることについては社内でも賛否が分かれるところかもしれません。攻撃者はこうした隙を狙って攻撃を仕掛けてくるであろうことは想像に難くないので、忙しいタイミングだからこそ、訓練を実施するべきという考え方はあります。
しかし、反面、「実際の業務に影響が出たらどうするんだ?」という意見も至極真っ当であり、無視して良いものでもないでしょう。
このように、社内でも意見が割れるような時こそ、それをきっかけに議論を深める機会を持つことが大切です。実際に攻撃され、被害が出てから慌てるのでは無く、起こり得る可能性を想定しておき、前もって話し合っておくことが、いざという時に大きく効いてきます。
議論の結果、「忙しいタイミングでは訓練メールは送らない」となったとしても、議論をした過程で課題感を社内で共有し、いざという時にどうすれば良いかについて考えるきっかけとなったのであれば、それはそれで一つの成果と考えて良いと思います。
📈 訓練結果の“見え方”も変わる!
時間帯やタイミングを意識した訓練を行うことで、例えば、以下のような気づきが得られます。
- 「午後に限ってクリック率が高い社員が多い」
- 「同じ訓練でも、終業前は報告率が下がる」
- 「タスクが重なると判断が雑になる社員が多い」
📊 単なるクリック率や報告率ではなく、**「心理状態別の傾向分析」**という新たな指標で、社員のセキュリティ感度を可視化してみることをお奨めします。
🎯 訓練は“タイミング設計”が命!
標的型攻撃メール訓練においては、**「どんな訓練メールを作るか」だけでなく、「どんなタイミングで送るか」**によって、結果が変わってきます。
🛠 訓練担当者が取り入れたい工夫
- 時間帯をずらした多層的訓練スケジュール
- 週の中でも気持ちがブレやすい日を選定
- 集中力が下がる瞬間を狙ってメールを配信
想定したとおりの結果となるかどうかを検証するために、特定の時間帯に訓練メールを送るやり方もあれば、特定の時間帯に訓練メールを送ったら社員はどのような反応をするか?を調べるために訓練メールを送るやり方もあります。
いずれにしても、タイミングを意識して訓練を実施することは重要です。
これまであまり深く考えずに訓練メールを送信していた。とか、
業者に言われるままに訓練メールを送信していた。ということであれば、
これを機会に、訓練メールを送信するタイミングについて考えてみていただければと思います。