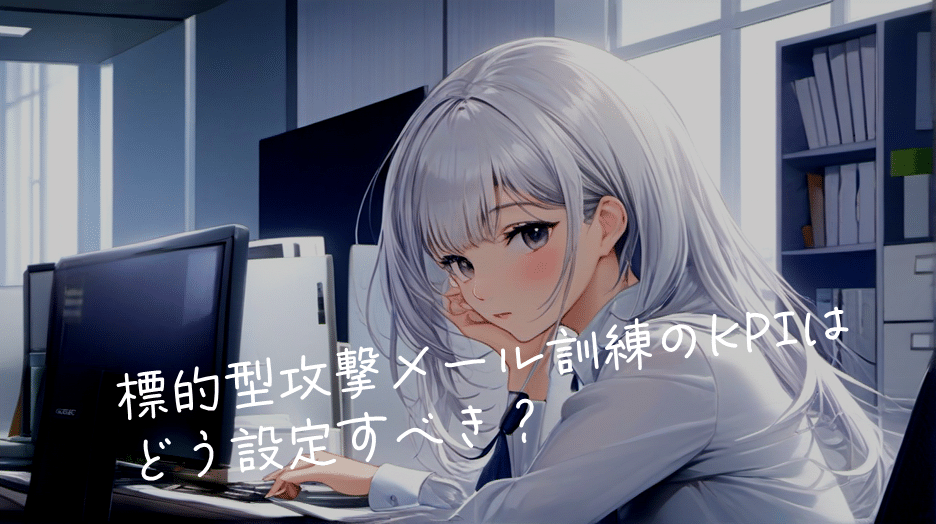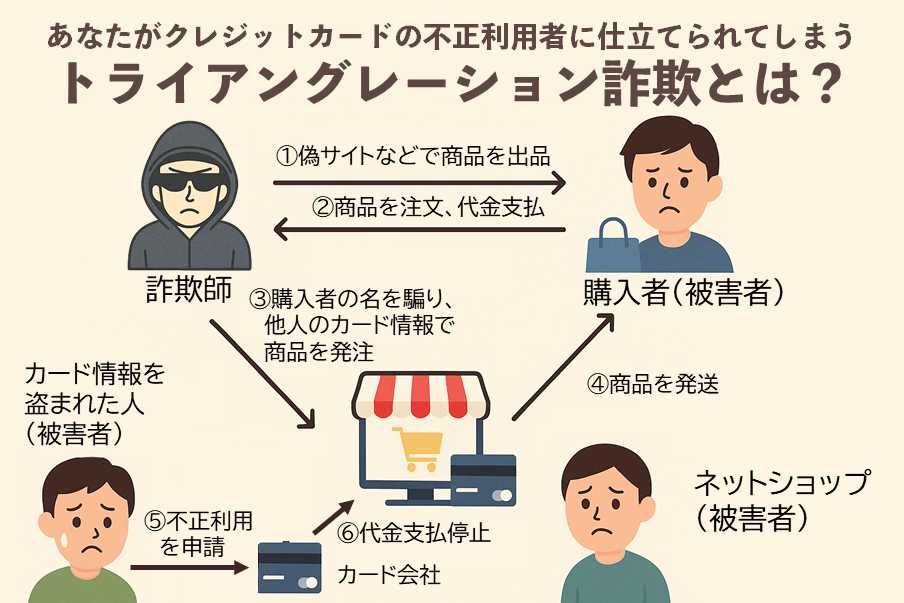フィッシングメール訓練には効果がない
とする声が、一部で聞かれるようになってきました。
実際、**日経クロステックの記事(参考リンク「「フィッシングメール訓練」は効果があるのか、2万人対象の大規模調査で驚きの結果」)**でも、そのような主張が紹介されています。
このような主張を見ると、それも、証拠となるデータを元に解説がなされていると、「やはり、フィッシングメール訓練なんて効果が無いんだな」と思ってしまいがちです。
しかし、これは訓練自体に意味がないということではありません。
むしろ問題なのは、“訓練のやり方”に工夫が欠けていることです。
🧠「答えを覚えるだけ」の学習に限界がある
「演習問題を解いて、間違ったところの正解を覚える」という学習法は、受験でもよく使われます。
ですが、単に“正解を覚えただけ”では、成績が上がらないというのもまた事実。
なぜなら、本質的な理解がなければ応用が効かないからです。
たとえば、選択肢のうち「この形式ならAが正解」と機械的に覚えてしまえば、少しでも出題の切り口が変わっただけで、もう対応できなくなります。
似たような問題なら正解できるけれど、ちょっと問題文を組み替えたら全く正解できなくなるようなケースは、本質を理解できていない事の典型です。
💬 フィッシングメール訓練にも、同じ落とし穴がある
フィッシングメール訓練で「効果が無い」と言われる場合、
多くはこうした 「答え合わせ型訓練」に陥っているケースです。
- リンクをクリックしたら「これは訓練でした」と表示
- 「次から気をつけましょう」とだけ伝えて終了
- 解説はあるが、本人は読まずに流す
- なぜそのメールが危険だったかを本人が理解していない
これでは、**「このメールは怪しいメールっぽいかどうか」を判別する“ゲーム”**になってしまいます。
当然、現実の攻撃には太刀打ちできません。
このような訓練を続けたところで、思うような結果が得られないのは当然で、この結果から「フィッシングメール訓練は効果が無かった」と主張するのは、素振りの練習だけやってバッティングが上手にならなかったからといって、素振りの練習はバッティングの上達に効果が無かったと主張するようなものです。
乱暴な言葉で言えば、「形だけの訓練をやりました。効果がありませんでした。そりゃそうでしょうね。」って話です。
🛠 本質的な理解を促す仕掛けを入れよう
本当に効果のある訓練にするためには、以下のような工夫が欠かせません:
✅ 「なぜ怪しいのか?」を自分で考えさせる
- 回答解説の中で、具体的な不審点に気づかせる仕掛けを設ける
- 添削式のワークや、判断根拠を書かせる形式も効果的
✅ 「他の場面でも応用できる知識」に落とし込む
- 特定の文面だけでなく、URL確認や差出人確認の方法など汎用スキルを解説
- 「似たパターン」を複数提示することで、知識を抽象化させる
✅ 心に残る「気づき」を得られる仕掛け、演出を設ける
- サポート詐欺ややり取り型攻撃など、日常的に見落としやすい手口を題材にする
- 訓練後の解説動画で、“感情”に訴える気づきを与える演出を用意する
大事なポイントは、”本人の自主性に頼らない”ということです。
実施する側からすれば、本人が自主的に学習してくれれば楽ですが、”やらされ感”を持って訓練に臨んでいる社員が自主的に学習に臨むことは期待薄です。
もちろん、うっかりクリックしてしまったことをきっかけに気づきを得て、前向きに取り組んでくれるようになるという人もゼロではありません。しかし、全員が全員そうなるわけではないでしょう。
だからこそ、訓練の実施には創意工夫、そして仕掛けが必要なのです。
❓ 御社の訓練、「正解を当てること」が目的になっていませんか?
フィッシングメール訓練は、「正解を当てる力」を養うためのものではありません。
「なぜそれが危険かを判断できる目」を育てることこそが本質です。
受験勉強と同じように、間違いの背景を理解し、自分の弱点と向き合ってこそ、本当の実力がつくというものです。
単なる答え合わせに終始する訓練では、訓練を重ねても社員は強くなりません。
だからこそ、訓練の中に“本質的な理解を促す工夫”があるかどうかを、今一度問い直すことが重要です。
成績を上げる勉強と同じで、「どうして間違えたのか」を深く掘り下げることが、本当の成長に繋がります。
これはセキュリティ教育においても同様です。
そして、本質的な理解が必要なのは、訓練メールに騙されなかった人にも当てはまります。
「たまたま騙されなかった」というのではなく、本質的な理解ができているからこそ、騙されなかったということであるべきで、訓練メールに騙されなかった人にも本質的な理解を促すアプローチもあってしかるべきだと思うのです。
その意味では、あえて全員にリンクをクリックしてもらい、攻撃者の狙いや手口を知ってもらうような訓練のやり方も、工夫の一つなのではないかと考えます。
また、特定の担当者が訓練を実施するのではなく、社員が持ち回りで訓練を実施することで、実際に攻撃者の視点に立ってもらうというやり方も、本質的な理解を促すという点では有効でしょう。
✍ 最後に
組織によっては様々な理由から「ウチでは効果が出る訓練に取り組むのは無理そうだ」というところもあるかもしれません。
そのような組織においては、効果が出せそうにない訓練に取り組むよりも、セキュリティ対策システムの導入や強化など、あえて別の施策に注力する方が賢明ということはあるかもしれません。
しかし、効果が出る訓練に取り組む気力や余力はあるという組織も少なくないはずです。
「フィッシングメール訓練は効果が無い」という論文の主張を見て、
「ああ、やっぱりそうなんだ」と納得してしまう前に、
「正解にたどり着いた理由」まで掘り下げられるような訓練設計が果たしてできていたのか?
「効果が出るやり方」を考えることに正面から向き合ってきたか?
を考えてみてもらえたらなと思います。
答え合わせで終わる訓練から、
「気づき」と「納得」を育む訓練へ。
それが、真に効果のあるフィッシングメール訓練の第一歩です。