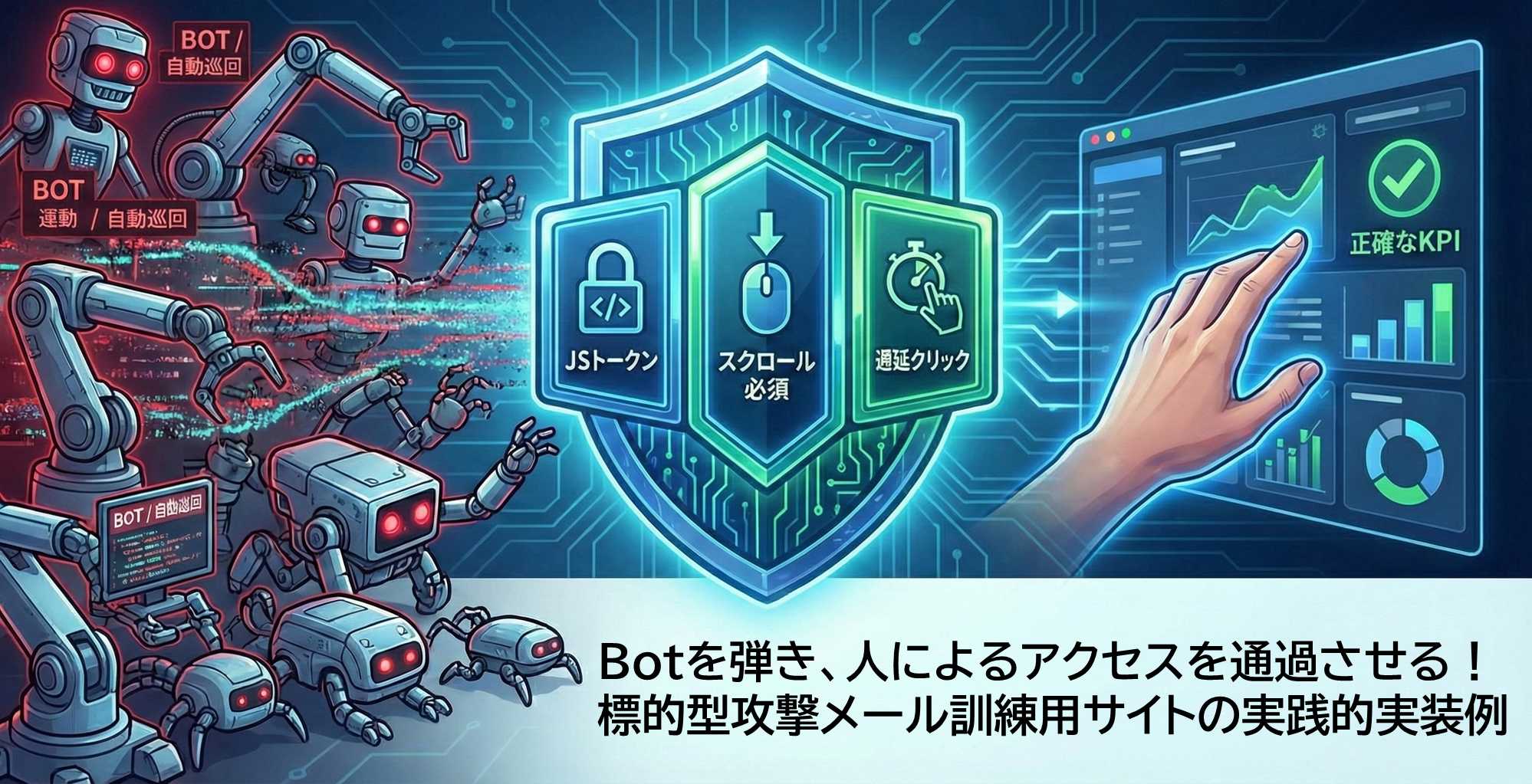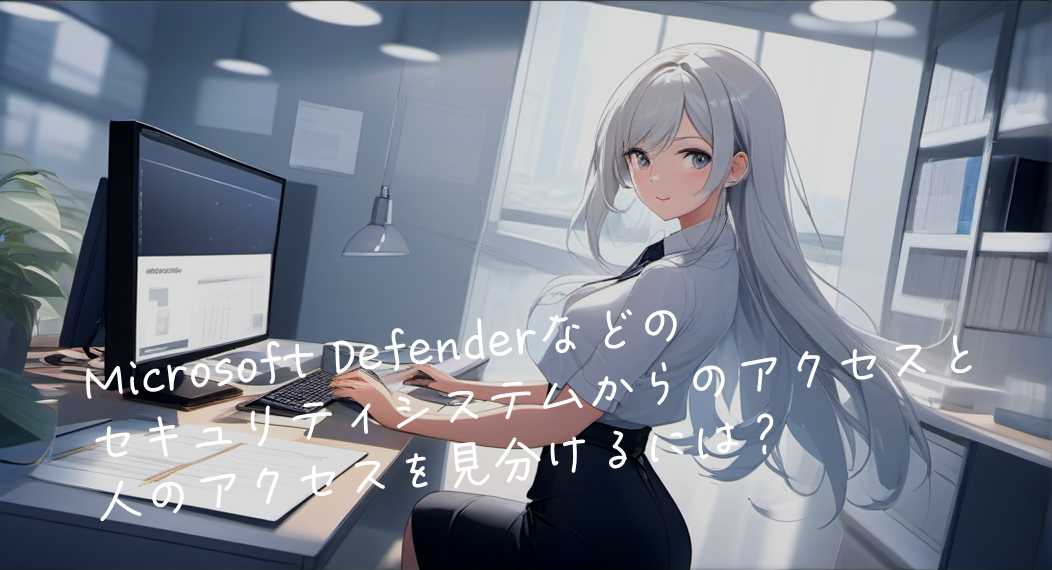現実に届かないメールを使った訓練に意味はあるのか?
「こんなメール、見たことないですよ」
「これ、本当に実際に届くんですか?」
標的型攻撃メール訓練を実施した際、こんな声が社員から上がったことはありませんか?
確かに、訓練で使用したメールが、日常的に見かけるようなメールと雰囲気が異なると、「リアリティに欠ける」と感じる人が出るのは自然なことです。しかし、現実に届いた実績がないメールであっても、訓練として意味がないわけではありません。
今回は、その理由と、社員にどう伝えるべきかを考えてみたいと思います。
🎯 訓練の目的は「経験させること」
まず、標的型攻撃メール訓練の目的は、「経験によって気づく力を養う」ことです。
たとえば、火災訓練では、実際に火事が起きたことがない会社でも消火器の使い方を練習します。それと同じで、「起きたことがない」からといって、「起こり得ない」わけではありません。
メールの不審な特徴、たとえば:
- 表示URLとリンク先URLが違う
- 急かすような文言
- 添付ファイルへの不自然な誘導
こうした**「見分けのポイント」**を実体験として学ばせるには、現実に届くかどうかとは別に、疑似体験を提供することが重要です。
実際の攻撃メールには様々な攻撃手法があり、見分けポイントとして挙げられる項目も色々ありますが、一つの攻撃メールで使われている手法はそのうちの幾つかでしかありません。
しかし、標的型攻撃メール訓練が実施できる回数は限られているため、訓練メールの内容を実際の攻撃メールと同じ内容としていたのでは、全ての見分けポイントを網羅することはできないので、見分けポイントを学んでもらうために、実際の攻撃メールとは異なる内容となってしまう場合もあることは致し方ないところです。
📚 「想定外」のための訓練
サイバー攻撃は、想定されていないところを突いてくるのが常です。
つまり、**「今までに見たことがないメールこそ、狙われる可能性がある」**ということ。
訓練に「違和感」があることは、実は訓練としては成功の証でもあります。
「違和感を感じた」「変だと思った」——この気づきこそが、防御の第一歩。
現実にまだ来ていないメールでも、攻撃者が次に使ってくるかもしれない手口を想定し、先回りして体験させることが、訓練の大きな意義です。
👥 社員への伝え方のポイント
「現実的でない」と言われたときに、訓練担当者として伝えたいメッセージは、次のようなものです:
🔐 「このメールは“今までに来ていない”かもしれません。でも、“これから来ない”とは限りません。実際に攻撃されてからでは遅いのです」
また、次のようなアナロジー(比喩)を交えて伝えるのも効果的です:
🧯 「防災訓練でやる“地震が起きて火災が発生”のシナリオも、今までに経験したことがない人がほとんど。でも、だからといって訓練が無意味ではないですよね?」
🚨 「現実的」であるよりも「教育的」であること
現実に似せることももちろん大切ですが、訓練メールは教育的効果を優先して設計されています。
つまり、**「気づくべきポイントに気づけるか?」**という観点で設計されており、リアリティ重視ではなく“気づき”を促す設計なのです。
現実の攻撃メールがここまで親切に“見破りポイント”を提示してくれることは稀です。
むしろ訓練メールの方が、気づいてもらいやすい“ヒント”が散りばめられているのです。
🚨 「現実的でない」と言ってくる社員には2種類ある
これまでの経験上、「現実的でない」と言ってくる方は、以下の2つのどちらかであることが多いようです。
・実施には届くことがないと思われる内容で訓練を実施しても意味が無いと考える人
・訓練メールに自分が騙されてしまったことに腹を立てている人
前者と後者では、同じ「現実的でない」という指摘でも、裏側に隠れている心理は異なります。
🧠 タイプ①:「実施に意味がない」と冷静に考えている人
このタイプは、訓練メールの内容が過去の実例に無く、現実離れしていると感じているため、訓練の有効性に疑問を持っています。
彼らに伝えるべきポイントは以下の3点です。
✅ 実際に“ありえなかった攻撃”が後から起きることがある
- 攻撃者は過去のメールの模倣ではなく、想定外の手口を好む。
- 訓練は「今起きている攻撃」だけでなく、「これから起こるかもしれない攻撃」に備えるもの。
✅ 防災訓練と同じく、“まだ起きてない”事象にも備える必要がある
- 例えば火災訓練では、誰も火事を見たことがなくても消火器を使う練習をします。
- セキュリティ訓練も、未然の備えが目的です。
✅ 訓練は“教育的”な設計が優先される
- 「気づけるかどうか」が訓練の目的。
- 表示URLとリンク先URLの違い、件名の文面の違和感など、判断のポイントに気づく訓練です。
😠 タイプ②:「騙されたことへの怒り」を正当化している人
このタイプは、訓練メールに自分が引っかかったことに不快感を持ち、それを「現実的でないから仕方ない」と**“正当化”している**ケースが多く見られます。
この場合は以下のような伝え方が効果的ですが、自身が騙されたことを指摘してしまうと、本人の怒りに油を注ぐような結果になる恐れもあるため、対応には慎重さが求められます。
✅ 騙されたのは「能力」ではなく「経験」の問題
- 引っかかったからといって、その人が劣っているわけではありません。
- 「初めて出会う手口」なら誰でも騙される可能性があるということを強調。
✅ 訓練で“悔しい”と感じることはむしろ良い兆候
- それは「気づき」が生まれた証。
- 「次は騙されないようにしよう」と思えることが最大の収穫。
✅ 訓練で引っかかって良かった!現実の攻撃でなくて本当に良かった!
- 「本番だったら被害が出ていたかもしれない」と想像できる機会。
- 訓練だからこそ失敗してもリスクゼロ。その経験こそ、訓練最大の価値。
💬 タイプ別の声かけ例
💡 タイプ①への声かけ:
「たしかに、現実に来たことはないかもしれません。でも、だからこそ“今のうちに体験しておこう”という考え方も大切なんです」
💡 タイプ②への声かけ:
「もしこれが本物の攻撃メールだったら…と思うとゾッとしますよね。でも訓練で気づきが得られたことは、むしろすごいことだと思います」
✨ 訓練は、“見たことのない攻撃”に備えるためにある
- 「見たことないから意味がない」ではなく、「見たことないからこそ備える」
- 「引っかかったことが悔しい」ではなく、「訓練で気づけてよかった」
社員の指摘には、単なる批判ではなく心理的背景があることを理解し、適切に対応することで、訓練の価値がさらに伝わるようになります。
「今までに来たことがないから訓練は不要」は、セキュリティ対策としては危険な考え方です。
「来たことがないメール」だからこそ訓練する意味がある。
攻撃者は、過去ではなく未来からやってくるのです。
そのときに備えるために、今、私たちは訓練をしているのです。