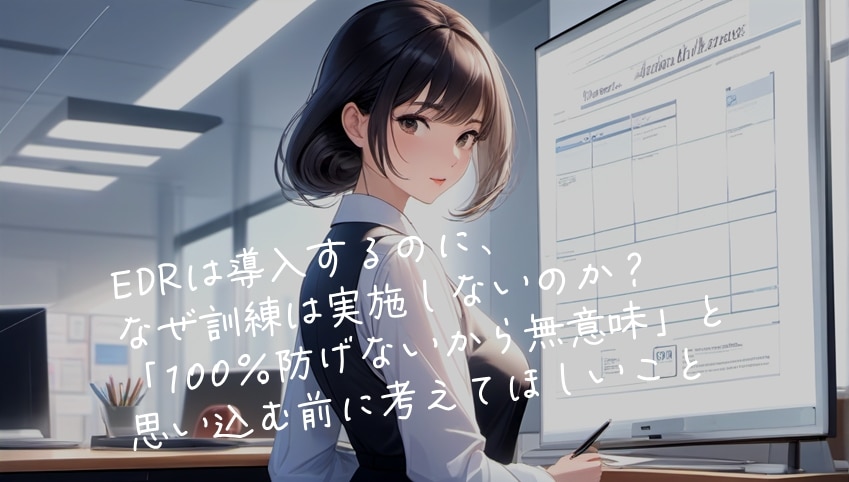
セキュリティ対策=システム導入で終わり?
多くの企業が、EDR(Endpoint Detection and Response)などのセキュリティシステムを導入しています。
不審な通信の検知や感染拡大の抑制といった、いわば“自動ブレーキ”としての役割を果たすこれらのシステムは、「とりあえず入れておけば安心」という気持ちにさせてくれるものです。
しかし一方で、標的型攻撃メールへの対応力を高める「訓練」については、「100%見分けるのは不可能だからやっても意味がない」として、最初から検討すらされないことも少なくありません。
けれど、EDRだって100%の防御が保証されているわけではないのです。
なのに、なぜ訓練だけが“無意味”とされてしまうのでしょうか?
⚖️EDRも訓練も“100%防御”はできない
- ✅ EDR:攻撃を“技術で止める”
- ✅ 訓練:攻撃に“人が気づく力をつける”
どちらも「100%攻撃を防ぐ」ことはできません。
しかし、それぞれの役割と強みは異なります。
むしろ**“100%防げない”からこそ、両方が必要**なのです。
🤖なぜEDRは受け入れられやすく、訓練は敬遠されるのか?
✅ EDRは「導入すれば仕事が終わる」
- ベンダーが導入してくれる
- 可視化レポートも自動で出る
- 数字で効果をアピールしやすい
- 「導入した」という事実が対外的にも説明可能
EDRのようなシステムは、ベンダーに依頼して導入・設定してしまえば、その後の運用はIT部門に任せておけばよいと考えられがちです。
「導入するだけで仕事をしたことになる」「数字として投資効果をアピールしやすい」という面があります。
👉 つまり、“やってる感”が出しやすく、意思決定も通しやすいのです。
❌ 訓練は「人を巻き込むから面倒」
一方、訓練は「社員を対象とした教育活動」であり、
- 実施前の説明と調整
- 実施中のトラブル対応
- 実施後の結果フォロー
- 社員からの不満や誤解のリスク
など、“人”を巻き込む要素が多いため、担当者にとって負担が大きく感じられます。
👉 つまり、訓練には**“手間と労力”がついて回る**ため、実施のハードルが高く見られがちです。
🧠「100%見分けられないから無意味」は誤解
「訓練しても100%見分けられるようにはならない」──それは事実かもしれません。
✨ ですが、訓練の本当の目的は…
- メールを見分ける感度を上げる
- 報告行動を習慣化する
- ミスや失敗をすぐに報告できる土壌を育てる
というように、”見分ける力の“底上げ”と、“引っかかった時の行動”を身につけさせることです。
たとえクリックしてしまっても、すぐに上司に報告できるかどうかで、被害の大きさは大きく変わります。これは、どんなに高性能なEDRでも代わりにやってくれない“人間の役割”です。
🔁「訓練」は、実際の攻撃が来た時に“早く気づき、対応する”ための練習です。
🔓EDRでは防げない「人を狙う攻撃」に備えるには?
EDRが防げるのは、既知のマルウェアや異常な挙動です。
しかし最近の攻撃は…
⚠️「人の心理をつく」巧妙なものばかり
- 信頼関係を装ったメール
- 本物そっくりなログイン画面
- サポート詐欺やClickFix型の操作誘導
こうした攻撃は**“ユーザーが騙されるかどうか”**が突破口になります。
つまり、**EDRをすり抜けた最後の砦は“人間”**なのです。
🔄EDRと訓練は補完関係である
| 項目 | EDR | 標的型攻撃メール訓練 |
|---|---|---|
| 対象 | 技術的な攻撃 | 人を騙す攻撃 |
| 主な機能 | 検知・隔離・可視化 | 気づき・判断・報告 |
| 得意分野 | マルウェアの挙動解析 | フィッシングやソーシャルエンジニアリング対策 |
| 役割 | ブレーキシステム | ドライバーの運転技術向上 |
経営層にとって必要なのは、
「被害を未然に防ぐ仕組みを組み合わせる」という視点です。
- セキュリティシステム:技術による検知・隔離
- セキュリティ訓練:人的ミスを防ぐリテラシーと行動の育成
どちらも完璧ではありませんが、両者を組み合わせてこそ、リスクを最小限に抑えることができます。
🚗 自動ブレーキがあっても、ドライバーが安全確認できなければ事故は防げません。
オートパイロットが機能する車に乗っても、走行中にハンドルから手を離すことは怖いと感じる人は多いのに、EDRを導入しているから人の目で確認しなくても大丈夫と考えるのはおかしくないですか?という話です。
しかも、セキュリティ侵害による損失は、自動車事故による損失の比ではないくらい、大きな損失に繋がりかねないのにも関わらず。です。
💡セキュリティ対策に必要なのは“両輪”のバランス
- ✔️ 技術的対策(EDR・メールフィルター等)
- ✔️ 人的対策(訓練・教育・文化)
この両方があってこそ、多層防御(Defense in Depth)が実現します。
訓練は“効果が見えにくい”かもしれませんが、意識と行動を変える唯一の手段です。
✅訓練を「無意味」と切り捨てないで
「EDRは入れるが訓練は無意味」という発想は、
“技術だけで守れる”という楽観的な幻想に過ぎません。
「訓練をしても100%見分けられないからやっても無意味」
という言葉の裏には、
✒️「完璧じゃなければ意味がない」という危険な思考停止
があります。
でも、実際の現場では**「100%防げない」からこそ準備が必要**であり、補完し合う必要があるのです。
セキュリティ対策において最も恐ろしいのは、人的リスクを軽視することかもしれません。
EDRと同様に、**訓練も企業の防御力を高める“投資”**であることを忘れてはいけません。





