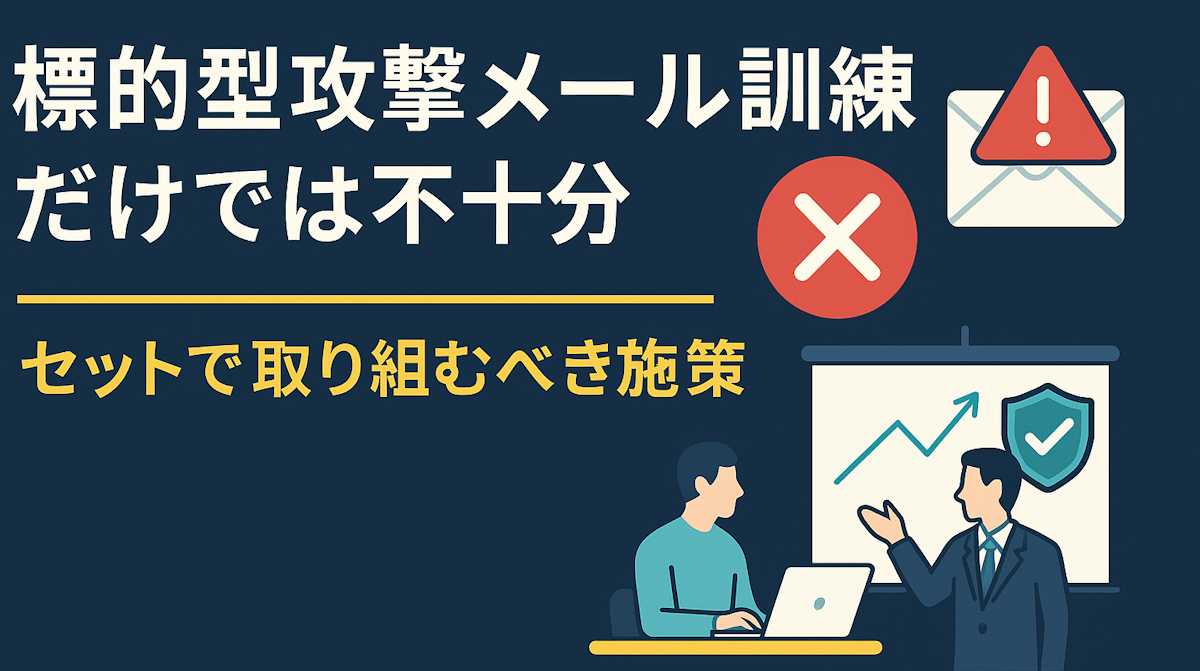🔥実在企業を騙る広告に騙される人が急増中
最近、**YouTube上などで「大手企業などの名前を騙る広告」**が横行しています。たとえば「○○(大手メーカーの社名)が開発した!」と謳う怪しいガジェット、「○○(有名大学の名称)が推薦!」とうたうよくわからない商品……。
もちろん、実際にその企業が関与している事実は一切ありません。
にもかかわらず、こうした広告を信じて商品を購入してしまう人が後を絶たないのです。
🧠「ファクトチェックすればわかる」──それでも騙されてしまう理由
「ちょっと検索すればすぐ嘘だとわかるのに…」
そう思った方も多いでしょう。しかし、それが誰にでもできるとは限らないのが現実です。
✅ 騙される理由その1:情報リテラシーの格差
- インターネット検索やSNSに慣れていない人ほど「広告=信頼できる情報」と思いがちです。
- **「動画でプロっぽく紹介されている=本物」**と感じてしまう人も少なくありません。
✅ 騙される理由その2:「権威の錯覚」
- 実在する企業のロゴや名前が映っているだけで、“あの企業が出している商品”と思い込んでしまう心理が働きます。
- 特に高齢層やネット広告に慣れていない層は、この権威づけの罠に陥りやすいのです。
✅ 騙される理由その3:広告に対する“受け身”の姿勢
- 「自分に合っている商品を表示してくれている」と広告を自分の味方と勘違いするケースも。
- ファクトチェックの手間を惜しみ、「すぐ買ってしまう」行動も見受けられます。
- 大手の会社が提供しているサービスだから嘘の広告など表示するわけがないという思い込みが、「疑う」という思考を自ら排除してしまいます。
👥その人、あなたの会社にもいます
ここで忘れてはならないのが、こうした“騙されやすい人”は社会の中に存在しているという事実です。
つまり、
▶ そのような人も「社員」として働いている可能性があるということ。
▶ あなたの会社のパソコン、あなたの会社のクレジットカード、あなたの会社の情報資産にアクセスできる立場にあるということ。
**「プライベートでの被害」**が、
**「会社全体にまで波及するリスク」**を秘めているのです。
・あなたの会社の社員が嘘の広告に騙されて会社のクレジットカード情報を入力してしまったら?
・大手の会社名を騙った偽のメールに騙されて業務システムへのログイン情報を入力してしまったら?
プライベートで騙されてしまうのと同様に、業務でも騙されてしまう可能性は十分考えられるのです。
📣会社として取り組むべき“だまされない教育”
こうしたリスクを防ぐために、企業は情報リテラシー教育やセキュリティ教育を社内で行う必要があります。
💡教育のポイント
- 「本物そっくりの広告」に騙された実例を紹介する
- なぜ人は騙されるのかを心理面からも解説する
- 大手企業が提供しているサービスだから安全と考えるのは間違いであることを示す
- **「怪しいと思ったときの調べ方」**を実習形式で身につけさせる
- **「自分ごと化」**させる工夫(例:社内で匿名アンケートを取り実態を可視化)
🛡️社員を守ることは、会社を守ること
騙されやすい人が悪いのではありません。
悪いのは、そのリスクを理解せず放置することです。
社員一人ひとりの判断が、会社の信用や安全性を左右します。
「自分の会社は大丈夫」と思っている管理職こそ、まずは一度このテーマに向き合ってみてください。
✉ まとめ
- 嘘の広告に騙される人は想像以上に多く、誰もが被害者になり得る。
- 騙される原因は「情報リテラシーの格差」「権威の錯覚」「広告に対する受け身」など。
- そうした人が働いている以上、会社としても対策が必須。
- 「教育」は最大の予防策。正しい知識を届ける仕組みづくりが会社を守る。
嘘の広告に騙されるなんて、騙されるヤツが馬鹿なだけだ。と思うのは簡単です。
しかし、そうした人が自社の社内に居るかもしれないということのリスクを会社は考えるべきです。
嘘がまかり通る時代においては、個人のリテラシーを高め、個人を守ることは、会社を守ることでもあるのです。