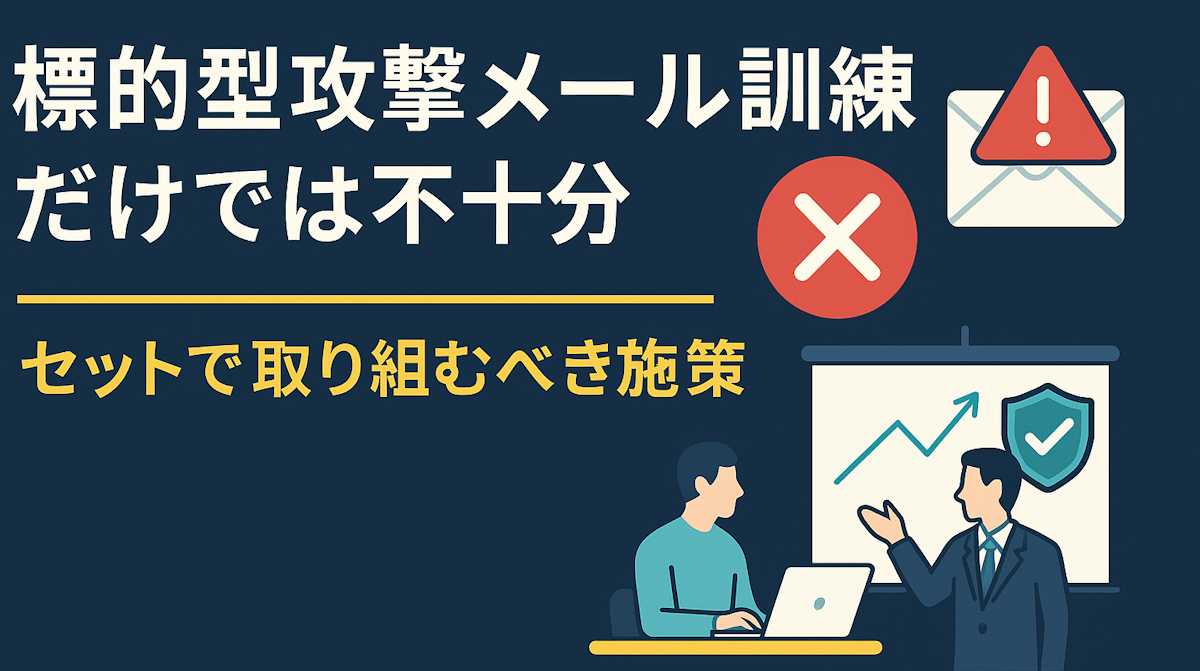🧠 AIで作られた“ビートたけし”が語りかける衝撃
2025年、ある公共広告が注目を集めました。
そこに登場したのは、かの有名なビートたけし氏──のように見える人物。
しかし、その映像はAIによって生成された“フェイク”でした。
フェイクは、ホンモノみたいな顔をする。(公益社団法人 ACジャパン)
🎙️「今、あなたが触れているその情報、本物だと信じていいと思いますか?」
そんな問いかけが、テレビの前の私たちに突き刺さります。
信じていたものが、簡単に偽れる時代。
“AIフェイク”が、ついに公共広告という公的メッセージの中でも扱われる時代がやってきたのです。
🎯 なぜ公共広告でフェイク映像を用いたのか?
公共広告といえば、交通安全や薬物防止など、社会にとって“正しい行動”を促すための手段です。
そんな中で、「これは偽物です」とあえて明かす映像を流したのは、次のような意図があったと考えられます。
- AIによるフェイク技術はすでに “誰でも使える脅威” になっている
- 社会全体に「本物らしさ=信頼性ではない」ことを知らしめる必要がある
- 「見た目」や「声」が一致していても信用できない時代が始まっている
こうしたリスクを “気づかせるきっかけ” として、あえてフェイクを使ったと推察されます。
つまり、これは単なる警告ではなく、社会が「フェイクとどう共存するか」を考える時期に来たという宣言でもあると思うのです。
⚠️ AIフェイクは映像だけじゃない
映像・音声だけでなく、次のようなビジネス上の“なりすまし”も、AIによって急速に巧妙化しています。
| フェイクの手口 | 内容例 |
|---|---|
| 📧 フェイクメール | 役員を装った振込依頼メール(BEC攻撃) |
| 🧑💼 フェイク人物 | 存在しない“カスタマーサポート”や”なりすまし社員”がチャットで誘導 |
| 🌐 フェイクWebサイト | 本物そっくりのフィッシングページをAIが自動生成 |
これらは、いずれも「本物のように見えるが、実は偽物」という“視覚・感覚への依存”を逆手に取った攻撃です。
🧩 判断を個人に任せる時代は終わった
AIフェイクが進歩し、本物そっくりのクオリティにまでレベルが上がっている今では、
「このメール、おかしいかも」「この動画、なんか変だな」
――こうした直感だけで見抜くのは、もはや困難となってきています。
これからの企業が直面するのは、次のような課題です。
- 🔄 判断の属人化がリスクを生む(人によって見抜けたり、見抜けなかったり)
- 📉 属人的判断は 再現性がなく、教育効果も曖昧
つまり、「信じていいかどうか」は、個人の感覚に頼るのではなく、仕組みで判断するべき時代に入ったということです。
これまでのように、詐欺メールに騙されないようにするのは個人としてあたり前のこと、一般常識の範疇であり、わざわざ会社が教えるようなものではないとして個人の自己研鑽に任せるという考え方は時代遅れであり、もはや会社として仕組み化することを考えなければならないと思うのです。
✅ 企業が今取り組むべき3つのアクション
では、仕組みで判断するというのは具体的にどのようなことでしょうか?
それは、個人の勘や経験に頼らず、明文化されたルールやプロセス、ツールによって誰でも同じように判断できるようにするということです。
🧭 「感覚で判断」と「仕組みで判断」の違いとは?
| 項目 | 感覚で判断 | 仕組みで判断 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 各人の経験・直感 | ルール・マニュアル・ツールによる一貫性ある基準 |
| 再現性 | 人によってバラつく | 誰でも同じ判断が可能 |
| 教育コスト | 属人的で教えづらい | マニュアル化・標準化が可能 |
| セキュリティリスク | 見落としや錯覚の可能性あり | 多重チェックやロジックで誤りを検出できる |
🔍 では、どのようにすれば「仕組みで判断」できるのでしょうか?
✅ 1. 判断基準のルール化・文書化
例)「不審なメール」を仕組みで判断するには?
- 件名があいまい・過剰な緊急性を訴えている
- 送信者アドレスと表示名が一致しない/ドメインが怪しい
- 本文にリンクが含まれていて、表示URLと実際のリンク先が違う
- 個人情報・ログインを促す内容がある
➡ このようなチェックリストを用意しておけば、誰でも同じ基準で判断可能になります。
✅ 2. ツールや仕組みによる二次確認
例)送金依頼メールの承認フロー
- メールで来た依頼内容をSlackやTeamsで必ず口頭確認する
- 指示があった場合、自動的に上長が確認するワークフローを通す
- リンク先URLの検証ツール(例:VirusTotal、Google Transparency Report など)でチェック
➡ 人の感覚に頼らず、プロセスやツールを組み込むことでミスを防ぎます。
✅ 3. 誰がやっても同じ判断になる環境作り
- 決裁・申請・報告の業務プロセスに「本人確認・二要素認証・多段承認」などを仕込む
- セキュリティに関わる判断は、“必ず複数人が関与する”ように設計
- 社内教育では、**事例ベースで「ルールに照らして考える練習」**を繰り返す
以上のように、”見抜ける人”が持っている知識を社員全員で共有し、誰もが同じ基準で判断ができる、また、一人が突破されてしまうことがあっても、他のメンバーが盾となって防御できるよう、属人頼りにならない”仕組み”として構築すること。
これは組織であるからこそできることであり、また、組織だからこそ構築すべきものだと思うのです。
💬 フェイクが前提の社会で、信頼を築くには
「その情報は本物ですか?」と問われたとき、
私たちは**“はい”と即答できる材料を、どれだけ持っているでしょうか。**
企業はこれから、次のような責任を負うことになります。
🛡️ 社員をフェイクから守ること
🔒 顧客をフェイクに騙させないこと
📣 自社の情報がフェイクに利用されないように守ること
AIによって「本物らしさ」が誰でも作れる時代。
だからこそ、“本物であることを証明する責任”は、企業側に求められています。
- 直感や経験ではなく、判断の“道筋”をルールとプロセスで整備する
- 誰でも判断できるようにする仕組みを、あらかじめ作っておく
- その仕組みを、すべての社員に“徹底して共有する”
こうした「仕組みによる判断」が、これからの企業の信頼と安全を守る“土台”になります。
📝 今できる第一歩として、社員の「気づく力」を育てる訓練から始めてみませんか?