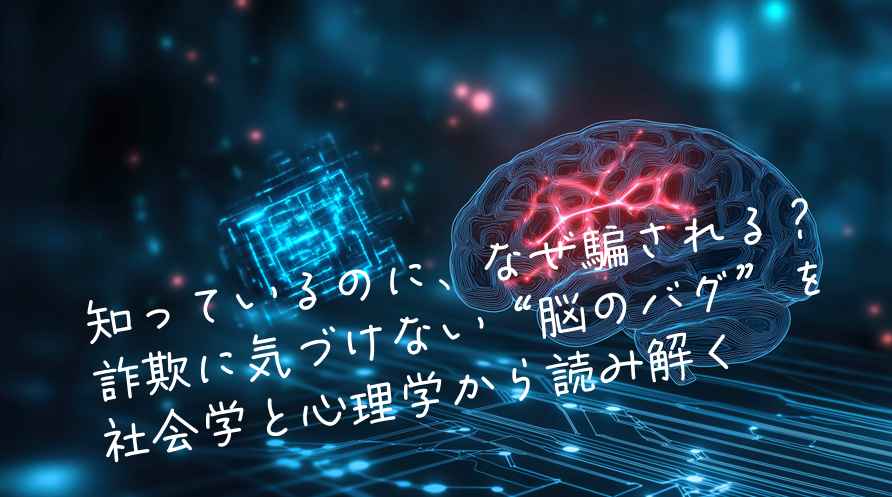
💬「これ、どう見ても詐欺じゃん」…そう思っていたのに
テレビで詐欺の被害者インタビューを見て、ついこんなふうに感じてしまったことはありませんか?
「いやいや、そんなの絶対怪しいでしょ。自分だったら絶対引っかからないよ」
ところが――
実際に詐欺に遭ってしまうのは、**「詐欺の手口をよく知っている人」**であることも、少なくありません。
例えば、学校で生徒にフィッシング詐欺などの危険性について教えていたはずの講師自身が、
ある日突然、自ら被害者になってしまったという話も実際に存在します。
【参考記事】都立高講師が「サポート詐欺」被害
🧠「知っている」と「気づける」はまったく別物
詐欺の手口を知っているからといって、
実際にそれを**“その場で見抜ける”とは限らない**――これは多くの人が見落としがちな盲点です。
- 🧩 詐欺と気づくには「知識」より「その場の判断力」が必要
- ⏳ 詐欺の多くは、考える“余裕”を与えないように設計されている
つまり、**詐欺とは“正常な判断をさせないように設計された罠”**なのです。
詐欺に騙されるのは情報弱者、いわゆる”情弱”だからと考えてしまいがちですが、実際は、人間の本能としての脆弱性を巧みに突かれてしまうことによって引き起こされる必然であるということ。
知識が無いことは詐欺に遭ってしまう要因の一つですが、知識さえ身につければ被害に遭うことを防げる、eラーニングなどで学習してもらうことがセキュリティ教育だと思っているなら、その考えを改め直す必要があります。
🧭 社会学的観点:なぜ“普通の人”が騙されるのか?
👔 1. 「肩書き」や「企業名」への無意識な信頼
詐欺師はしばしば、以下のような肩書きを偽装します:
- 銀行職員
- 警察官
- 大手企業のサポート窓口
これらは社会的に**「信じてしまいやすい立場」。
私たちは知らず知らずのうちに、その“肩書き”に従順になってしまう**性質を持っています。
🙊 2. 「恥」の文化と相談しにくさ
日本社会に根づく「恥をかきたくない」「騙されたと思われたくない」という心理。
結果として、怪しいと感じても誰にも相談せず、騙され続けてしまうというケースも少なくありません。
🧬 心理学的観点:「心」が判断を狂わせるとき
😰 1. 感情が先に動く「ヒューリスティック」
詐欺師が使う言葉は、感情を動かすトリガーに満ちています:
- 「アカウントが不正利用されています!」(恐怖)
- 「今なら○○が当たります!」(期待)
- 「このままだと訴訟になります」(焦り)
脳は一瞬で“感情”に支配され、理性的な判断力が麻痺してしまいます。
🧏♂️ 2. 「正常性バイアス」による思考停止
人は、日常とかけ離れた状況に出くわしたとき、
「これはきっと大丈夫」「自分には関係ない」と思い込み、
異常を異常と認識しない性質を持っています。
これが、詐欺を前にしても「まぁ大丈夫だろう」と思ってしまう原因です。
📚 実際の事例:「まさか自分が…」という落とし穴
- 🔧 ITエンジニアがサポート詐欺に遭った事例
→ 突然パソコンに表示された「ウイルス警告」と「サポート窓口の電話番号」。
普段は冷静な彼も、「音」「警告」「タイムリミット」の演出に冷静さを失い、遠隔操作を許可してしまいました。 - 🗣 詐欺セミナーの講師がロマンス詐欺に巻き込まれた事例
→ SNS上で偶然知り合った女性と交流し、信頼関係が築かれたと感じた数週間後、「身内の手術費用」の名目で多額を送金。
知識はあっても、「自分に限っては違う」と思ってしまったことが判断ミスの元に。
🎯 知っている人こそ「訓練」が必要な理由
📌 知識は“座学”で終わると身につかない
頭では理解していても、それを**「行動に移せるか」は別の話**。
実際に近い状況を**模擬体験(訓練)**することで、初めて「気づける力」が養われます。
💡「自分も騙されるかも」と思える人が一番強い
「自分は大丈夫」と思っている人ほど、詐欺の網にかかりやすい傾向があります。
逆に、「いつでも自分も騙される可能性がある」と思っている人は、
注意深く、冷静な判断ができるのです。
「詐欺に騙されるなんて情弱だからでしょ」なんて言っている人は、既に心の隙が自身の中に生まれてしまっているのです。
✅ まとめ:詐欺は“脳のバグ”を突いてくる
- 詐欺師は、私たちの心理の隙間を巧みに突いてきます。
- 知っていることと、気づけることは違う。
- “自分だけは大丈夫”という思い込みが、最大のリスクです。
🔐 本当に身を守るために必要なのは、“体験”を通じた気づき。
座学だけでなく、**訓練を通じて「体で覚える防御力」**を手に入れましょう。





