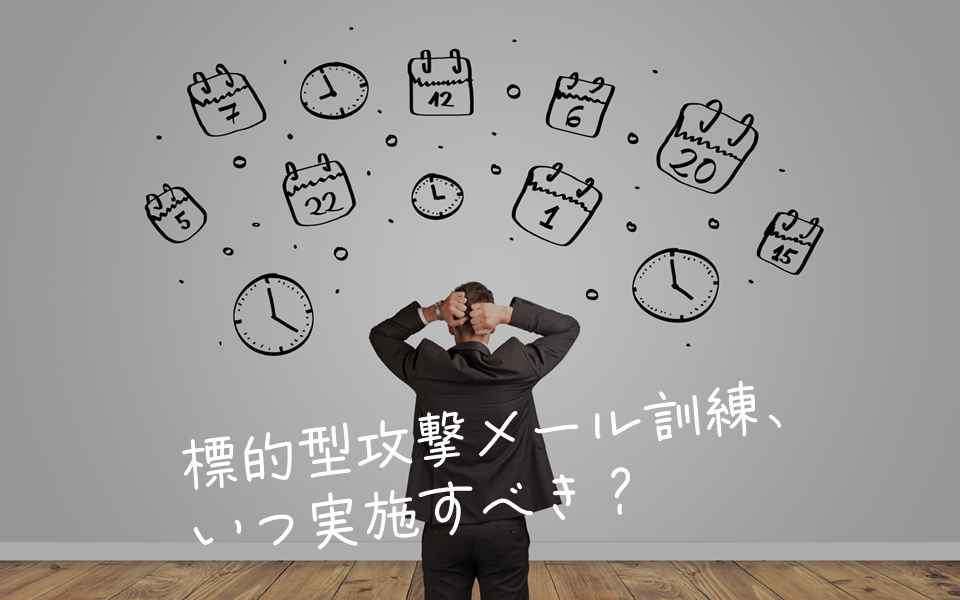
年1回 or 年2回の実施パターン別に最適な時期と注意点を考える
新年度を迎え、新入社員研修とあわせて標的型攻撃メール訓練を実施した企業もある一方で、ゴールデンウィークが明けて「そろそろ訓練を…」と動き出す企業もあるかと思います。
しかし、訓練は「実施すれば終わり」ではありません。
効果的なタイミングで実施することで、社員の記憶に残りやすく、セキュリティ意識の定着にもつながります。
理想を言えば四半期毎や毎月など、多い頻度で訓練が実施できれば良いのですが、予算や人員の問題、また、準備にかかる時間などを考えると、実施できるのは年に1回、多くても2回がやっとという企業も多いかと思います。
今回は、「年1回」と「年2回」訓練を実施するケース別に、それぞれおすすめの実施時期と、その決め方のポイントを解説します。
📅 年に1回訓練を実施する場合のおすすめ時期
✅ ベストな時期:5〜6月 または 9〜10月
| 時期 | 特徴 |
|---|---|
| 5〜6月 | 新入社員が一通り業務に慣れたタイミング。社内のセキュリティ意識が落ち始める時期でもあり、注意喚起に最適。 |
| 9〜10月 | 夏休み明けで気の緩みが出やすく、かつ年末に向けて詐欺が増加する時期の前哨戦として効果的。 |
🧭 ポイント
- 新入社員を含む全社員が対象になるタイミングを狙う
- 繁忙期(3月・12月など)を避ける
- 実施後に研修・フォローアップが行いやすい時期を選ぶ
訓練を年に1回しか実施できないという企業の場合は、その1回でできるだけ成果が得られるようにすることを考えざるを得ませんので、業種にもよるとは思いますが、繁忙期は避け、訓練の実施前後での研修やフォローアップと組み合わせて、余裕を持って取り組めるタイミングで実施することが鍵となってきます。
訓練自体は年に1回しか実施できなくても、eラーニングによる研修や注意喚起などは年間を通して実施できるかと思いますので、年に1度の訓練を中心に、その前後でどのような取り組みを行うかを考え、1年を通してどのような成果に結びつけていくかを設計することがポイントとなります。
📅 年に2回訓練を実施する場合のおすすめ時期
✅ ベストな時期:5〜6月 & 10〜11月
- 5〜6月:新年度の警戒感が薄れた頃合いで、最初の意識づけ
- 10〜11月:年末年始の攻撃リスクが高まる前に、再確認として実施
🎯 メリット
- 意識のリマインド効果が高まる
- 攻撃傾向の変化(実際の詐欺メール手口)にも対応できる
- 継続的な教育体制として社内外への信頼にもつながる
年に2回訓練が実施できると、社員教育の設計の幅が大きく広がります。1回目を前哨戦、2回目を本戦と捉えることもできますし、1回目と2回目でテーマを変えるといったこともできます。
少ない実施頻度でできるだけ多くの成果を得ようと考えれば、年1回の場合と同様、繁忙期を避けるのは基本になりますが、訓練実施に慣れてきて、社員のリテラシーも高いレベルが維持できている企業であれば、2回のうち1回はあえて繁忙期での実施にチャレンジしても良いと思います。
ただ、年に2回の場合も、四半期毎や毎月での実施に比べれば、やはり実施頻度に制限があることに変わりはないので、年に1回の場合と同様に、訓練以外の施策も織り交ぜながら、1年を通してどのような成果に結びつけていくかを設計することが必要です。
🧠 実施時期を決める際に考慮すべきポイント
- 業務スケジュールとのバッティング
- 決算期、異動期、繁忙期と重なると、社員がメールに注意を払えない可能性あり
- 決算期、異動期、繁忙期と重なると、社員がメールに注意を払えない可能性あり
- 他の研修・教育施策との連携
- セキュリティeラーニングや情報リテラシー教育と組み合わせると相乗効果あり
- セキュリティeラーニングや情報リテラシー教育と組み合わせると相乗効果あり
- 社内の“油断しやすい時期”を狙う
- 連休明けや期末直前など、気の緩みが出やすいタイミングは狙い目
- 連休明けや期末直前など、気の緩みが出やすいタイミングは狙い目
- 訓練内容との連動性
- 詐欺トレンド(例えば「電子帳簿保存法」「インボイス制度」など)に合わせた内容を出す場合、タイムリーさも重要
考慮すべきポイントは、年間の教育計画をどのように考えるかで変わります。社員のリテラシーが低く、まずはリテラシーを向上させることが最重要課題であれば、社員が集中して取り組める時期に設定することが望まれます。
逆にリテラシーが高く、身につけている知識が実践できることが最重要課題として設定されているのであれば、詐欺のトレンドを踏まえ、繁忙期などに関係なく実施することも一つの考え方になります。
⚠️ 実施時期を決める際の注意点
- 「毎年同じ時期」だとパターンを読まれる危険性あり
→ 年度ごとに微調整を加えて変化を持たせる
- 急な実施通知は反発を招くことも
→ 訓練実施の背景や目的を丁寧に周知
- 訓練後のフォロー体制も忘れずに
→ 問題行動の指摘だけでなく、学習の機会として位置づけることが大切
いずれにしても重要なポイントは、年間を通じた社員教育の計画をしっかり考えるということです。計画が無い状態では軸も定まらず、評価ポイントも定まらないので、実施時期を検討しても意見によって二転三転することになりかねません。
例えて言うなら、地図を持たずに進もうとしているような状態です。
訓練の実施内容を社内で検討しているけれど、なかなか話がまとまらないなあと感じている方は、今年は何を重要課題と位置づけるのか?など、地図に相当する”社員教育の計画”について、今一度確認されることをお奨めします。
✨ まとめ
| 実施頻度 | 推奨時期 | 狙い |
|---|---|---|
| 年1回 | 5〜6月 or 9〜10月 | 年間で1回の集中訓練による注意喚起 |
| 年2回 | 5〜6月 & 10〜11月 | 継続的な意識向上と攻撃トレンドへの対応 |
実施する“時期”は、訓練効果を左右する重要な要素です。
推奨時期は記載の通りですが、だからといって、この時期にしか実施するべきでないということではありません。
毎年、5〜6月 & 10〜11月に実施していた場合は、社員も”そろそろ訓練の時期だ“と何となく覚えてしまうので、訓練を実施しても効果が半減してしまうかもしれません。こうした心理があることを踏まえると、”あえて時期をずらす“ということも考え方としては必要です。
社員の業務状況や心理状態、また、訓練実施によってどのような成果を得ることを目的とするのか?といったことを踏まえて、最も効果が出るタイミングを見極めましょう。





