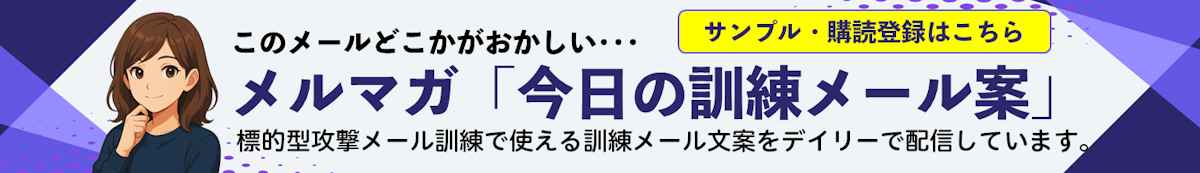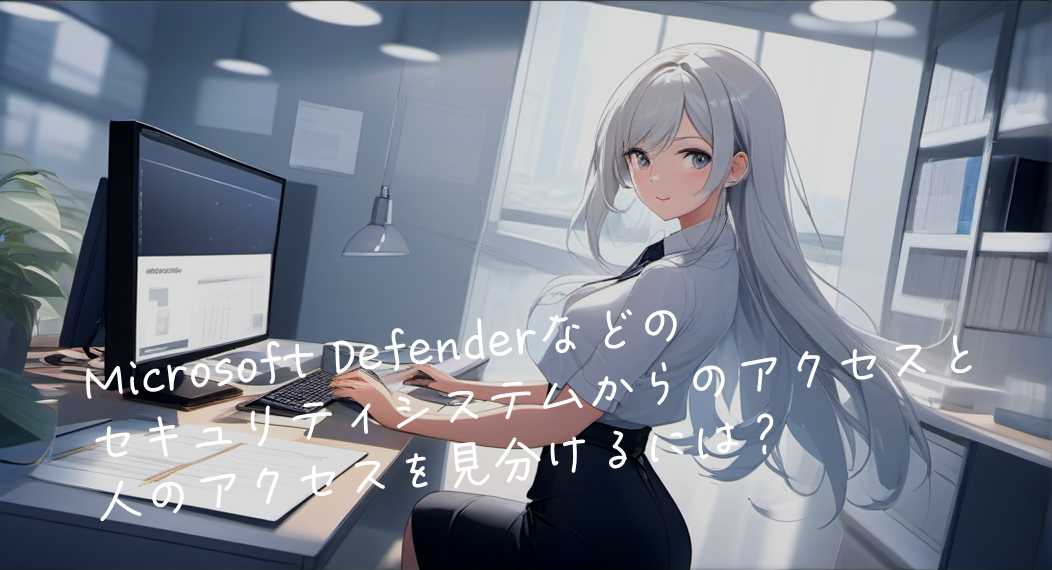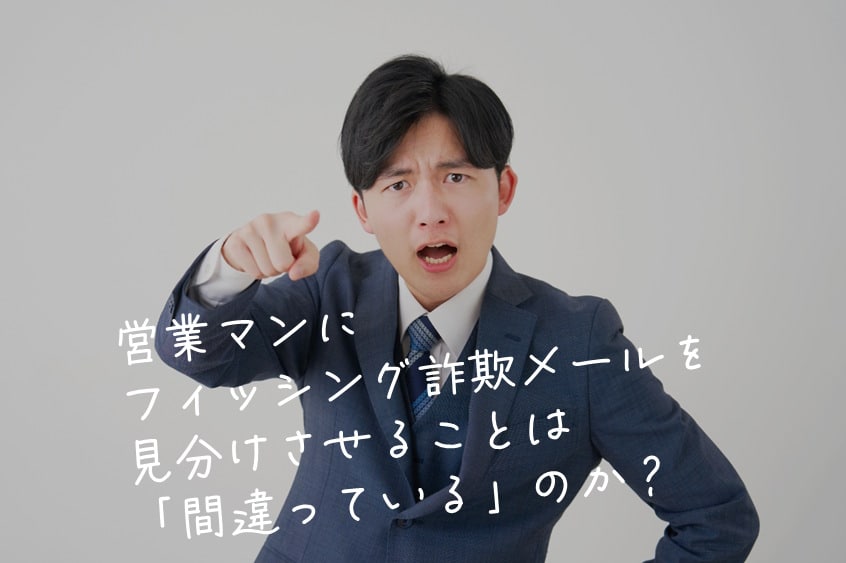
~もっともらしい主張をしてくる社員への処方箋~
「営業マンは営業するのが仕事であって、フィッシング詐欺メールを見分けるのは営業マンの仕事ではない」──。
そんな声を聞くことがあります。
実際、訓練実施後にアンケートを取ると、”フィッシング詐欺メールを見分けないで済むようにするのが情報システム部の仕事であって、それを棚に上げて現場に見分けさせようとするのは情報システム部の怠慢だ!”といった意見を頂いたりします。
一見もっともらしく聞こえるこの意見。
ですが、現代のビジネス環境では極めて危険な考え方だと言わざるを得ません。
この記事では、この主張がなぜ間違っているのかを深掘りし、営業活動とセキュリティ意識の密接な関係について解説します。
🔹 「営業マンは営業するのが仕事」というのは間違いではないが…
確かに、営業職の本分は「売上を作ること」「取引先との信頼関係を築くこと」です。
ここまでは誰も否定しません。
問題なのは、そこから飛躍して
「だから、セキュリティ対策は自分の仕事ではない」
と結論づけてしまう点にあります。
現代のビジネスにおいて、情報リテラシーは全社員に求められる基礎スキル。
営業マンであろうと経理であろうと、最低限のサイバーリスクへの意識は「仕事の一部」になっているのです。
🔹 営業マンがフィッシングメールを見抜けないと、何が起きる?
営業マンがうっかりフィッシング詐欺に引っかかった場合、
単なる「自分だけの失敗」では済みません。
具体的には、こんなリスクが待っています。
🚩 取引先の情報漏えい
➡ 信頼失墜、契約解除、取引停止。
🚩 社内の営業情報・機密情報流出
➡ 競合他社に営業戦略を知られてしまう。
🚩 個人情報漏えいによる損害賠償リスク
➡ 数百万〜数千万円規模の賠償が発生することも。
これらすべて、営業活動そのものを危うくするリスクです。
フィッシングメールを見抜くこと、フィッシング詐欺に騙されないことは、
**「営業活動を守るために不可欠なスキル」**だということが分かります。
🔹 なぜ「全社員に求められる」時代になったのか?
かつては、IT部門がセキュリティ対策を一手に担っていました。
しかし現在は、攻撃者が
- 人間の心理
- 忙しさ
- 信頼関係
を巧妙に突く**「人間狙い」の攻撃(ソーシャルエンジニアリング)**を多用する時代。
つまり、誰もがサイバー攻撃の標的になり得る時代になっているということです。
特に営業職は、外部と頻繁にやり取りするため、狙われやすい存在といえます。
こう言うと「営業マンが営業以外の仕事にまで神経を使わなければならないのでは仕事にならない!営業に集中できるようにすることが情報システム部の仕事だろうが!」と反論される方もいます。
しかし、サイバー攻撃の標的になり得るとわかっていて、自分で自分の身を守ることもできない営業マンと取引したいと考えるクライアントが居るでしょうか?
情報セキュリティに関する知識もろくに持たない営業マンと取引なんかしたら、自社の情報が漏洩してしまうのではないか?そう考えるのが自然なのではないでしょうか?
🔹 営業マンだからこそ「引っかかりやすい」特性
営業職には、次のような特徴があります。
- 取引先とのメールやり取りが多い
- 新規の連絡を歓迎しがち
- 「急ぎ対応」が日常茶飯事
- 社外からの添付ファイル受領も日常的
これらはすべて、詐欺メールに引っかかるリスクを高める要素です。
だからこそ営業マンには、
最低限のフィッシング耐性が求められるのです。
🔹 まとめ:セキュリティ意識は「自分を守るため」のスキル
「営業マンは営業だけしていればいい」。
この考え方は、もはや時代遅れです。
フィッシング詐欺に騙されることは、単にIT部門に迷惑をかけるだけでなく、
自分自身の営業成績、キャリア、信頼、そして会社全体にまで甚大な被害を及ぼします。
だからこそ、営業職も含めたすべての社員が最低限のセキュリティリテラシーを持つことが、
「自分の仕事を守る」ために必須なのです。
営業マンにとって、フィッシング詐欺対策は「余計な負担」ではなく、
営業活動を守るための必須スキルです。
訓練を実施する側は、訓練実施に否定的な人達に対して、
- 単なるルールとしてではなく
- 各社員が行っている業務活動と結びつけて
- 自分たちを守るためだと
伝えることで、現場の意識は確実に変わっていきます。
✅ 「売上、そして会社の信用を守るためにセキュリティを意識する」
このマインドセットを、社内全体に根付かせていきましょう!