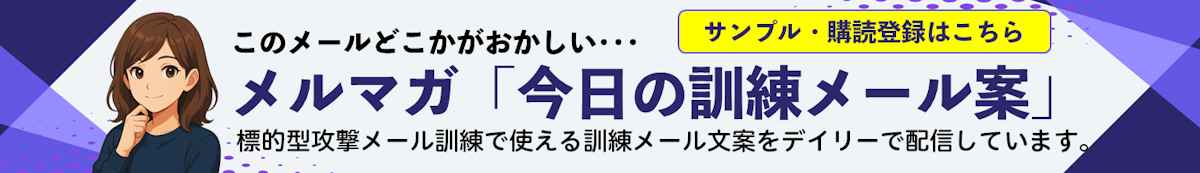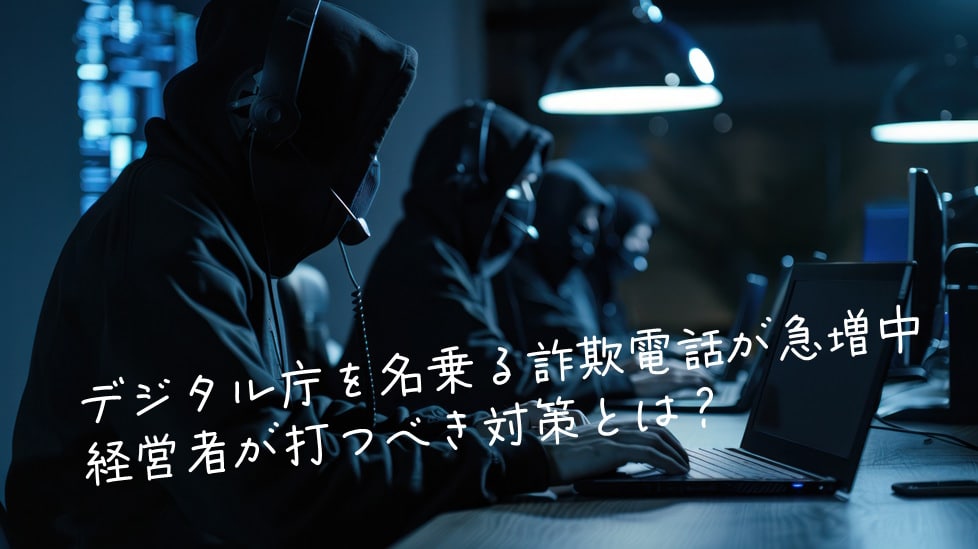
“会社の電話に出た社員”から始まるリスクと、経営者が打つべき対策とは?
📌 はじめに:いま、詐欺の主戦場は「電話」です
セキュリティ対策というと、
ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、メール訓練…といった**“デジタル領域の話”**を想像しがちです。
ところが最近、“アナログな電話”による詐欺被害が急増しています。
しかも、それが国の機関をかたる巧妙な手口だとしたら──?
◆ 実際に起きている:デジタル庁を装った詐欺電話の例
「こちらデジタル庁です。マイナンバーに不正アクセスがあった可能性があり、ご本人確認が必要です。」
「本人確認のために、お名前と生年月日、マイナンバー、銀行口座番号をお願いします。」
このような電話が、全国各地の企業や家庭にかかってきています。
声のトーンは落ち着いており、あたかも公的機関の職員のよう。
声を聞く限り、どこにでもいそうな普通の方という印象です。
背景には事務処理音が聞こえ、信じてしまいそうな空気感すら演出されています。
筆者の自宅にかかってきた電話では以下のようなものもありました。
「こちらデジタル庁です。お使いの携帯電話から大量の迷惑メールが送信されており、緊急措置として2時間以内に利用を停止する最終通告となります。」
「電話番号を確認させていただきたいので、お使いの携帯電話の番号をお願いします。」
◆ ある中小企業で実際に起きたシナリオ
📞 13:48 総務部電話応対記録より
「はい、◯◯株式会社です」
「私、デジタル庁の◯◯と申します。本日、御社で管理されているマイナンバー情報に関する緊急連絡でお電話しています。」
「今すぐ、従業員の登録情報の一部確認が必要です。○○様のフルネームと生年月日を教えてください」
このようにして、社内の新人社員が個人情報を口頭で伝えてしまったケースが報告されています。
もちろん、後日その「デジタル庁職員」が本物でなかったことが判明。
情報はどこかに転売され、さらなる詐欺やなりすましの温床になったと考えられています。
◆ 経営リスクは「個人」ではなく「会社」に及ぶ
- 社員が電話で情報を伝えただけで、
- 顧客の個人情報が流出
- マイナンバー情報漏えいによる報告義務
- 社内調査・外部報告対応による業務停止・風評リスク
企業として、「知らなかった」「うっかりだった」では済まされない時代です。
❗ 情報漏えい事故の原因の多くは、技術的な突破ではなく、
**“人の判断ミス”**です。
◆ 詐欺電話への備えは、「社員教育」以外にありません
電話口の相手が詐欺師かどうかを見抜く判断力は、
ルールだけでは身につきません。
だからこそ、企業としての対応は、
- ✅ 社員全体に詐欺電話の手口と対処法を周知すること
- ✅ 電話応対のロールプレイや疑似訓練を行うこと
- ✅ 「答えてはいけない情報」の明確化と共有マニュアル化
といった、“日常的な教育”が不可欠です。
詐欺電話は“個人が被害に遭うもの”で、”会社の業務とは関係がない”と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
あなたの会社の社員がプライベートで被害に遭ってしまい、金銭的に困窮するなどすれば、業務どころではなくなって、間接的に会社の業務に多大な影響が生じてしまうかもしれません。
社員のプライベートを守ることも、会社を守るためには必要なことなのです。
◆ 教育コストより、事故対応コストのほうがはるかに高い
| 内容 | 目安費用 |
|---|---|
| 社員向け詐欺電話対策教育(動画・訓練) | 数万円~(無償公開されているものを活用すれば0円) |
| 実被害発生時の調査・報告・対策費用 | 数十万円~数百万円 |
| 社会的信用の低下 | 金額換算不可(取引停止・顧客離れ等) |
📉「起きたあとに後悔する」よりも、「起きる前に備える」方が、コストもリスクも圧倒的に軽減できます。
◆ 経営者として問われる視点:「人」のセキュリティも会社の責任
「セキュリティ対策=IT部門の話」と思われがちですが、
詐欺電話のような社会的攻撃(ソーシャルエンジニアリング)への対策は、全社員の共通課題です。
そしてそれは、最終的には経営判断の領域に入ってきます。
- 情報漏えいによって誰が責任を問われるか
- 会社の信頼をどう守るか
- 顧客や社員に何をもって「安心」を提供するか
✅ 経営者に求められるのは、“技術的対策”だけではなく、“人への投資”です。