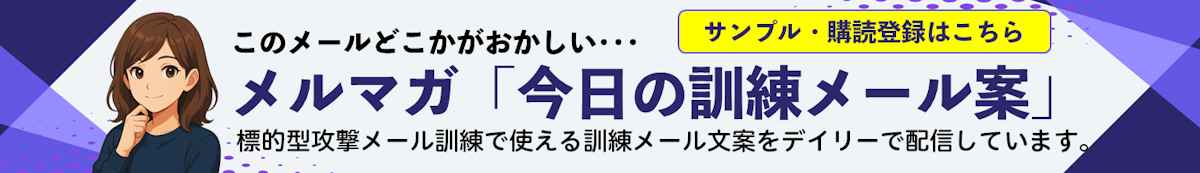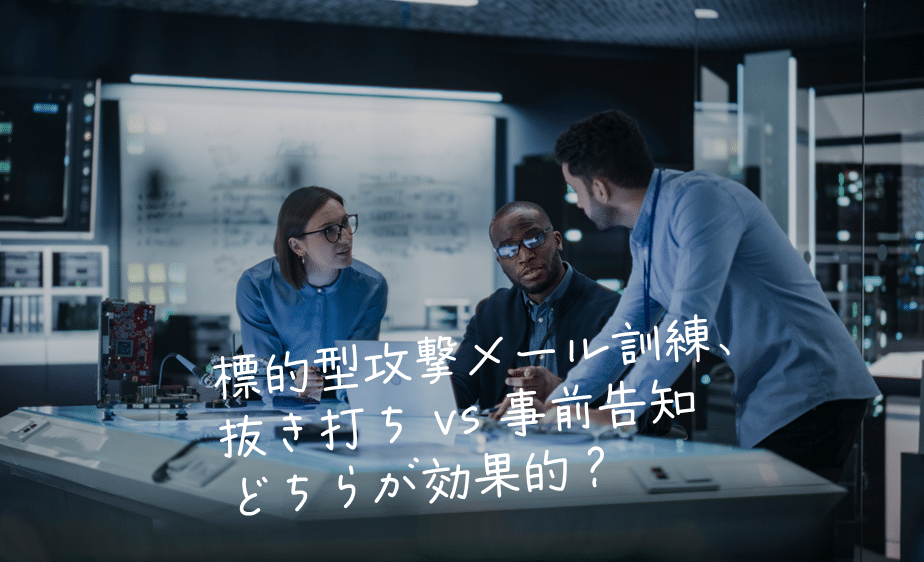
標的型攻撃メールは、企業の情報セキュリティを脅かす最も身近で深刻な脅威の一つです。
その対策として有効なのが「社員を対象とした模擬攻撃訓練」として、いわゆる”標的型攻撃メール訓練”があります。
この訓練について、「抜き打ちで実施するべきか?」「あらかじめ告知して実施するべきか?」
この問いに頭を悩ませるご担当者様は多いのではないでしょうか。
今回は、それぞれの方法のメリット・デメリットを比較しながら、効果的な訓練の進め方をご紹介します。
✅ 抜き打ち訓練のメリット・デメリット
【メリット1】リアルな判断力が試せる
事前に知らされていない分、実際の攻撃を想定した「その場の判断」が必要になります。
社員がどんな行動をとるかを観察しやすく、訓練としての効果も高くなります。
【メリット2】危機意識を強く植え付けられる
訓練メールをうっかりクリックしてしまった社員にとっては、「自分も引っかかった…」という衝撃が、強烈な学びになります。
【デメリット1】不信感や混乱を招く可能性
「騙された」と感じた社員が、企業や管理部門に対して不信感を抱くケースもあります。
また、ウイルス感染を装うような訓練内容の場合、混乱や問い合わせが殺到することもあります。
もし、本物だったら?という不安感から、パソコンをネットワークから切り離し、日中は業務が完全に止まってしまったという事例も実際にあります。
また、訓練メールに反感を覚えた社員がクレーマーとなり、モンスター社員として問題を起こすような事態にまで発展してしまったといったケースもあります。
【デメリット2】訓練後のフォローが必要不可欠
心理的負荷を与える可能性があるため、訓練後の振り返りやフォロー体制を整えることが重要です。
✅ 事前告知訓練のメリット・デメリット
【メリット1】社員の協力が得やすい
「訓練であること」をあらかじめ伝えることで、社員が安心して参加しやすくなります。
セキュリティ教育の一環として位置づけやすい点も利点です。
【メリット2】心理的安全性を確保できる
特にメンタル面への配慮が必要な部署や社員が多い職場では、安心感を持って訓練に取り組んでもらえます。
【デメリット1】実戦的な行動評価が難しい
「訓練だ」と分かっていれば、メールを開封しない・クリックしないといった慎重な行動をとりがちです。そのため、本番さながらの反応を引き出しにくい側面があります。
また、わかった気になって終わらせてしまい、時間の経過と共に訓練を実施したことすら忘れてしまうことで、結局何も身についていないといった結果となってしまうこともあります。
【デメリット2】訓練の効果が慣れで薄れることも
定期的に同じような訓練を告知付きで実施すると、社員にとって**「イベント化」してしまい、緊張感が薄れる**こともあります。
もっと実戦的な訓練をして欲しいと考える前向きな社員からは、訓練の方針にがっかりしてしまい、やる気を失ってしまうといったリスクもあります。
🔍 結局どちらが良い?おすすめの進め方は…
結論から言えば、企業の風土や目的に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
ただし、多くの企業で取り入れられているおすすめの方法は…
🔁 「初回は事前告知 → 徐々に抜き打ち型へシフト」
このように段階的にレベルを上げていくことで、社員の理解と協力を得ながらも、実践力を養うことができます。
🔁 「手口を学んでもらうためにあえて事前告知」
訓練は必ずしも、不審なメールを見抜けるかどうかを試すものとは限りません。攻撃者が私たちを騙そうとする手口を覚えてもらうために、わざとクリックしてもらって、どのような流れで騙されるのか?を知ってもらうというのもまた、模擬の攻撃メールを使う訓練だからこそできることです。
🔁 「組織長など、一部の人にだけ事前告知」
訓練実施によって社内に混乱をもたらさないためには、組織長など、万一、混乱が発生したとしても速やかに場を鎮めてもらえる方に対応してもらえるようにすることが必要です。このため、社内の主要メンバーにだけ事前に伝えておくというやり方もあります。
但し、中には自組織の成績を良くしようと、内緒で組織内に知らせてしまう方もいらっしゃるので、そうしたことがないよう、訓練実施の目的と意義を共有しておくことも大事なポイントです。
📝 まとめ
| 比較項目 | 抜き打ち訓練 | 事前告知訓練 |
|---|---|---|
| 実践性 | ◎ | △ |
| 協力の得やすさ | △ | ◎ |
| 心理的安全性 | △ | ◎ |
| 教育効果 | ◎(印象に残る) | ○(理解しやすい) |
以上の通り、抜き打ちも事前告知も一長一短があり、どちらが優れているとか、どちらでやるべきといった正解はありません。
どちらもやったことがないのであれば、実際にやってみることで初めて見えてくることもあるので、それぞれの訓練について、実際にやってみたらどうなりそうかを想定し、実際にやってみたらどうなるか?を試してみると良いと思います。
💡 最後に:訓練の目的は“罰すること”ではなく“備えること”
標的型攻撃メール訓練の目的は、社員を罰することでも責めることでもありません。
あくまで企業全体のセキュリティリスクを減らすための教育・啓発活動です。
訓練方法の選択は慎重に、そして社員との信頼関係を大切に。
そのうえで、「いざというときに誰もが落ち着いて行動できる組織づくり」を目指しましょう。
社員から反発されずに訓練を成功させるポイントは、訓練を実施することの目的と意義を会社全体に浸透させることにあります。