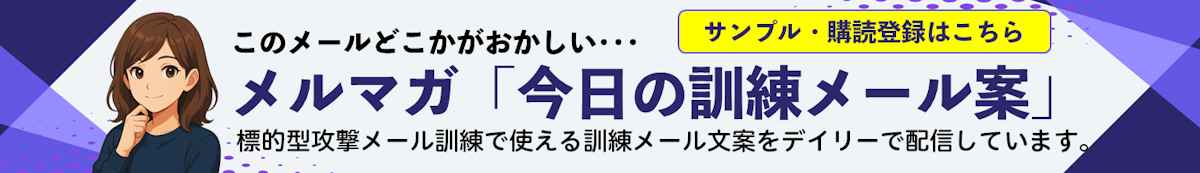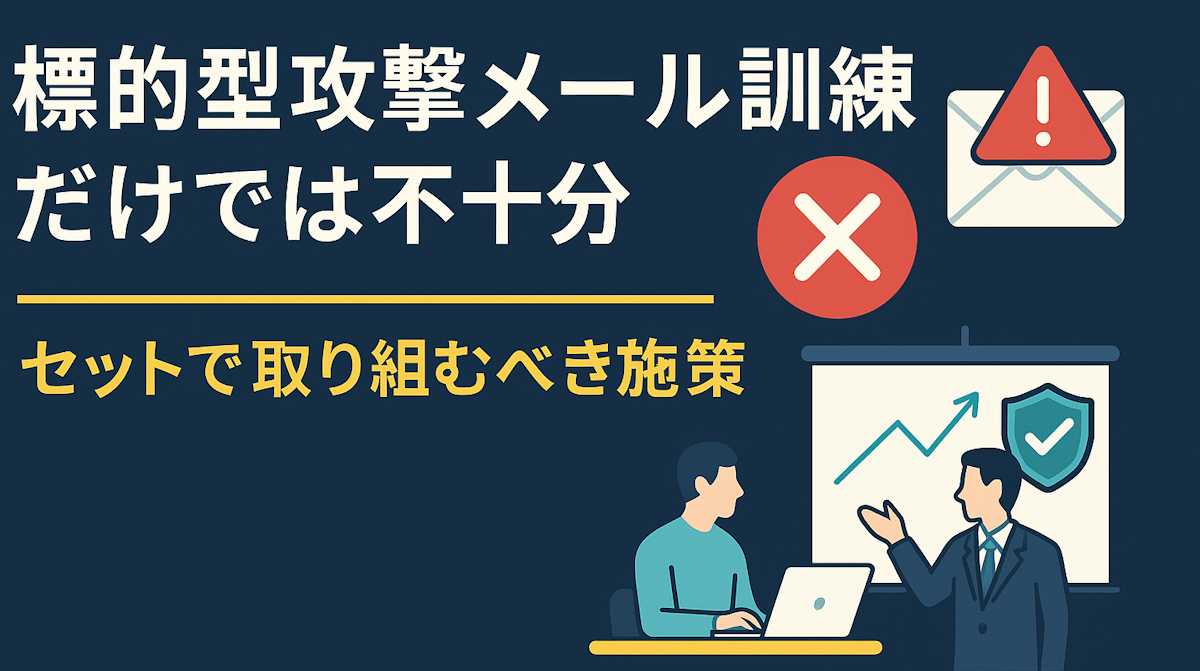📌 はじめに:見落とされがちな“わかりやすい詐欺メール”
標的型攻撃メール訓練を実施する際、
「どうせやるなら、実際の攻撃に近い“巧妙なメール”で訓練しないと意味がない」
とお考えの担当者は多いのではないでしょうか。
ですが――
「これはさすがに誰も引っかからないだろう」と思えるような、稚拙で怪しいメールでも、実は驚くほど多くの人が開封・クリックしているという事実があります。
💡誰が見ても怪しいメールでも、意外に開封されているという事実
【訓練メール事例①】
件名:「アカウントが凍結されました!」
差出人:support@amaz0n-pay-japan.cn
本文:
アカウントが凍結なりました。たいせつなアカウント守ってください。
確認するには↓リンク押して。
https://bit.ly/3xXXXXX
👀 日本語も変、URLも短縮、差出人のドメインも怪しい。
でも――実際の訓練ではクリック率が10%以上になることも珍しくないという驚きの結果に。
なぜ、そんなメールが開かれてしまうのでしょうか?
🧠 なぜ“あからさまに怪しいメール”が開かれるのか?
クリックしてしまった社員にヒアリングを行ったところ、次のような声が聞かれました。
- 「ちょうどAmazonを使った直後だったから、反射的に確認した」
- 「スマホで見たら、文字がうまく表示されず判断できなかった」
- 「気になったから、クリックして中身を確かめてから判断しようと思った」
- 「怪しいとは思ったが、URLからは判断が付かなかったから」
- 「アカウントが凍結されたら困ると思ったから」
つまり――
私たちが「こんなの普通は見破れる」と思っている前提が、現場では通用しないのです。
また、怪しいかどうかわからないからクリックしてみるといった行動を取る人も居るということも見逃せません。
❌ 訓練メールは“巧妙”である必要はない
訓練を「現実の攻撃と同じようにリアルにしなければ意味がない」と考えると、どうしても内容を凝ってしまいがちです。しかし、セキュリティ教育においては、訓練の“難易度”よりも“教育効果”のほうが大切です。
- 初学者には、まず「わかりやすい詐欺メール」を題材にした方が効果的
- 難易度が高すぎると、「自分には無理」と感じさせてしまい逆効果
- 意識を高めるステップとして、「気づける成功体験」が重要
💬 リテラシーが高くない社員には、むしろシンプルで“見破りやすい”訓練の方が効果的。
- 「怪しいメールに気づけた」という“成功体験”が次の警戒心につながる
- 「簡単すぎた」と思った社員でも、実際には見落としている点を知ることで再学習になる
リテラシーが高い社員には「こんなわかりやすい訓練メールじゃ訓練の意味がない」と思われてしまうかもしれませんが、優先すべきは、そんなわかりやすいメールであってもクリックしてしまう人を一人でも減らすことですから、「わかりやすい詐欺メール」であっても10%以上も開いてしまう人がいるのであれば、わかりやすい詐欺メールを使った訓練を実施することも検討するべきです。
❓誰も開かなかったら訓練の意味がないのでは?
訓練メールを送っても、誰も訓練メールを開かなかったら訓練の意味がないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、開いてしまいやすい内容を考えるあまり、いつの間にか開かせることが目的となってしまうこともあります。
より実践的な内容での訓練ということであれば、それもあながち間違いとは言えませんが、「気づく力」を身につけてもらうことが主目的である場合は、結果として「気づいたことによって誰も開かなかった」というのは、それはそれで訓練の成果の一つです。
開かせることばかりが訓練ではありません。
✅ 実際にクリックしてしまう人が多かった“あえて稚拙な”訓練メール例3選
以下に、不審だということがわかりやすい内容に見えて、意外とクリックしてしまう人が出やすい訓練メールのパターンを3つご紹介します。
📮 事例①:怪しすぎる日本語
あなたアカウントは重要問題で凍結なってます!
今すぐにパスワード送ってください!不自然な日本語であっても、シンプルで短いメールは、長いメールと比べて不審さに気づける箇所が少なくなるため、「ヤバい」などと思って確認しようとしてしまう心理が働きやすく、意外とクリックされてしまうものです。
📮 事例②:画像1枚だけのメール
- 本文なし。画像だけで「請求書をご確認ください」と書かれたPNG画像が貼ってあるだけ。
- 画像にリンクが埋め込まれている。
シンプルで短いメールと同様、画像だけでシンプルな文言しか書かれていないようなものも、やはり不審さに気づける箇所が少ないため、クリックされてしまいやすい傾向があります。
QRコードを悪用したフィッシング詐欺もこのパターンに近いかもしれません。
📮 事例③:差出人が”社長”
From: 社長 <president@xxxx.co.jp>
Subject: 今日中に至急確認してください「社長や上司、取引先から来ている」というだけで無条件でメールを開いてしまうケースは多いと思います。
“社長からの指示は絶対“という刷り込み、また、”社長からの指示を無視するなどあってはならない”という心理が、内容を疑うという思考を停止させ、指示通りに行動してしまうという結果に繋がりやすいのです。
上下関係を悪用したメールは開いてしまいやすいものの一つであり、ビジネスメール詐欺(Business Email Compromise)はまさにこのパターンと言えます。
🎯 訓練の目的は「気づける人を増やすこと」
訓練を設計する上で大切なのは、「実際の攻撃に似ているかどうか」ではありません。
いかに社員一人ひとりが“気づける目”を持つようになるかが、最も重要なポイントです。
そのためには、
✔ 難易度を段階的に上げる
✔ 初級者にも「気づけた」という体験を与える
✔ あえて“わかりやすい詐欺メール”を使って基本に立ち返る
といった工夫も必要です。
リテラシーが高くない人には、不審さに気づくための目の付け所を増やしてもらう、
リテラシーが高い人には、自分に慢心している点がないかどうか初心に返って気づいてもらう、
そんな設計を目指したいものです。
✍ 訓練の“本当の目的”を見失わないで
「高度な攻撃を想定したリアルな訓練」は、もちろん必要な場面もあります。
ですが、社員のレベルに合わない訓練は、ただの自己満足に終わってしまう恐れもあります。
📣 訓練の目的は、「社員が被害者にも加害者にもならないように育てること」。
そのためには、あえて“稚拙な訓練メール”から始める勇気も必要です。
訓練実施担当者はどうしてもリテラシーが高くなってしまうだけに、やさしすぎる訓練メールは「意味がない」として避けてしまいがちですが、訓練メールを受け取るのは担当者ではなく、現場の社員です。
現場の社員にとって適切かどうか?これを訓練実施担当者は常に忘れないようにしたいものです。