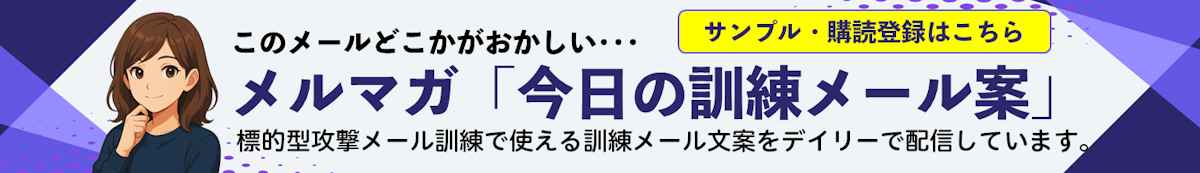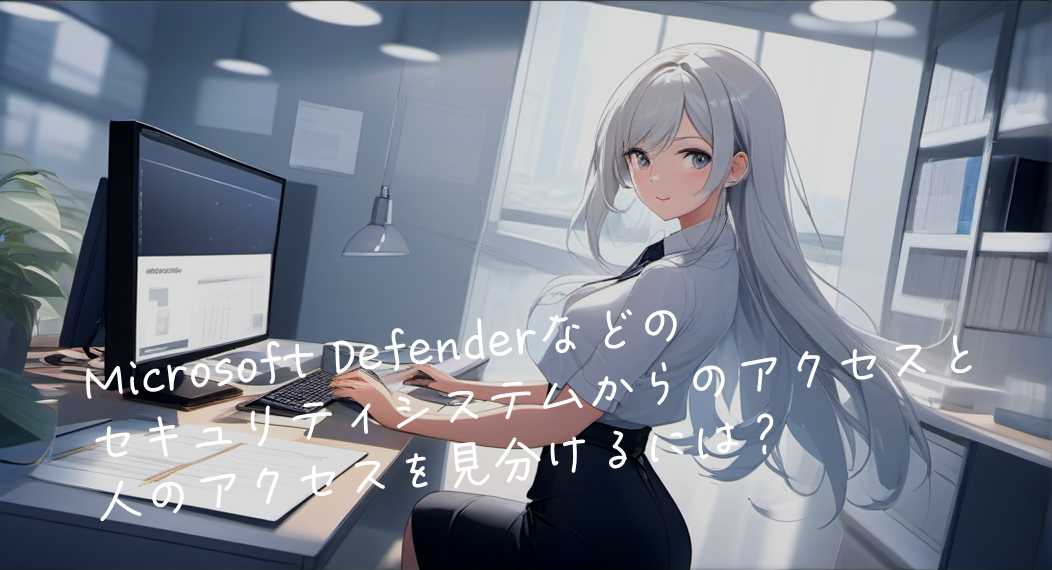📌はじめに|“だます訓練”に潜むジレンマ
慶應義塾大学をはじめとする教育機関で、「資料にあえて非表示のメッセージを埋め込み、生成AIに課題を丸投げした学生を見抜く」という取り組みが話題になりました。
これは、**“実際に体験させて、気づきを与える”**という教育手法の一例です。
この考え方は、標的型攻撃メール訓練にも通じるものがあります。
実際に偽メールを開いてしまったり、リンクをクリックしてしまうことで、「自分も騙される可能性がある」とリアルに実感してもらう──。これは啓発の上で非常に有効な方法です。
しかし同時に、「だます」という手法には倫理的な問題も内包しています。
訓練とはいえ、相手を驚かせたり、不快にさせたりしてしまっては、訓練の意義が揺らぎかねません。
今回は、**標的型攻撃メール訓練を実施する上で忘れてはならない“倫理の視点”**について、掘り下げていきます。
⚠️訓練が“やりすぎ”になるとき
✔ 訓練でよくある手法と、そのリスク
| 💻訓練内容 | 🚨倫理的リスク |
|---|---|
| 本物そっくりの取引先を装ったメール | 実在の企業との信頼関係を損なう可能性 |
| ウイルス感染を装った画面や音声の表示 | ストレスや不安感を引き起こす |
| 人事通知・賞与連絡を装うメール | 期待を裏切り、社員のモチベーション低下 |
| 懲戒・降格・評価に関する通知 | ハラスメントとして問題視される恐れ |
訓練を受けた側が**「騙された」「バカにされた」と感じてしまえば逆効果**。
情報セキュリティ意識の向上どころか、訓練への反感や不信感を生むことになりかねません。
📣SNS時代は“炎上”の危険も
訓練のつもりで実施したメールが、
「これはハラスメントでは?」
「精神的にきつかった…」
と、社内外で批判の対象になるケースもあります。
現代は、1人の不満がSNSで一気に拡散される時代です。
特に、標的型攻撃メール訓練のように“だます”要素がある手法は、説明が不足していると炎上の引き金になりやすく、そこで発生した禍根が今後の社員教育の進め方にも影響を及ぼしかねないリスクがあります。
実際、訓練メールに腹を立てた社員がその後、セキュリティ担当からの研修の呼びかけや、セキュリティ対策に関するアナウンスなどを無視するようになったという事例もあります。
🧭倫理的に適切な訓練とは?
では、どのような配慮をすれば、訓練の効果を保ちつつ、倫理的な問題を避けられるのでしょうか?
✅訓練設計で配慮すべきポイント
- 「驚かせる」ではなく「気づかせる」設計にする
- 実在の人物・取引先・社内制度を模倣しない
- 訓練後にしっかりと「意図の説明」と「フォロー」を行う
- ストレスを感じやすい人への影響を想定する
- 目的を常に“教育”に置く。「反省させる」「懲らしめる」意図は排除
訓練はあくまでも「学びの場」。
社員の尊厳と心理的安全性を守ることは、効果的なセキュリティ教育に不可欠です。
標的型攻撃メール訓練はともすると、誰も開かないような訓練メールでは訓練にならないと考え、”訓練メールを開かせてやろう”として、いつのまにか社員を”だます”ことが目的となってしまうことがあります。手段が目的にすり替わってしまう典型例ですね。
訓練を実施する担当者は、このようなことにならないよう、常に自問自答を繰り返す必要があります。
また、社員を叱責するようなことはしてはいけないと訓練実施担当者自身が認識していても、会社全体としてその認識が共有されていないと、訓練メールに騙されてしまった社員を上長が叱責するといったことが起きてしまうこともあります。
🔄リアル体験 vs 倫理のバランスをどう取るか?
訓練効果を高めるには、ある程度リアルな内容も必要です。
しかしそれが、対象者を過度に驚かせたり、不快にさせたりする内容になっていないか――。
その判断基準となるのが、**「その訓練を自分の家族や親しい人に対しても行えるか?」**という視点です。
もし「これはやりすぎかも…」と感じるなら、それは一線を越えているサインかもしれません。
📝訓練は“心に残る”ことが目的。でも…
📍標的型攻撃メール訓練の目的は、「痛みを与えること」ではなく、“気づき”と“自衛力”を育てることです。
そのためには、“体験させる”手法と、“尊重する”姿勢を両立させる必要があります。
私たちは「訓練だから、だましても良い」と思いがちですが、
本当に重要なのは、**「訓練だからこそ、丁寧な配慮が必要」**という視点です。
📌訓練担当者の皆様へ
御社の訓練、社員に“信頼”されていますか?
“気づき”は与えたい。でも“怒り”は買いたくない。
そんなジレンマに悩む担当者の方こそ、
倫理的に配慮された訓練設計を一度見直してみてください。
✔ 実名の使用や過剰な演出はしない
✔ 後味の悪さを残さない構成を考える
✔ フォローアップを忘れない
といった、倫理的に安心して使える設計ができているかどうか、また、その設計思想が社内に共有されているかどうかは、見直すポイントの一つです。
🎯最後に
訓練は「驚かせる」ことが目的ではなく、
「守る力を育てる」ことが目的です。
セキュリティ教育と言えば、”難しい”、”つまらない”、”面倒くさい”と思われ、適当に聞き流して終わりにしてしまうような社員も少なくないと思います。
しかし、AIを使うことが当たり前となり、フィッシング詐欺メールも昼夜関係なく送られてくるなど、全ての人の日常にセキュリティが溶け込み、普段自分が何気なく利用しているものにリスクが潜んでいることを“知らなかったでは済まなくなりつつある”現代においては、もはや、聞き流して終わりにするようなことはできない状況となってきています。
だからこそ、社員の誰もがセキュリティ教育を受けることに前向きになれるよう、
その目的を見失わず、信頼される訓練設計を目指したいものです。