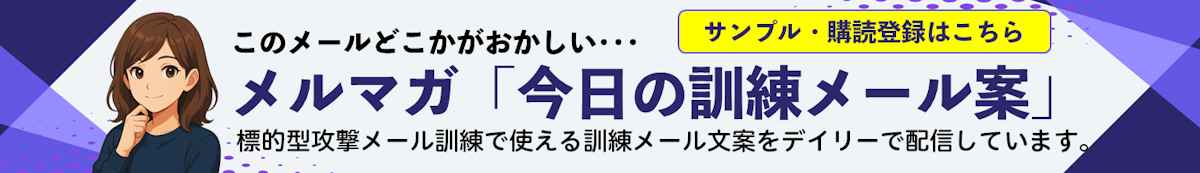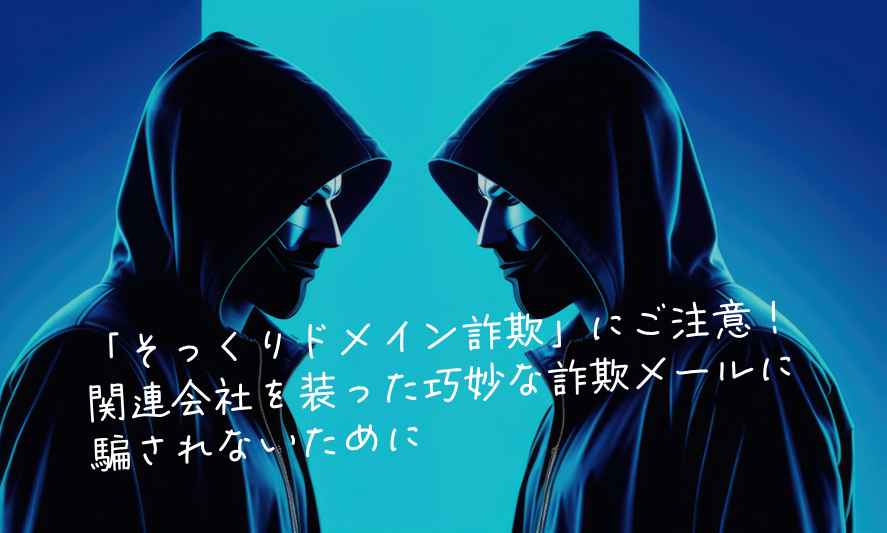
🤔ドッペルゲンガードメインってご存じですか?
入社したばかりの頃は、関連会社の名前やドメイン(メールアドレスの後ろの部分)をすべて覚えているわけではありません。
そんな不慣れな状況を狙ってくるのが、「ドッペルゲンガードメイン」詐欺です。
本記事では、似たようなドメインを使った詐欺メールに騙されないための注意ポイントを、わかりやすく解説します!
🕵️♂️ そもそも「ドッペルゲンガードメイン」って?
「ドッペルゲンガー」とは、そっくりさんのこと。
つまり「ドッペルゲンガードメイン」とは、本物にそっくりなドメイン名を使って、本当の会社から来たメールのように見せかける詐欺手口です。
たとえば…
| 本物 | 偽物(詐欺メール) |
|---|---|
@abc-company.co.jp | @abc-comapny.co.jp(文字を入れ替え) |
@abc-company.co.jp | @abc-company.co(末尾を省略) |
@abc-company.co.jp | @abc-cornpany.co.jp(英字を似た字に置換) |
👀 パッと見では気づきにくいので、油断すると簡単に騙されてしまいます。
実際、標的型攻撃メール訓練でドッペルゲンガードメインを差出人アドレスやリンク先のURLに用いると、一定数騙されてしまう人がおり、「よく似ていたのでつい…」といった理由を聞くことが多いので、本物そっくりなドメイン名を使われることが如何に危険なことであるかがよくわかります。
🎯 社員教育で伝えるべき3つの重点ポイント
1.差出人アドレスを「フルで確認」させる
【教育ポイント】
- 表示名だけを見て安心しないよう指導する。
- @以降のドメイン部分を必ず確認させる。
- 「.co.jp」「.com」など末尾の違い、小さな文字の違い(rn ⇔ mなど)に注意を向けさせる。
【伝え方のコツ】
- メールソフト(例:Gmail)の「詳細表示」機能を実演して見せると理解が早いです。
2.メール内のリンクは即クリックさせない
【教育ポイント】
- メール内の「こちらをクリック」などの誘導にはすぐに反応しないよう徹底。
- 重要な案内の場合は、公式サイトを自分で検索してアクセスし直す習慣を持たせる。
【伝え方のコツ】
- 実際に「公式サイト検索 → 自力アクセス」の流れをハンズオン演習で体験させると効果的です。
3.違和感を覚えたら「相談」を促す
【教育ポイント】
- 少しでもおかしいと感じたら、自己判断せずすぐ相談することを徹底。
- 恥ずかしいと思わず、「おかしいかも」と感じたら確認する文化を作る。
【伝え方のコツ】
- 実例を交えて、「一人で抱えた結果、大きな事故になったケース」と
「相談したことで被害を未然に防げたケース」を比較して紹介すると、意識づけしやすくなります。
🚨ドメイン名とは何か?も伝えておきたい
インターネットに明るい方であれば、ドメイン名とは何か?について語るまでも無くご存じかと思いますが、普段からあたりまえのように使われているが故に、ドメイン名とは何か?について知らないまま使っている方も実は多いかもしれません。
ドメイン名が何か?について知っていれば、末尾が.cnで終わっているドメイン名は中国のドメイン名だとわかるので、これは不審なメールであると気づきやすいですが、ドメイン名について知らないと、.cnで終わっているメールアドレスでメールが送られてきても不審さに気づかないので、すんなり騙されてしまうかもしれません。
このようなことが起きてしまうのを防ぐには、”そんな基本的なこと知っていて当然”とは考えずに、ドメイン名とは何か?について知ってもらう、また、知っているかどうかを確認するという機会を設けることをお奨めします。
🛡️ 教育のまとめ:育てたいのは「慎重な初動」
| 育成する習慣 | 具体的な行動 |
|---|---|
| メールアドレスをフルで見る | ドメイン末尾までチェック |
| すぐリンクを押さない | 自力検索アクセス |
| 違和感を相談する | 早めに共有・報告 |
社員に求めるのは、完璧な見抜き力ではありません。
まずは、
✅ 止まる
✅ 確認する
✅ 相談する
この3ステップを自然に取れるようになることが重要です。
「入社したばかりで知識や経験が無いのだから見抜けるわけがありません。だから見抜けなくたって仕方ないですよね」という言い分に対しては、「だからこそ、ちょっとした違和感を見逃さず、面倒でも立ち止まって確認、相談することが大切」ということを根気よく伝えていくことが必要です。
📚 実践補足:効果的な教育方法
- 🖥️ デモンストレーションを取り入れる
→ 偽物メールを見せながら、どこに注意すべきかを解説
- 📝 ミニクイズ形式で理解度チェック
→ 本物と偽物のドメインを見分ける練習
- 📄 チェックリストを配布
→ 日常的に注意できるポイントを明文化して配布
🚀 最後に
セキュリティ教育で最も大切なのは、
社員が「なんとなくおかしい」と感じたときに立ち止まれる環境を作ることです。
社員一人ひとりの小さな違和感が、
大きな情報漏洩や被害を防ぐ第一歩となります。
焦らず、繰り返し、
わかりやすく丁寧に伝えていきましょう!